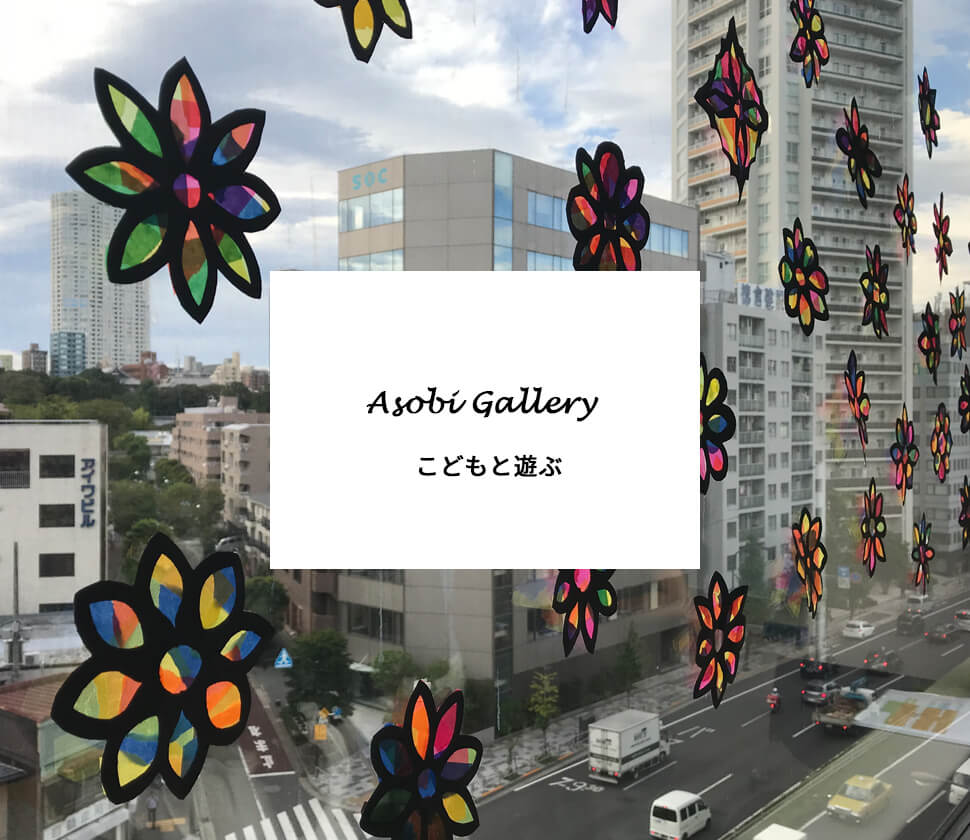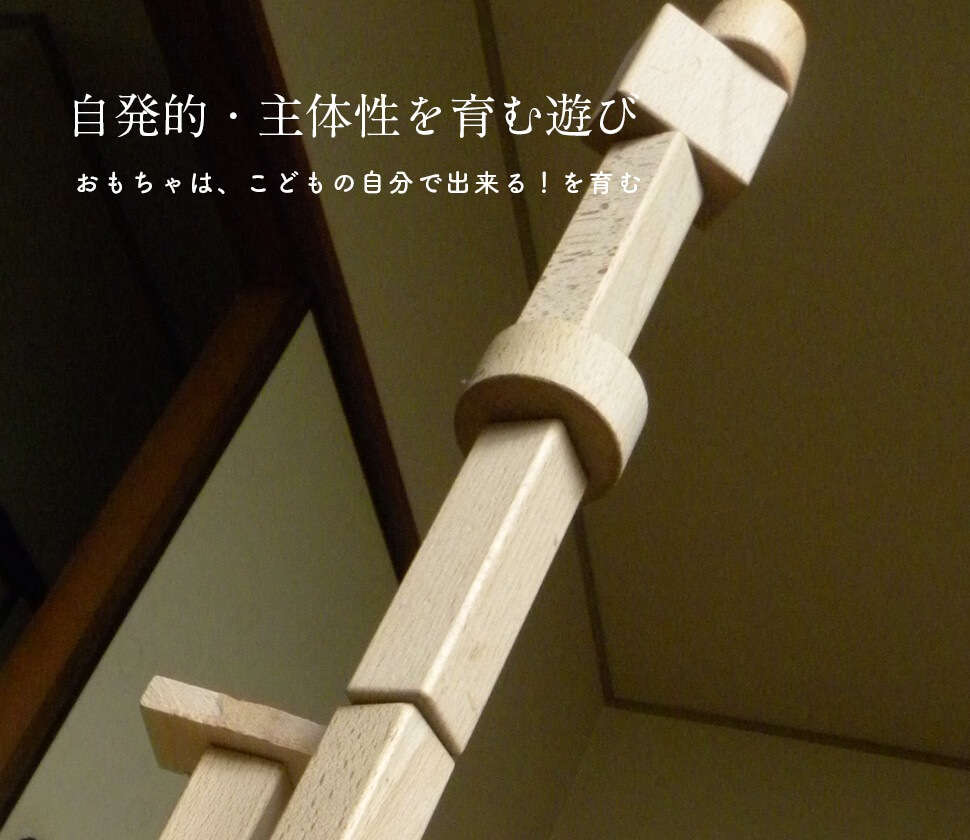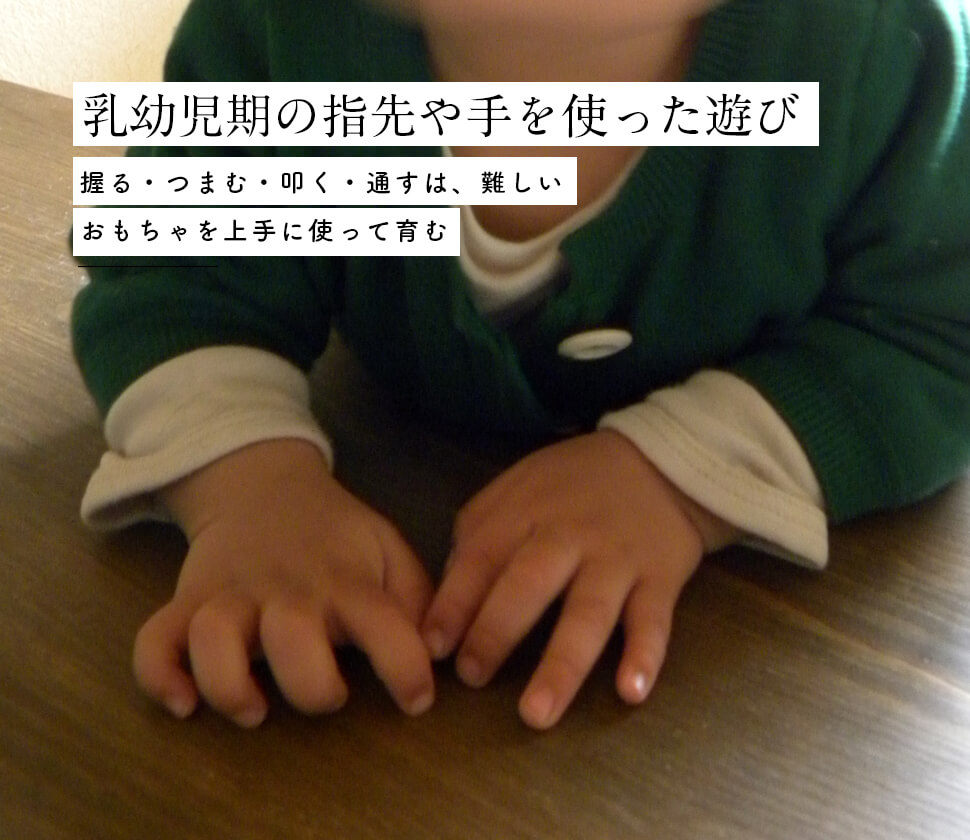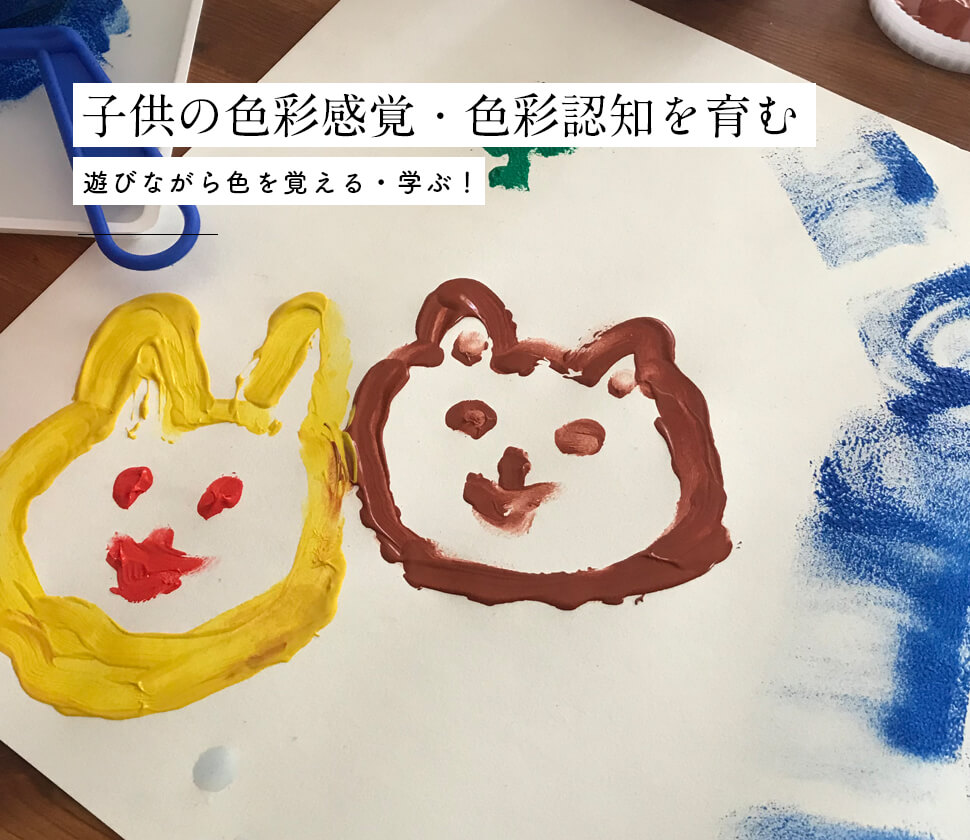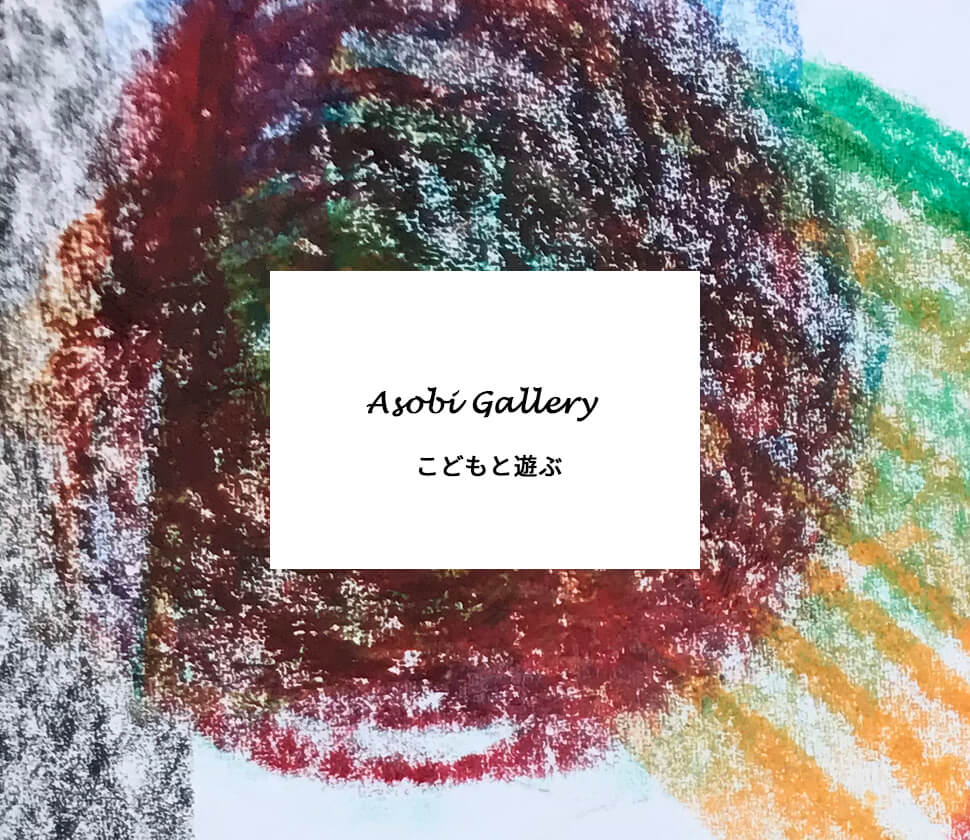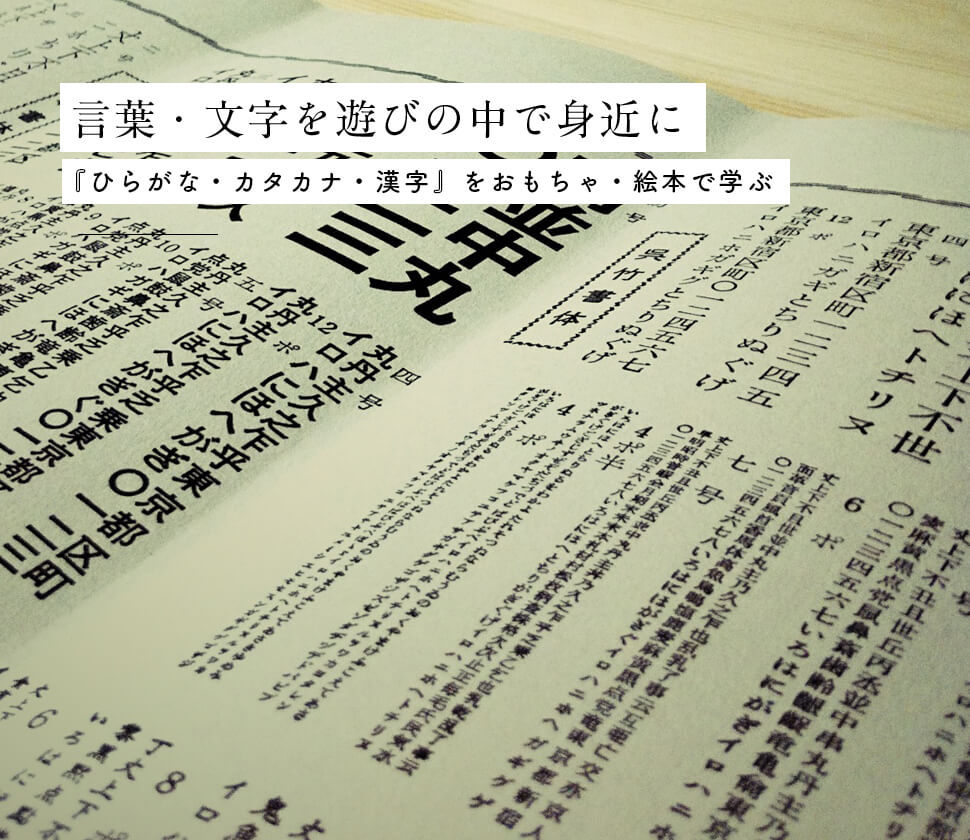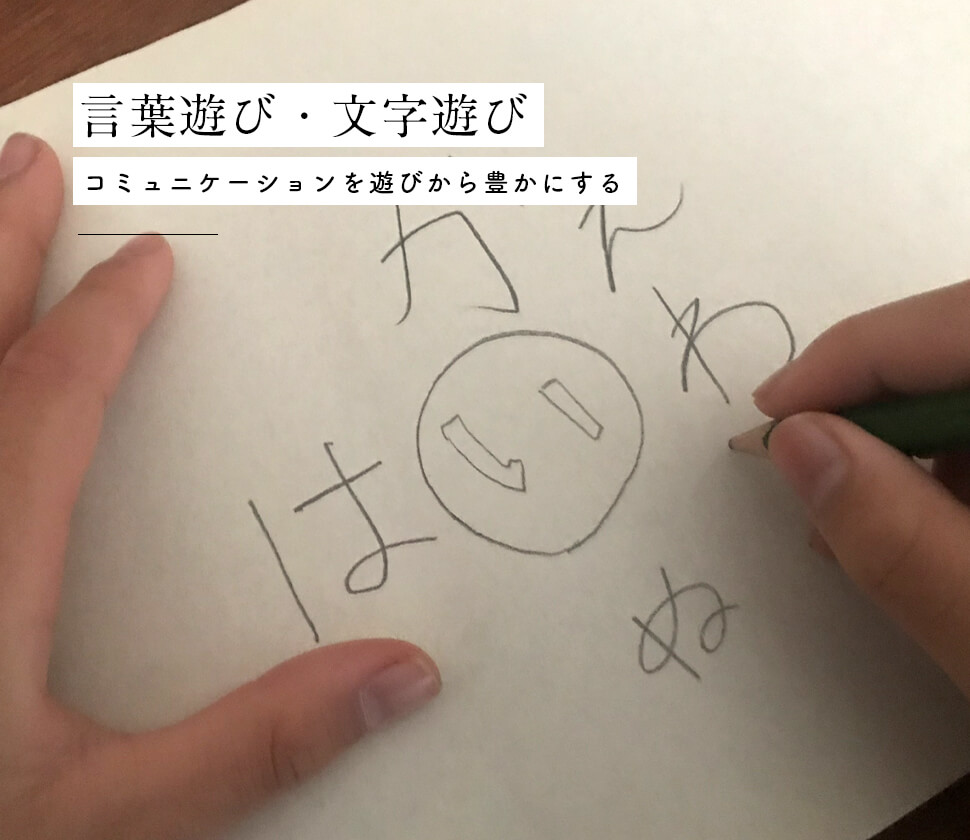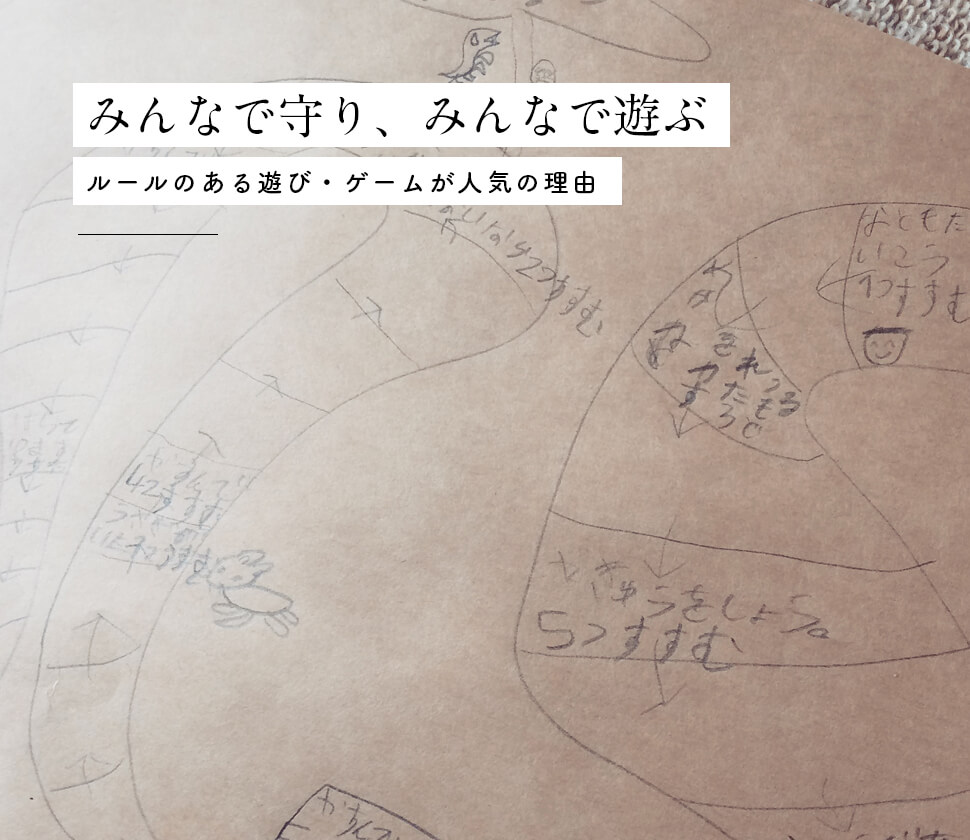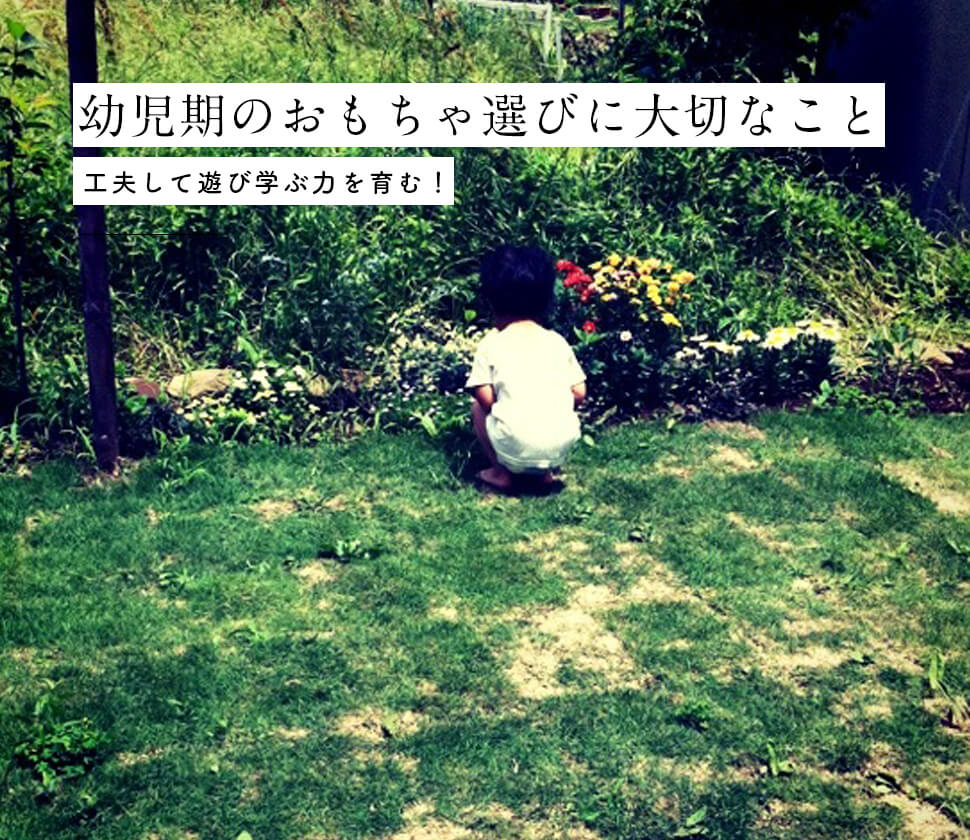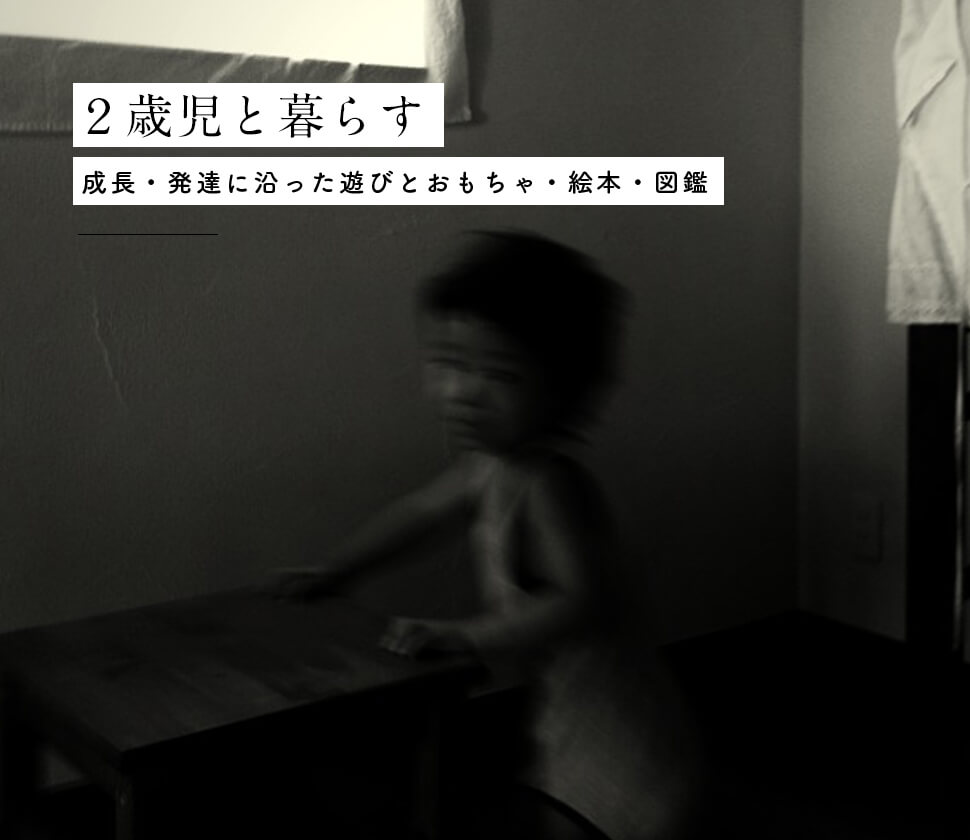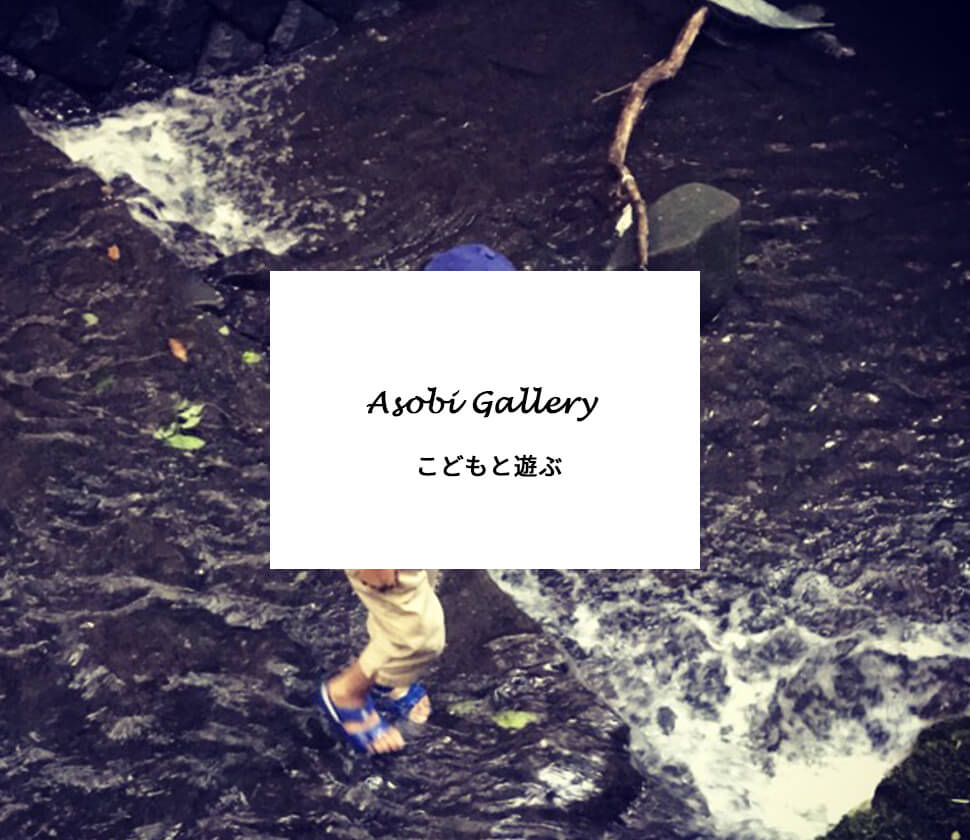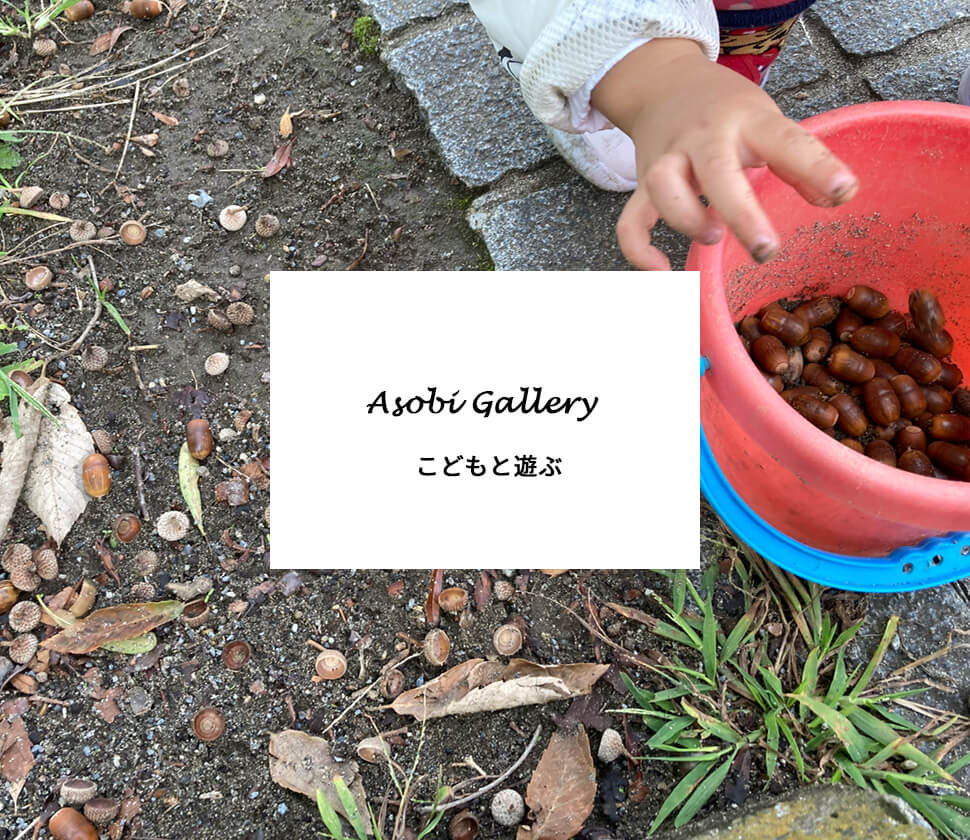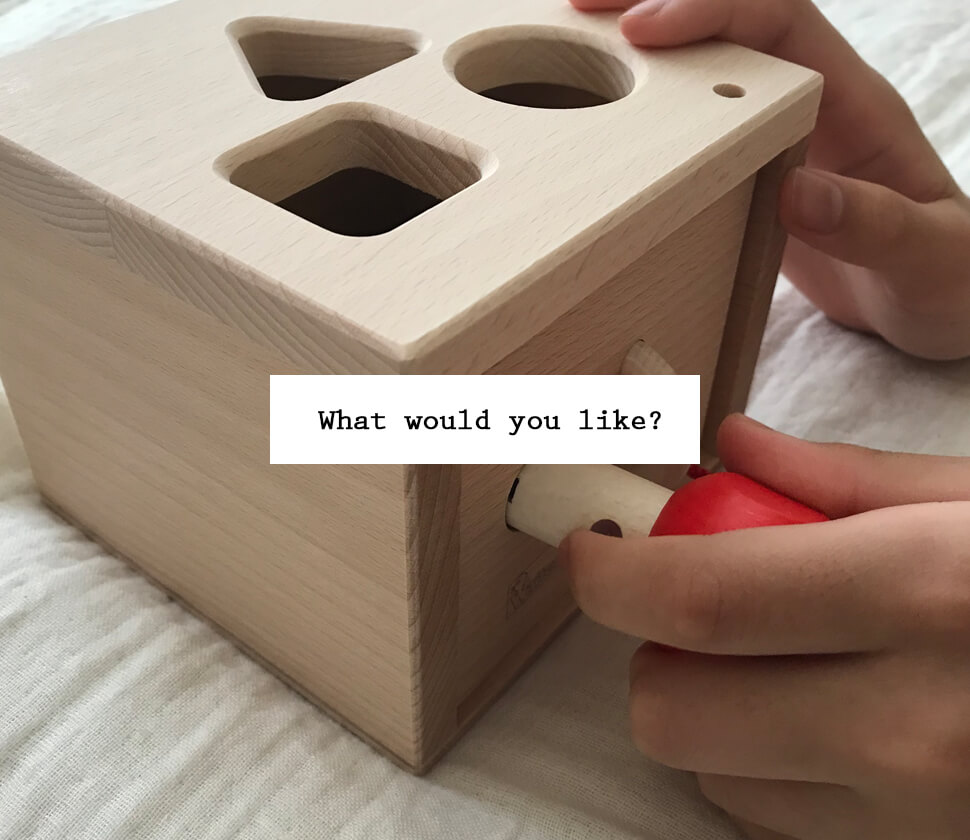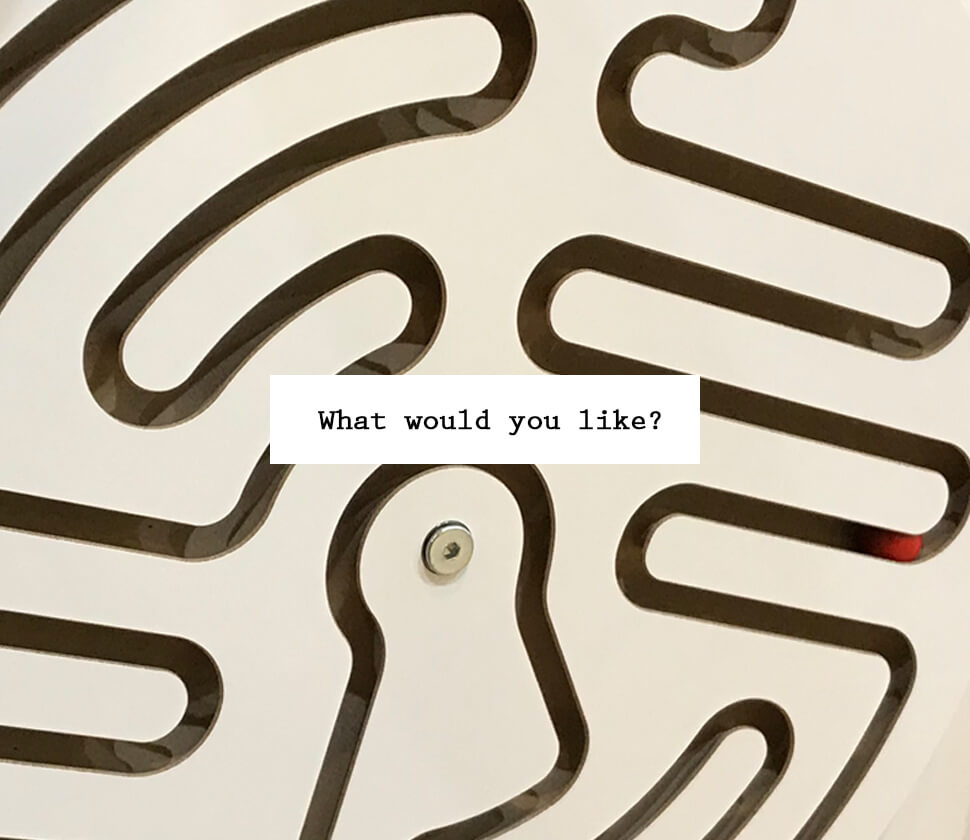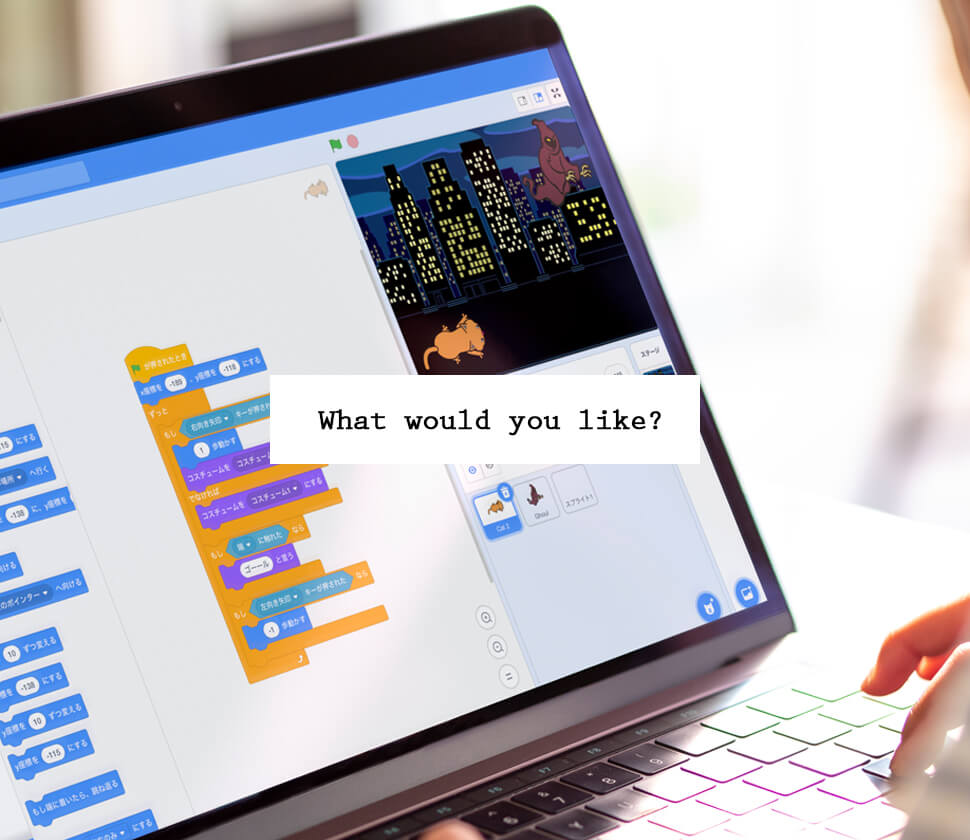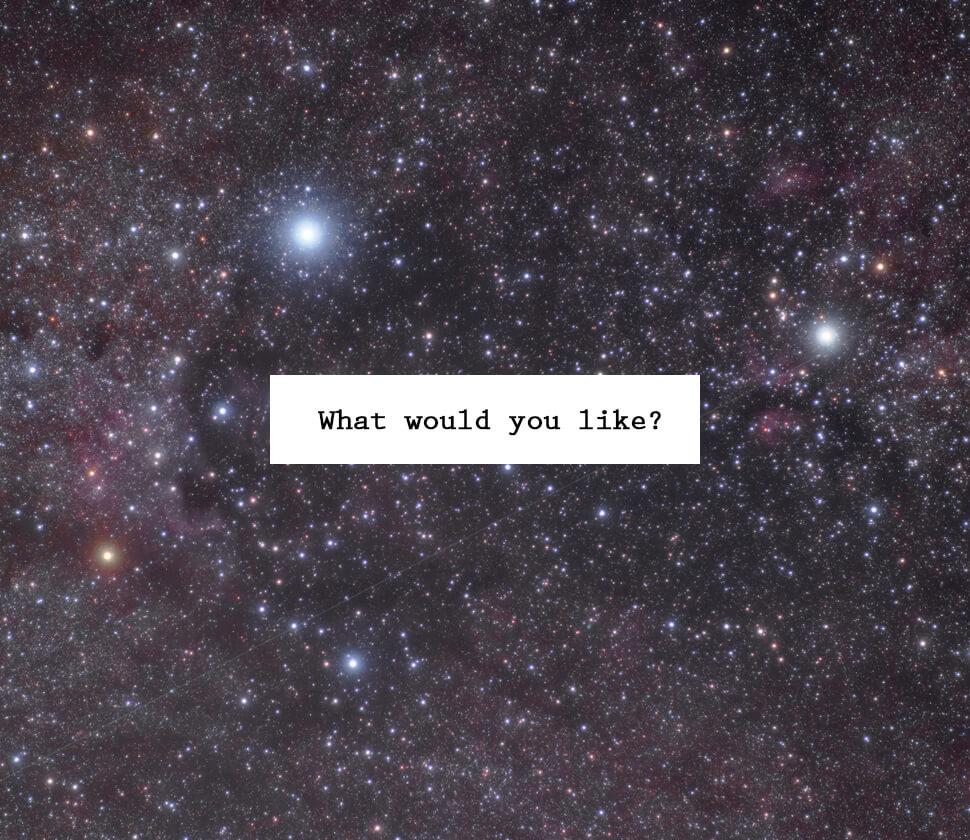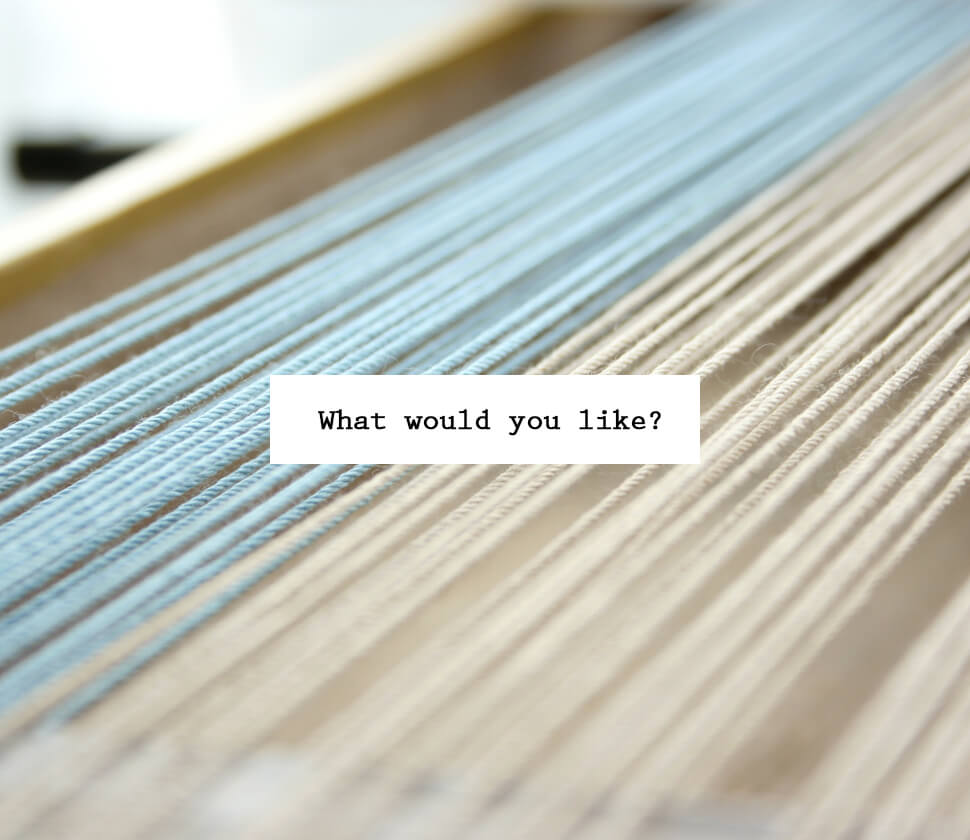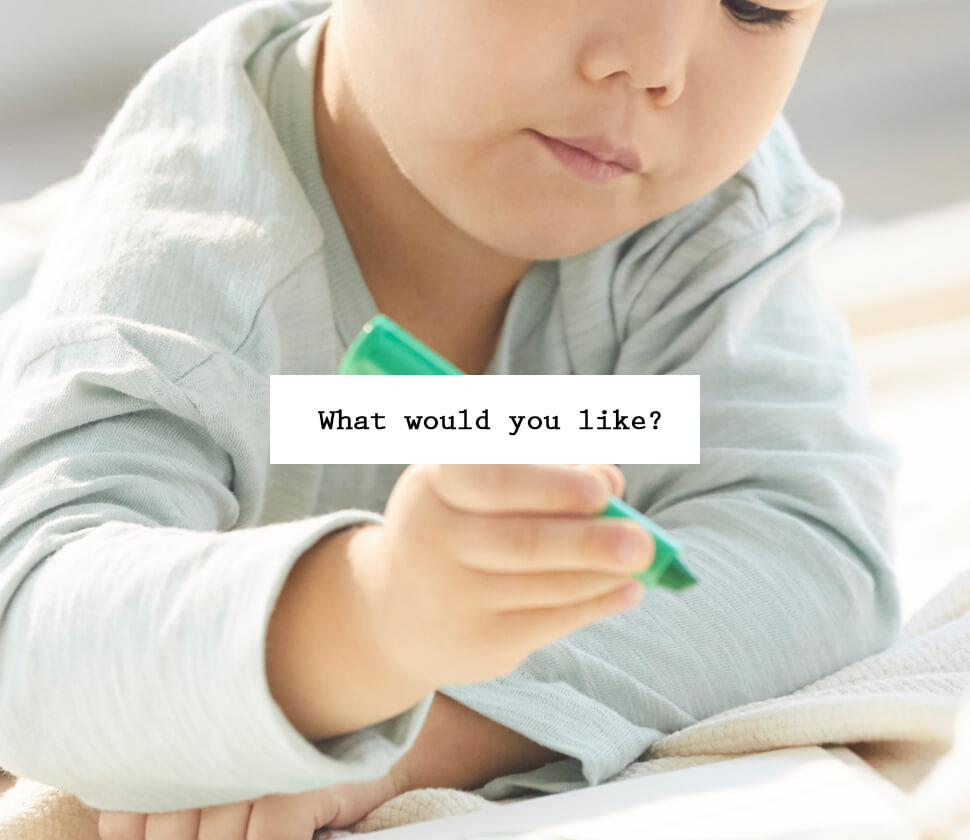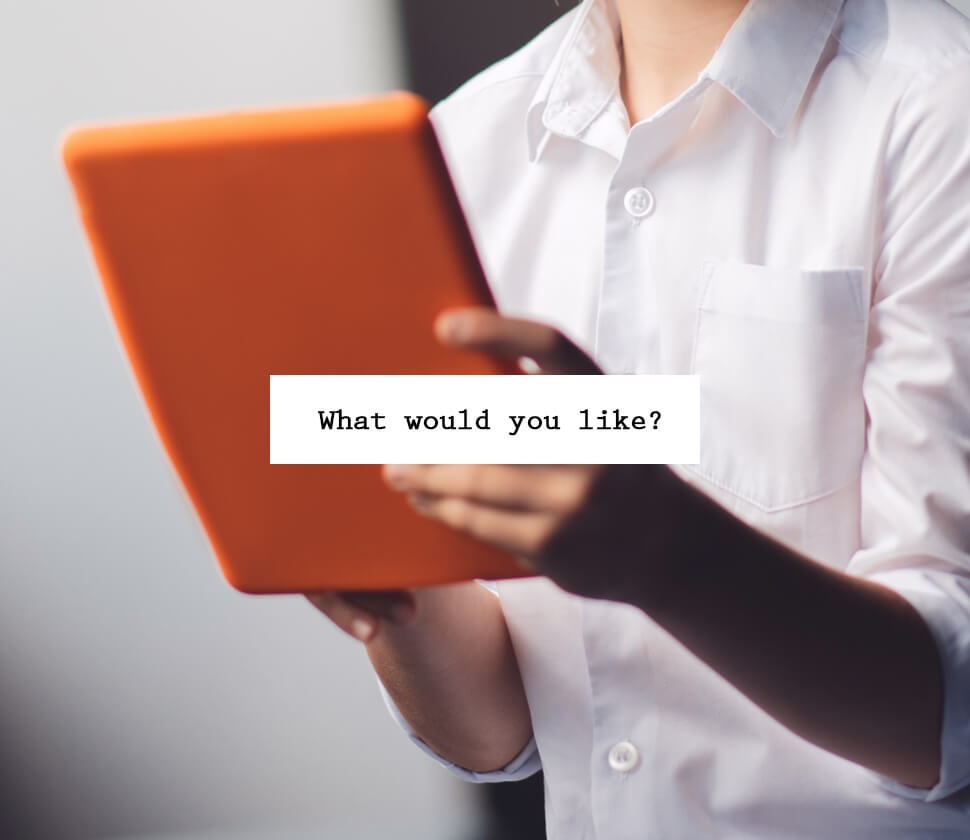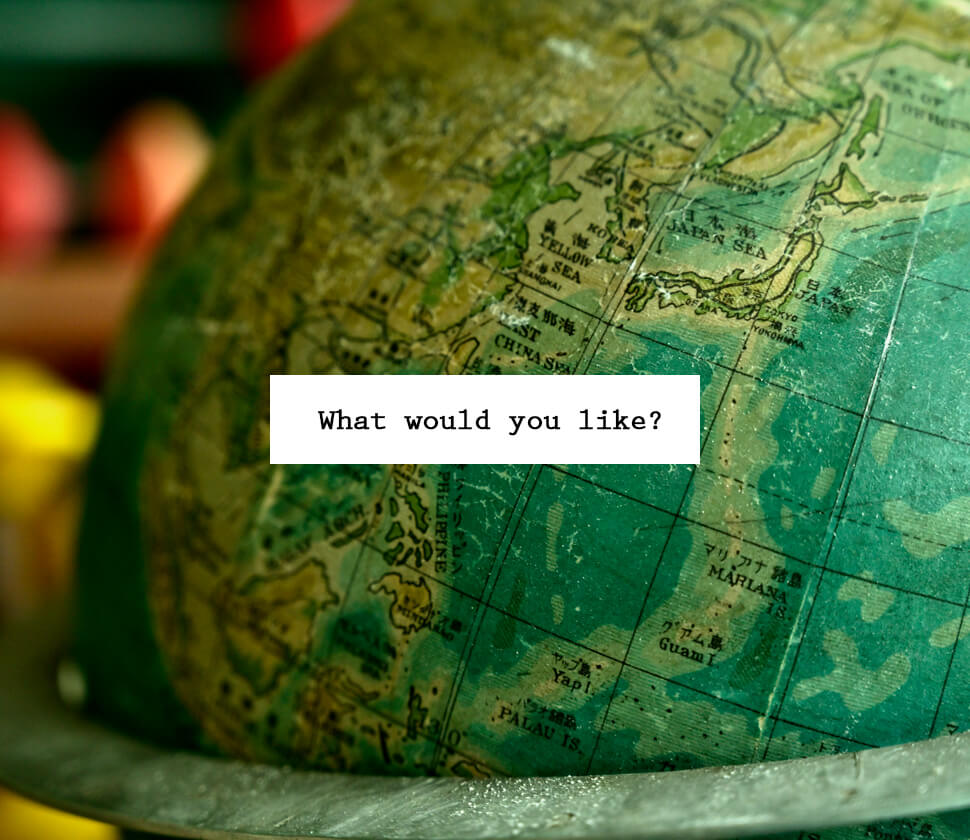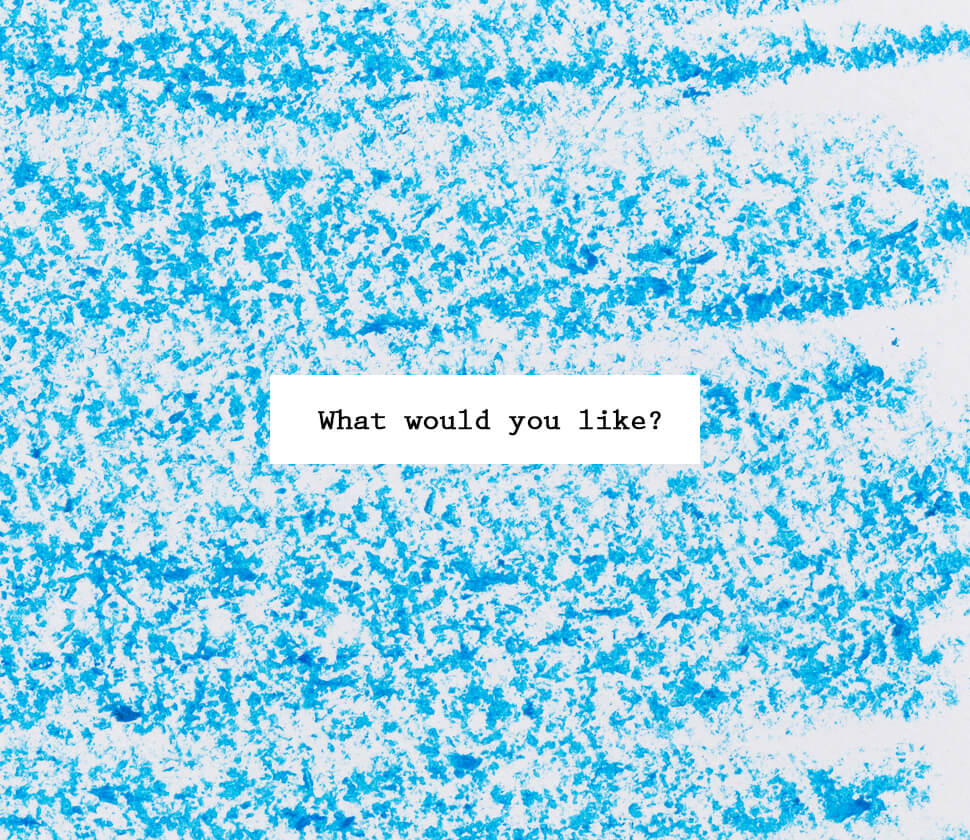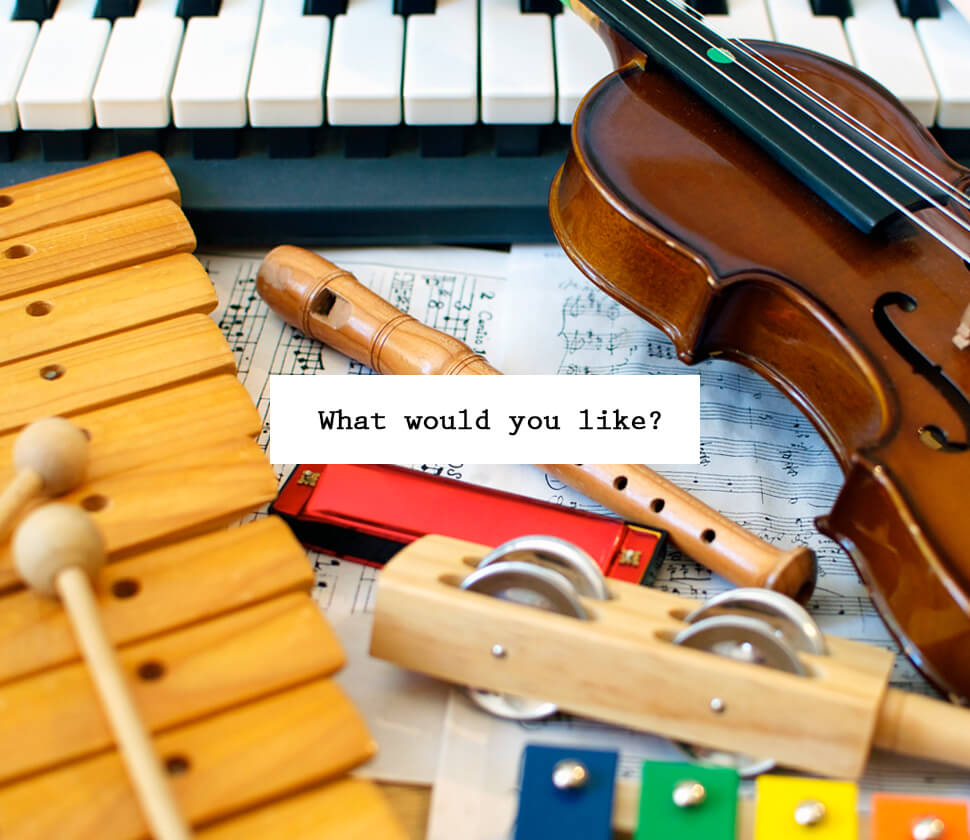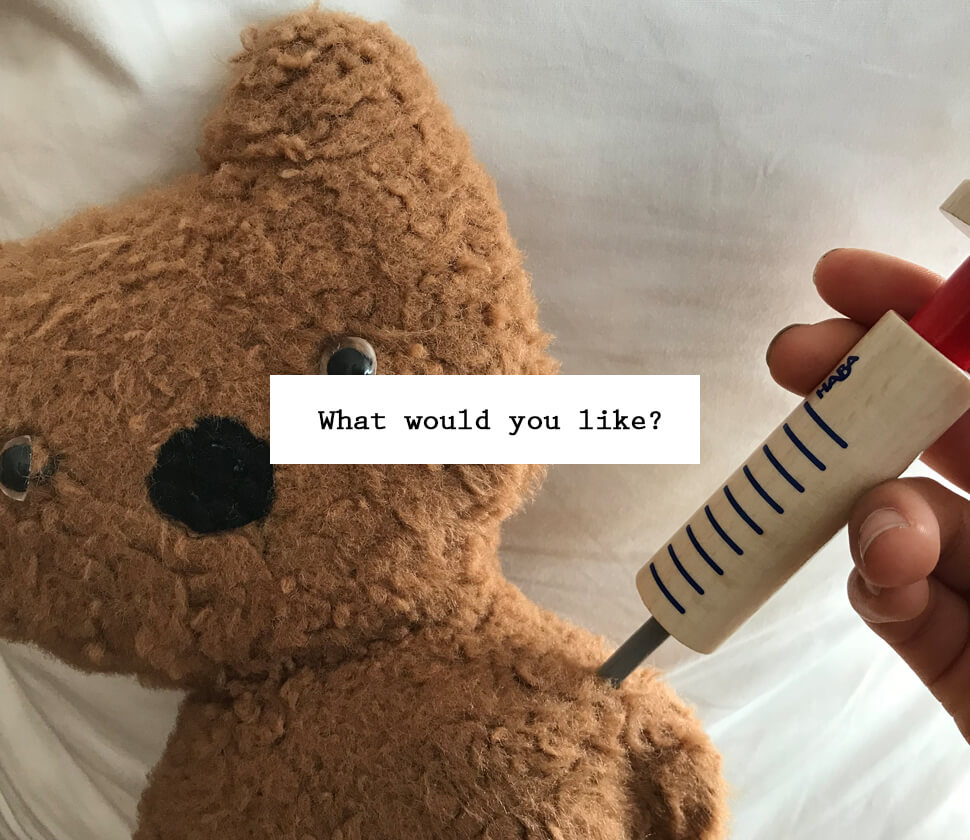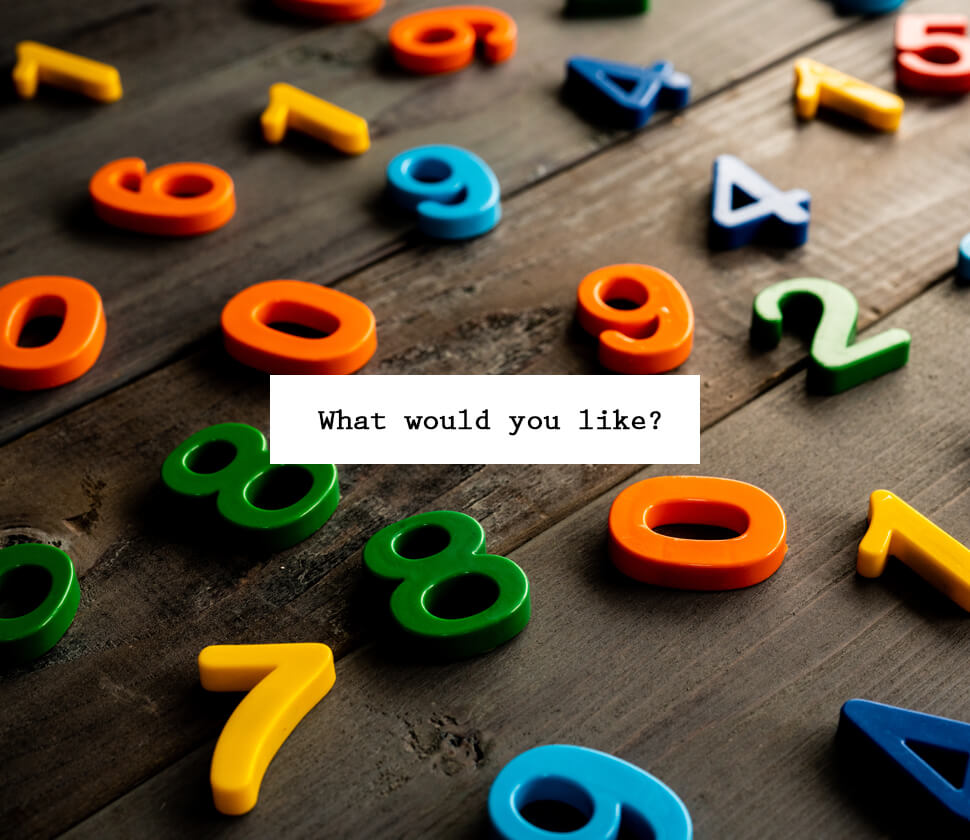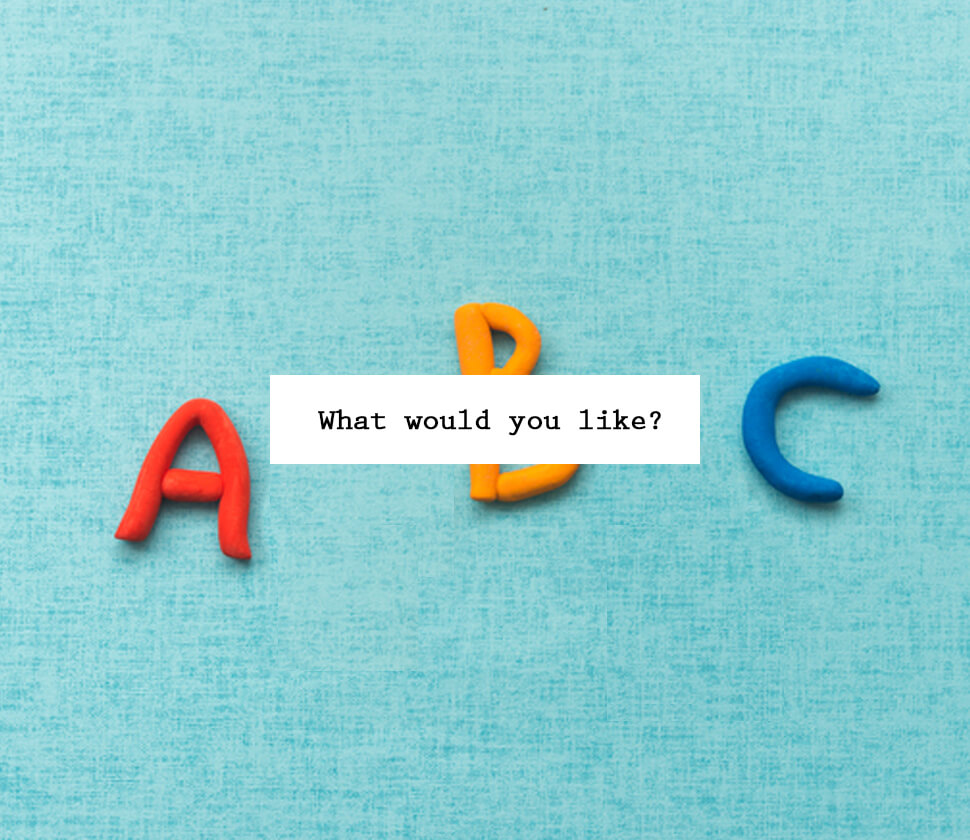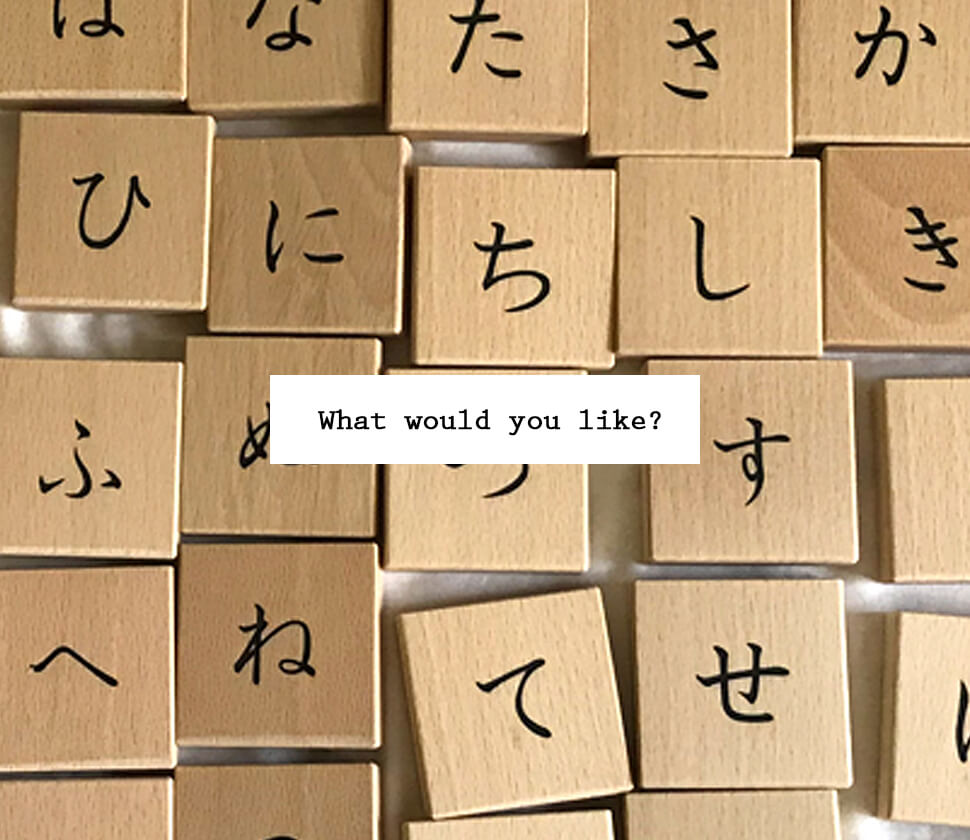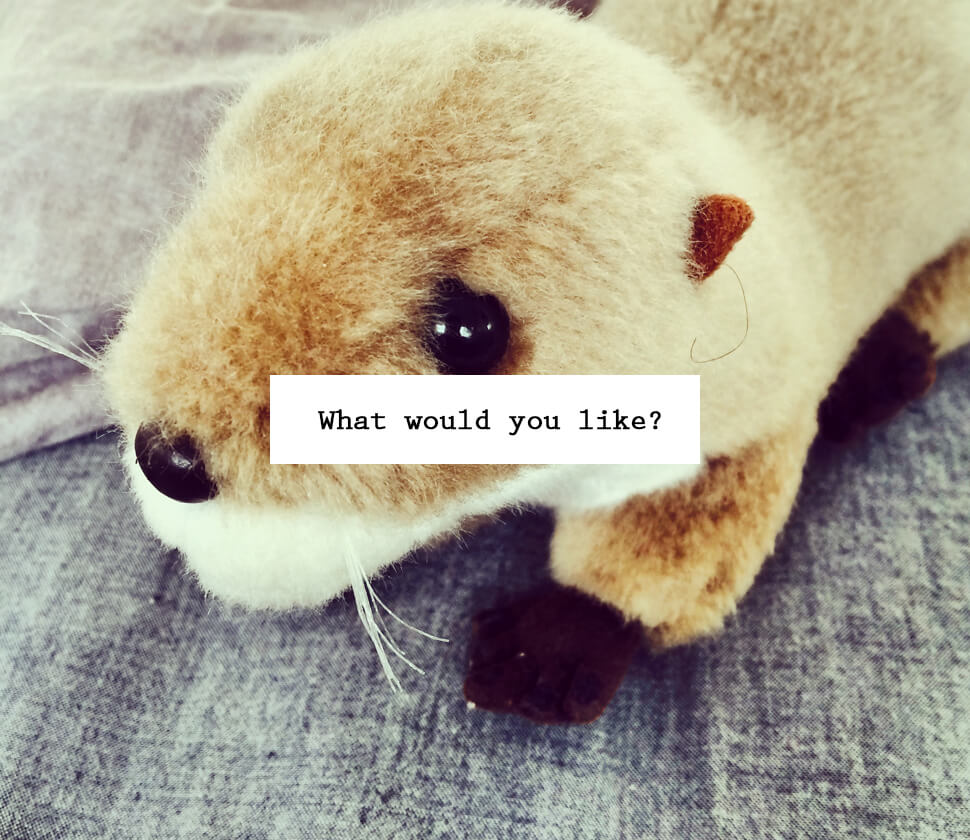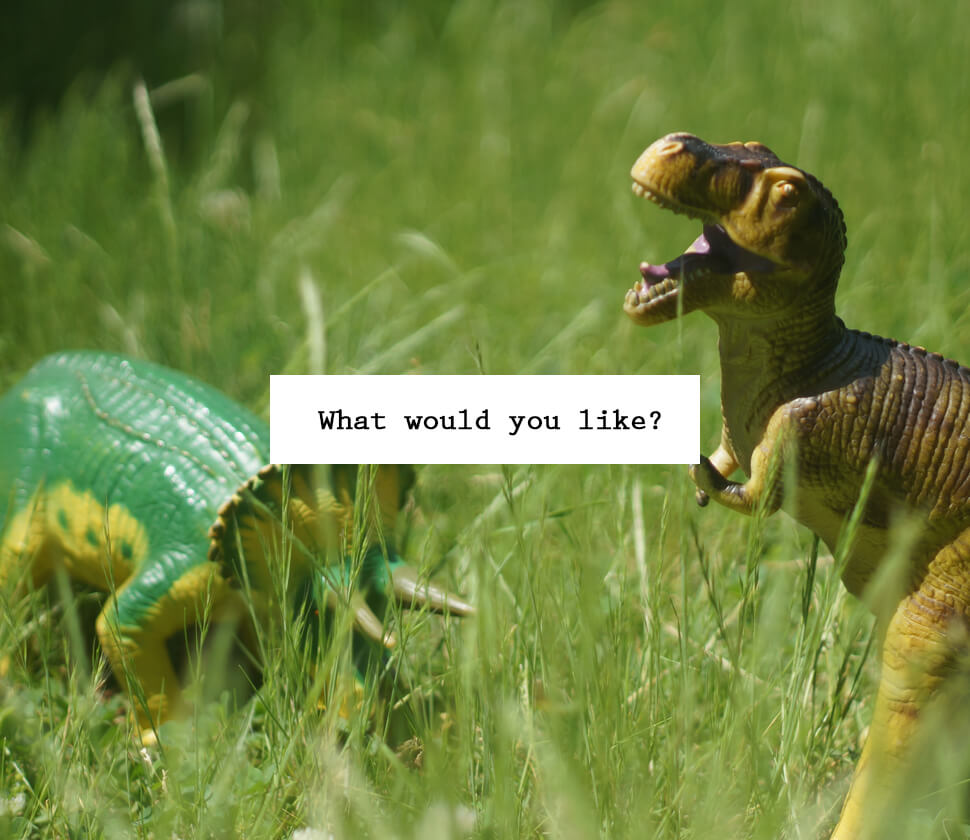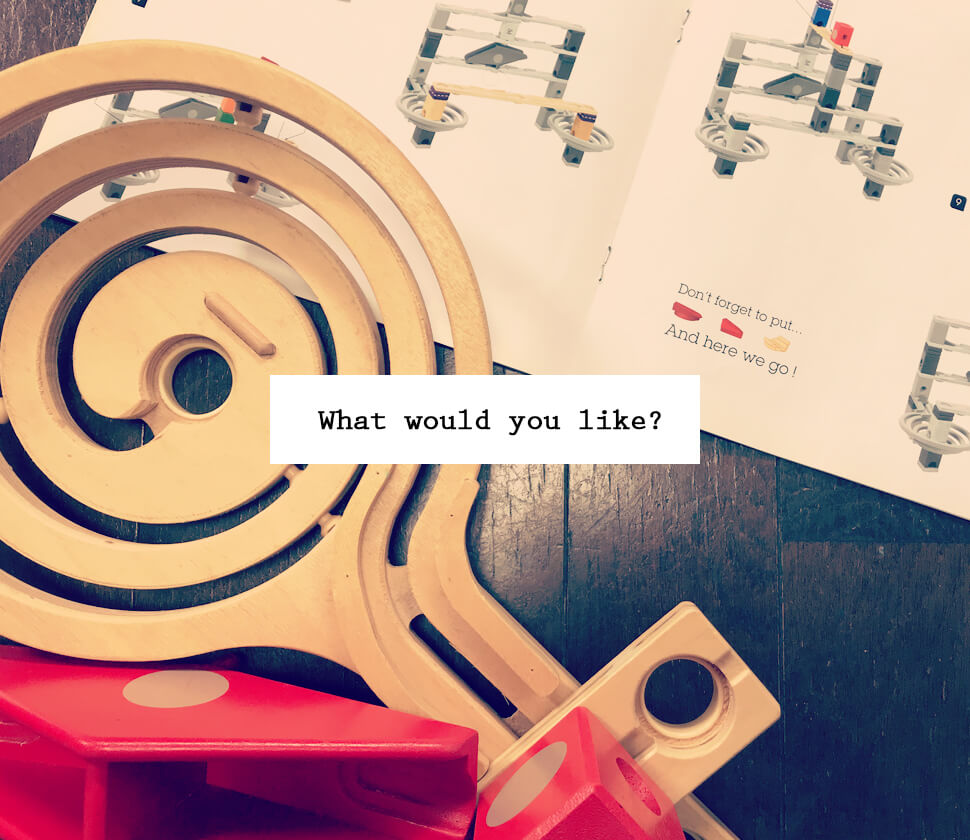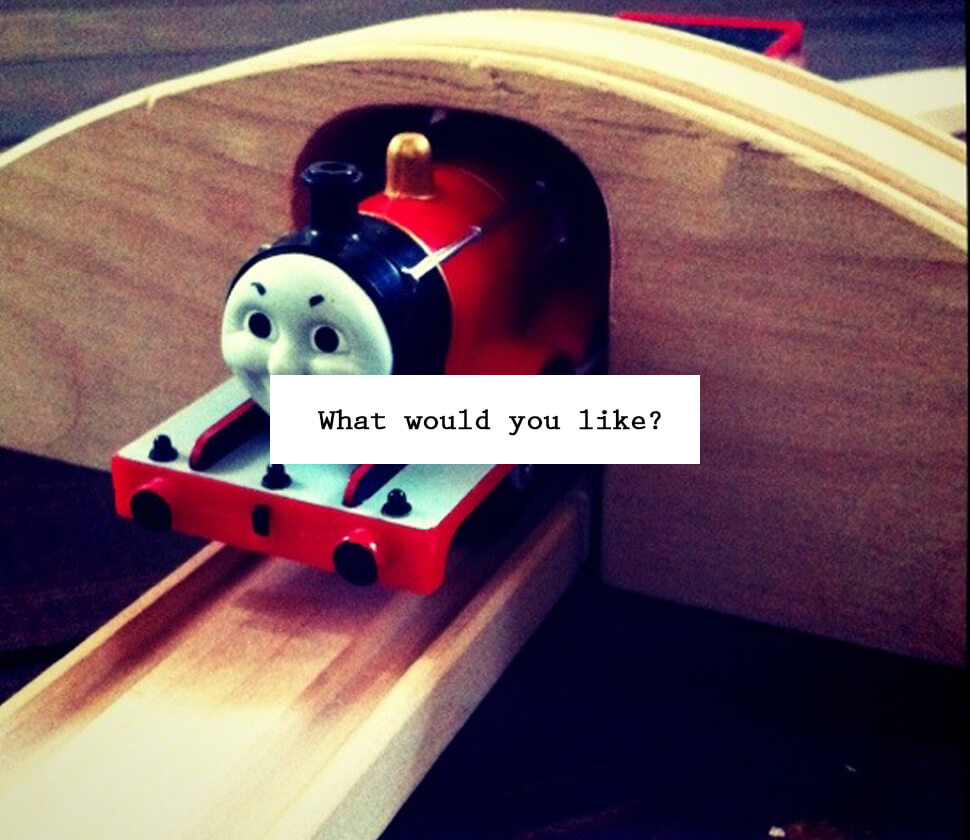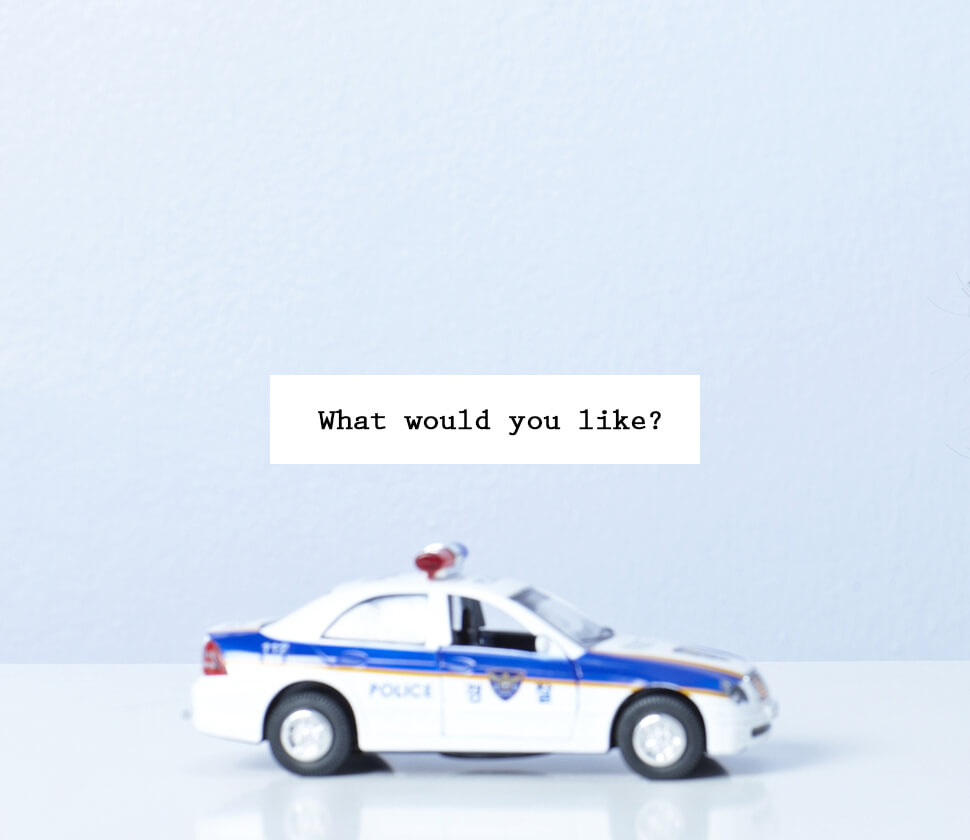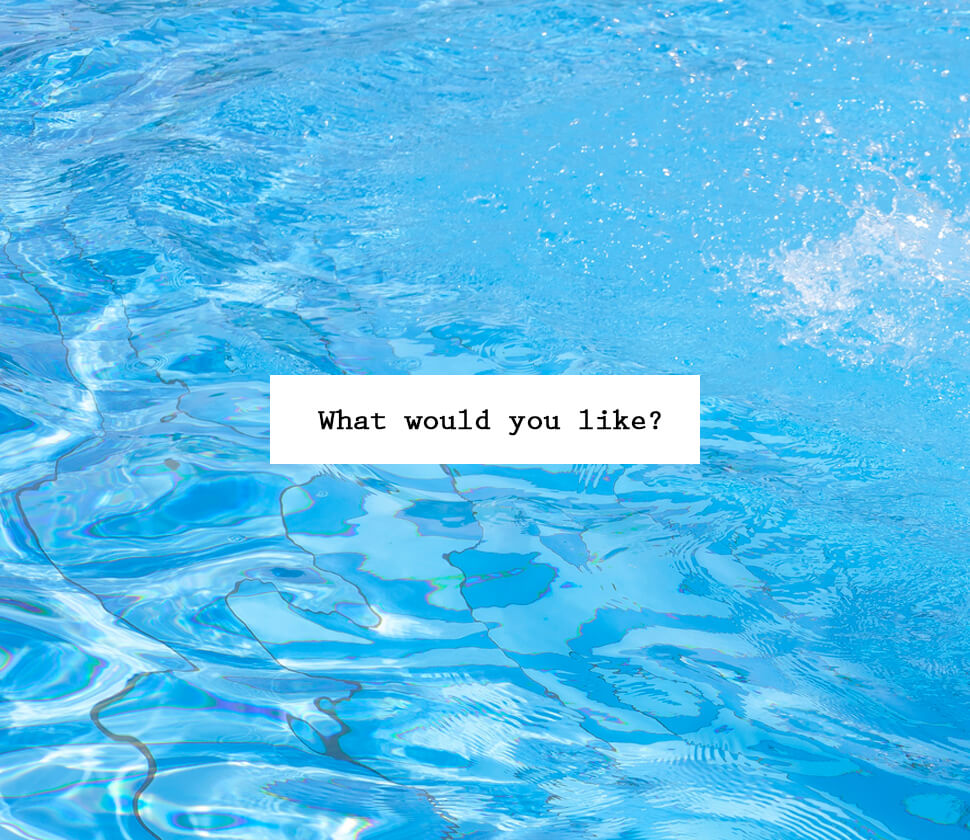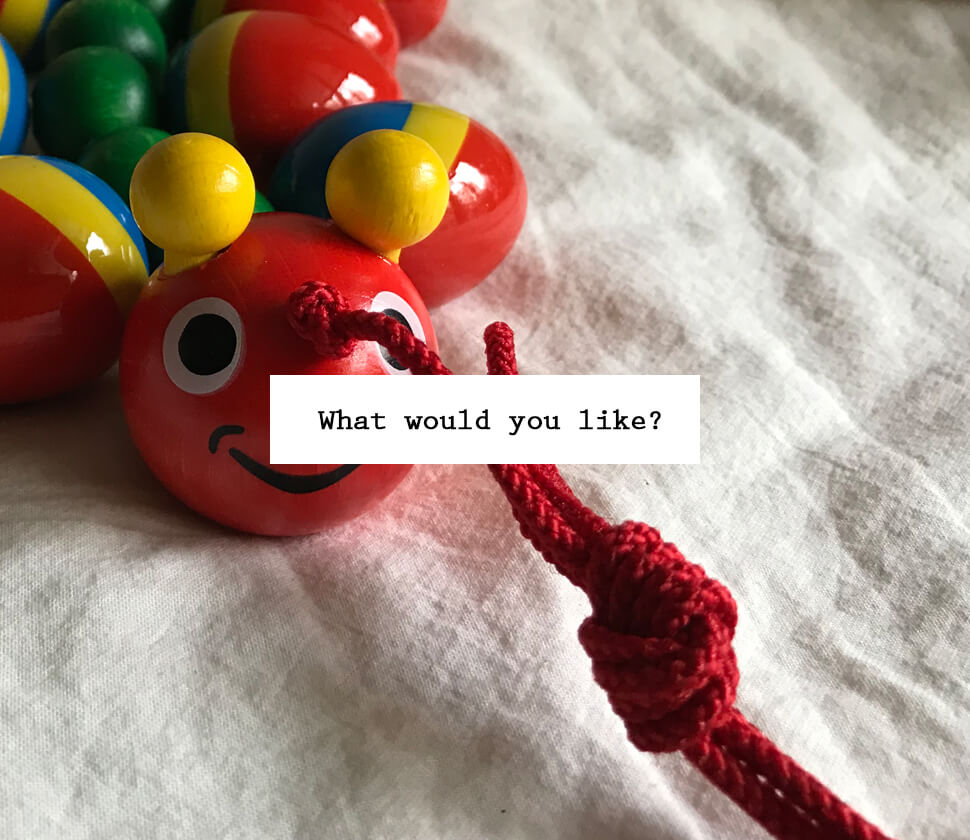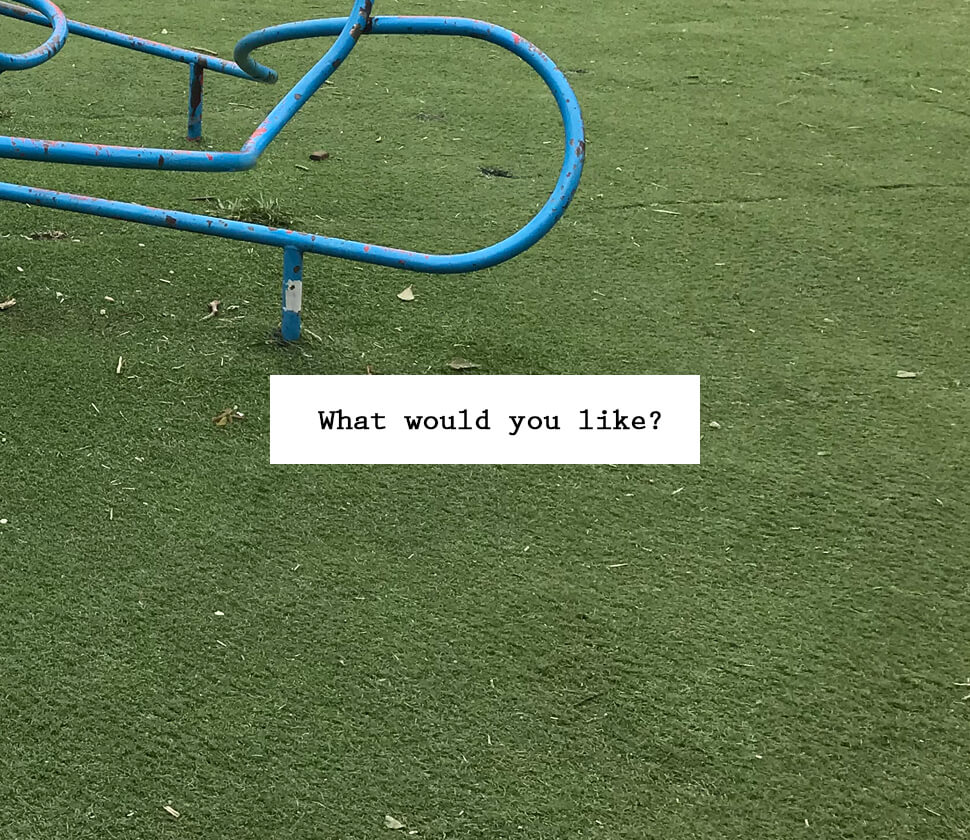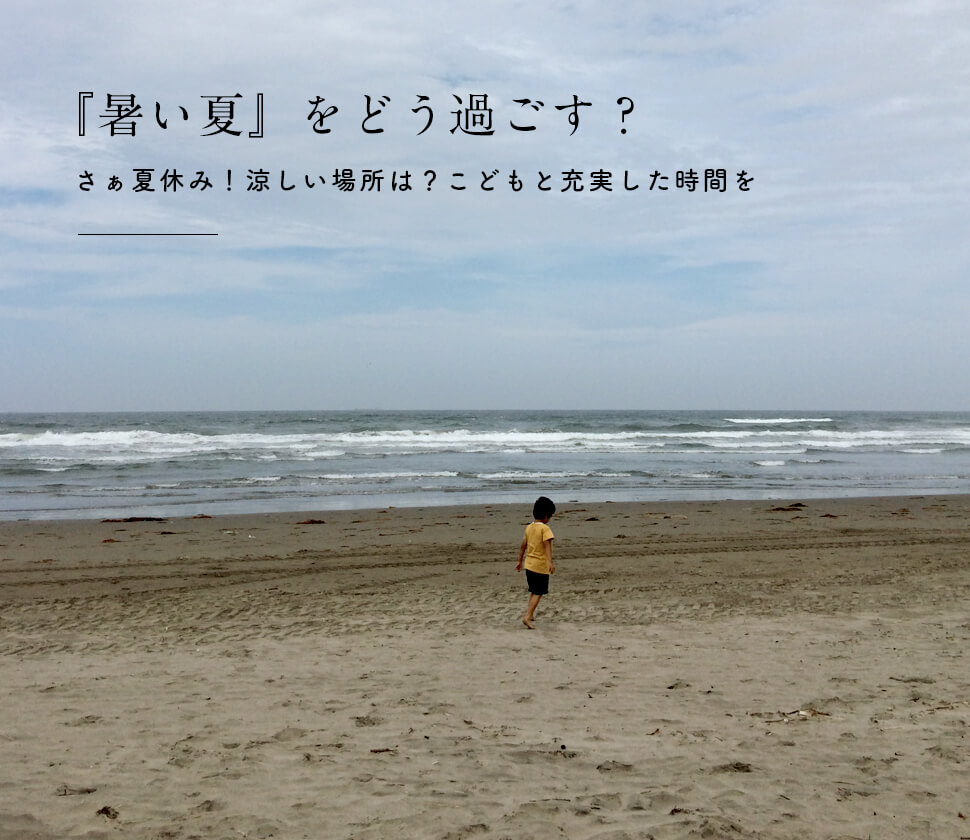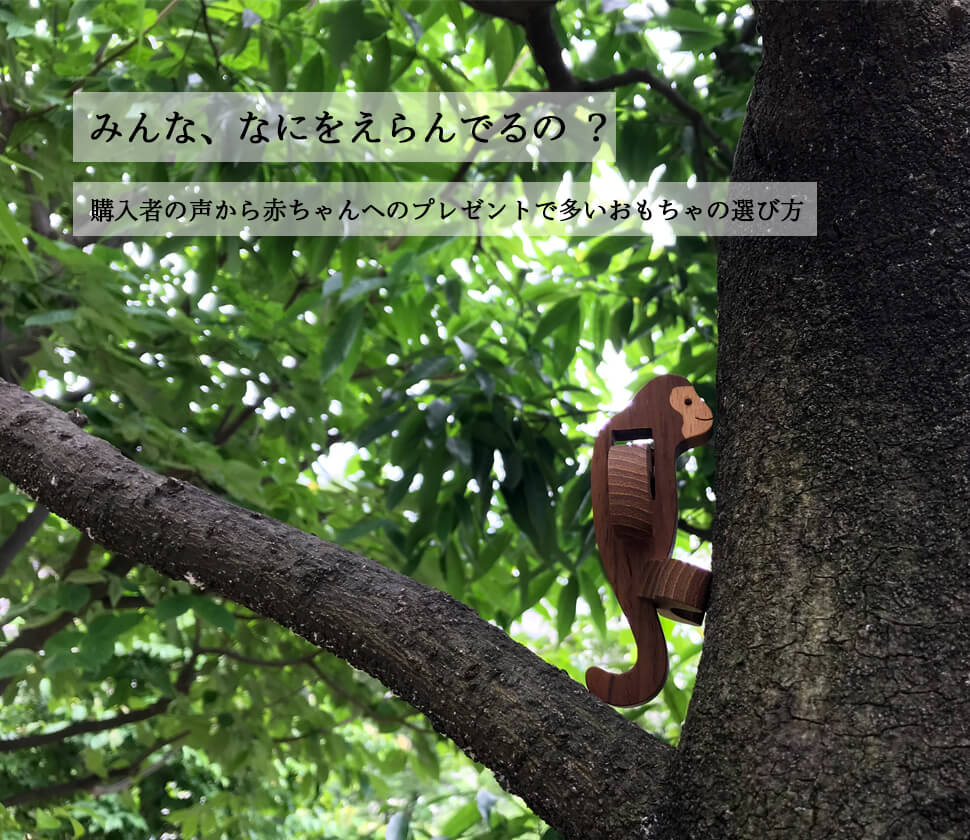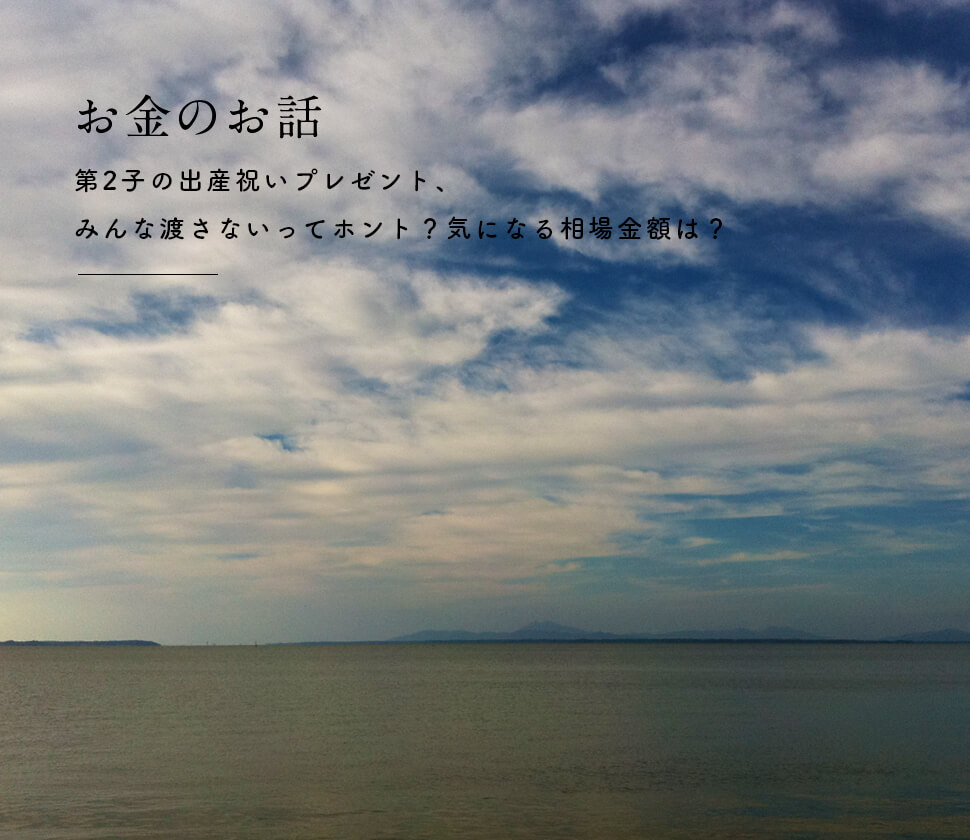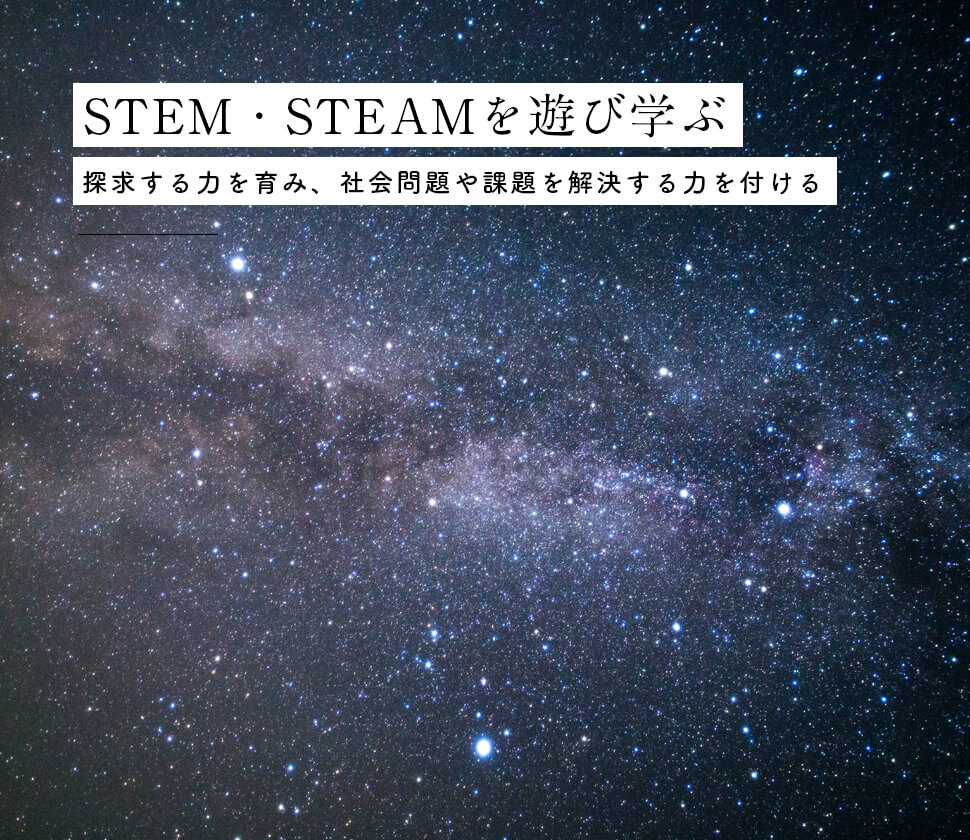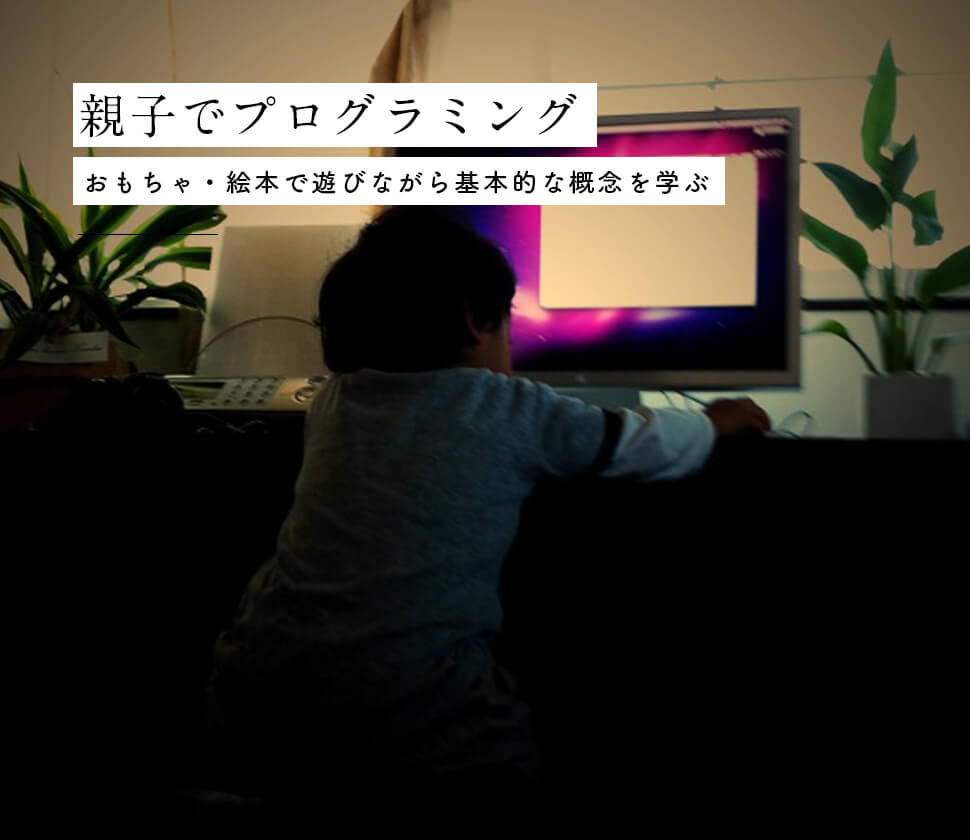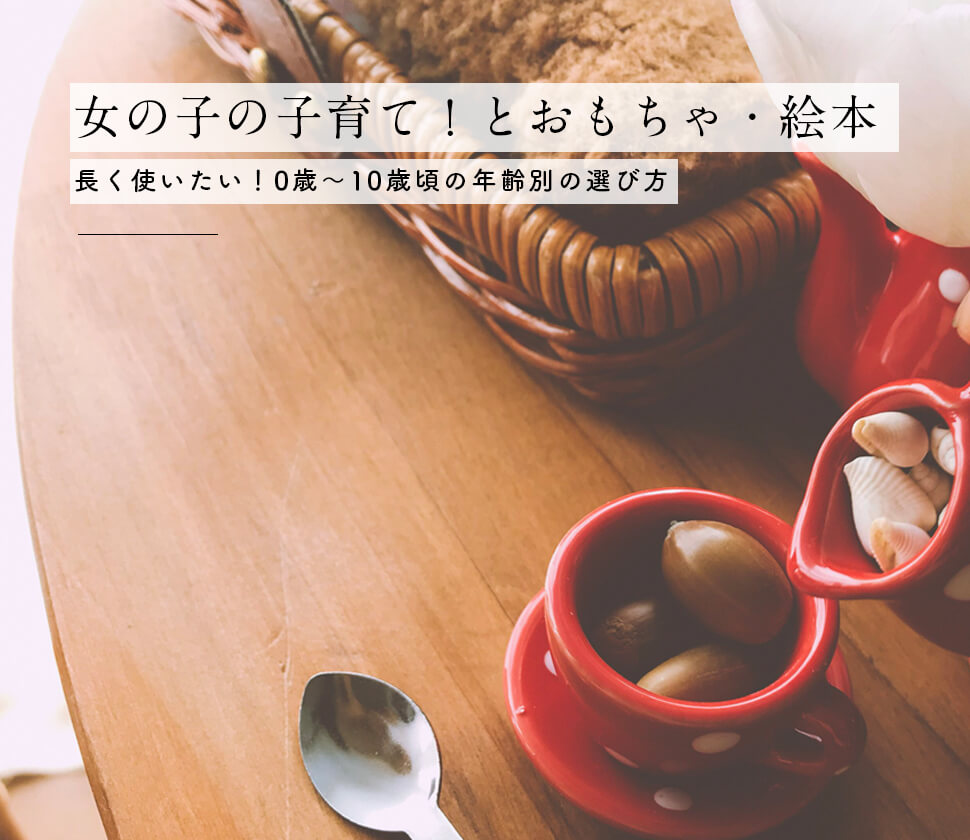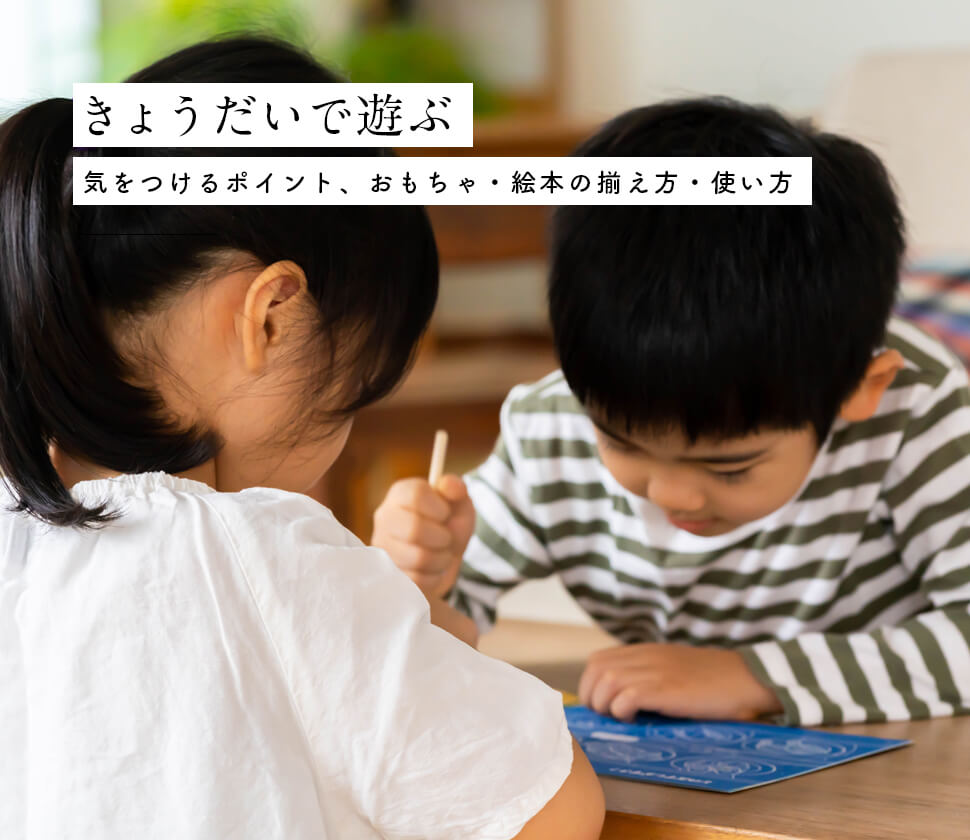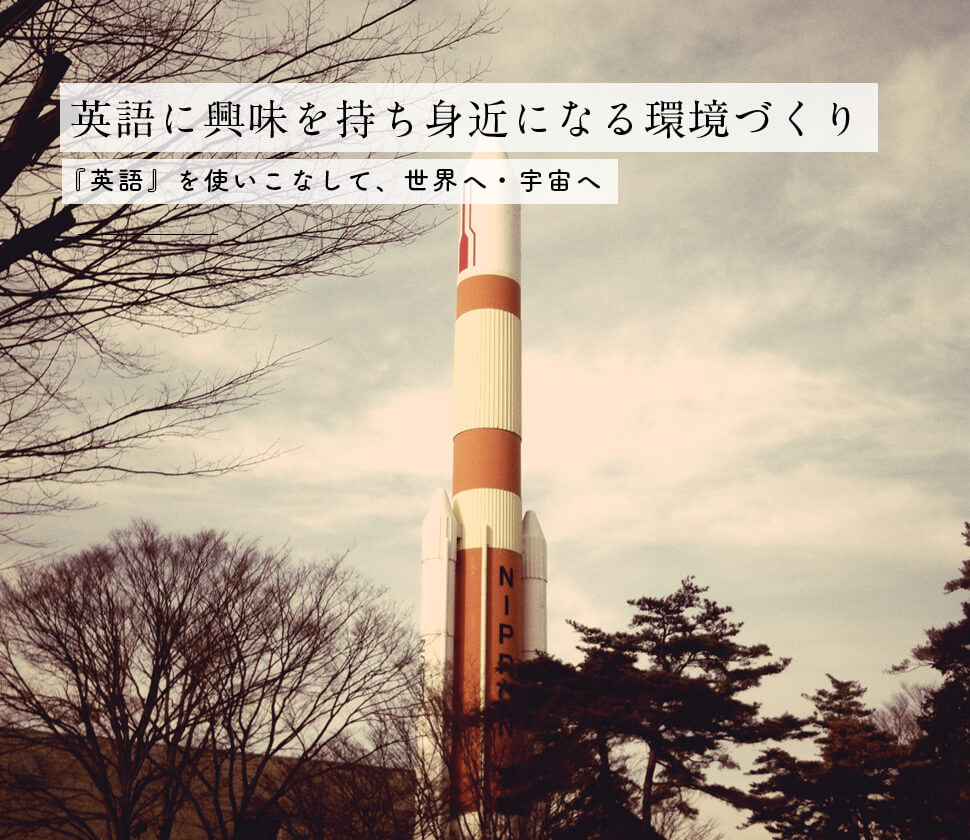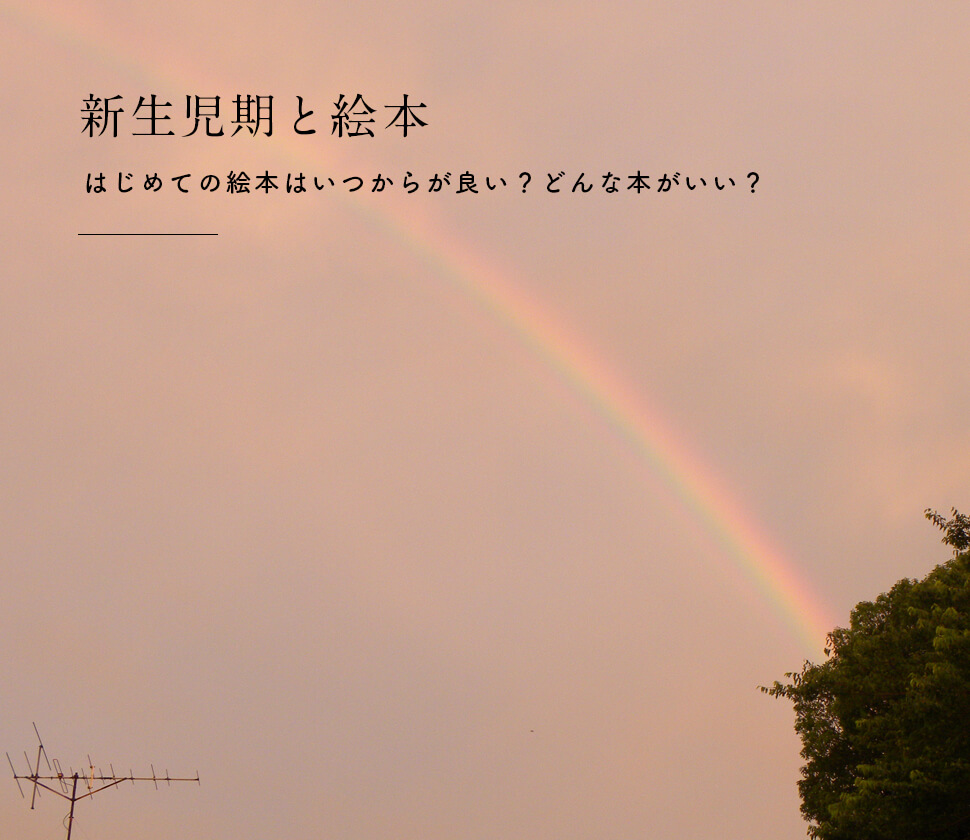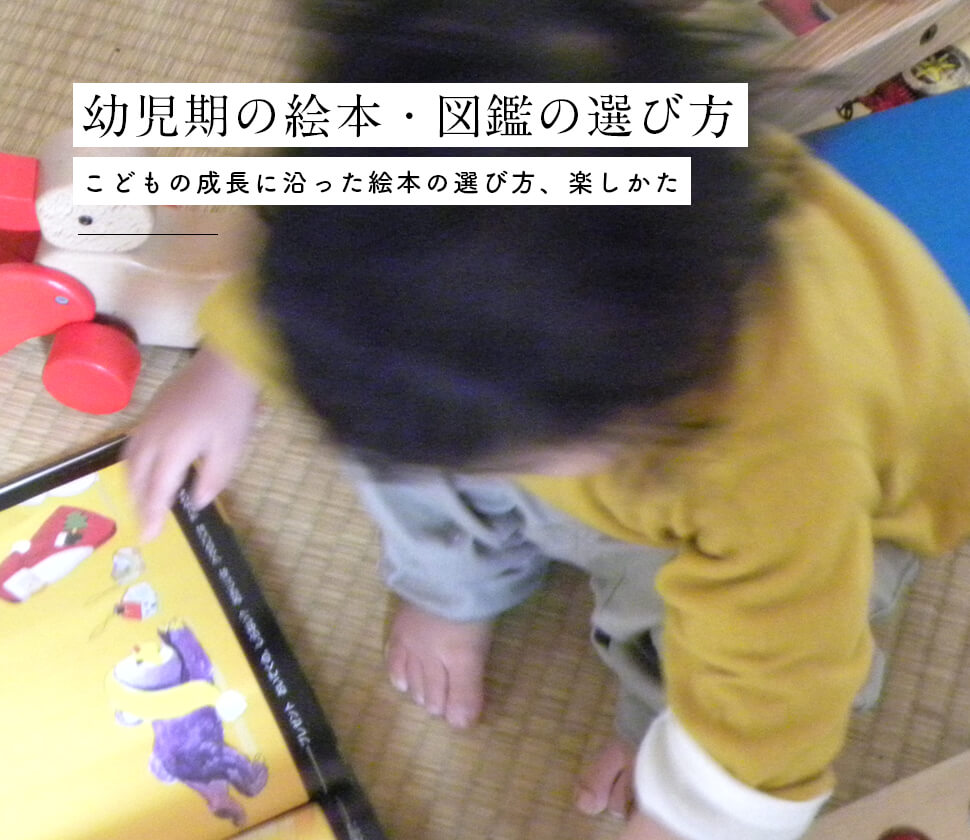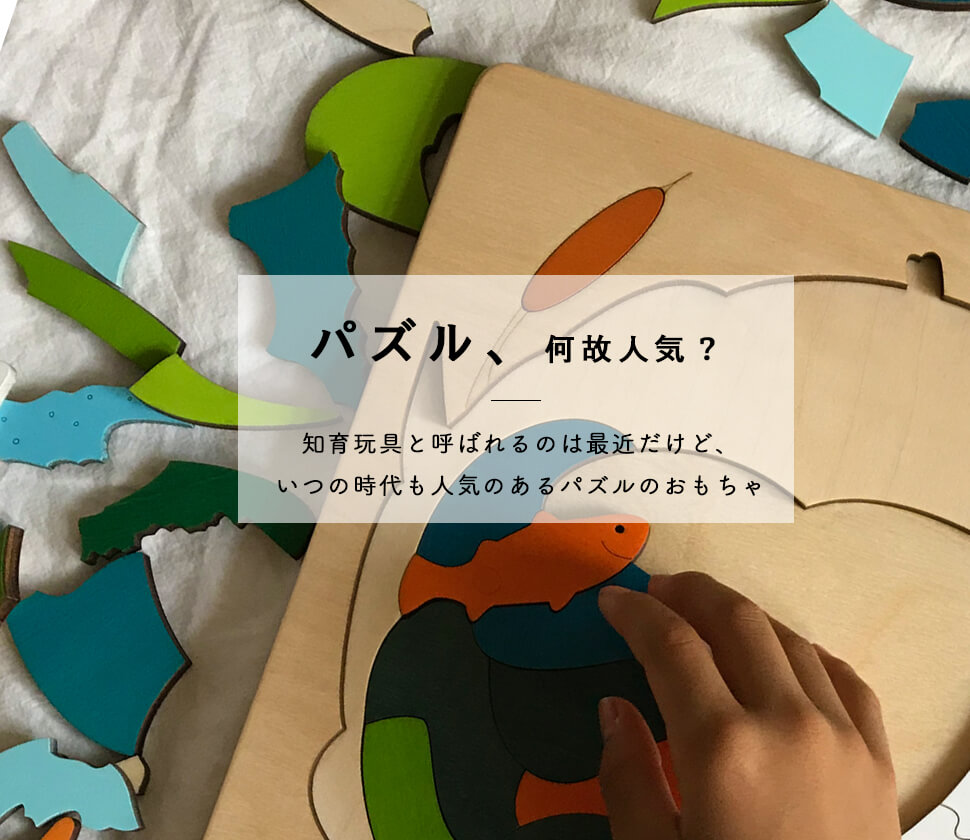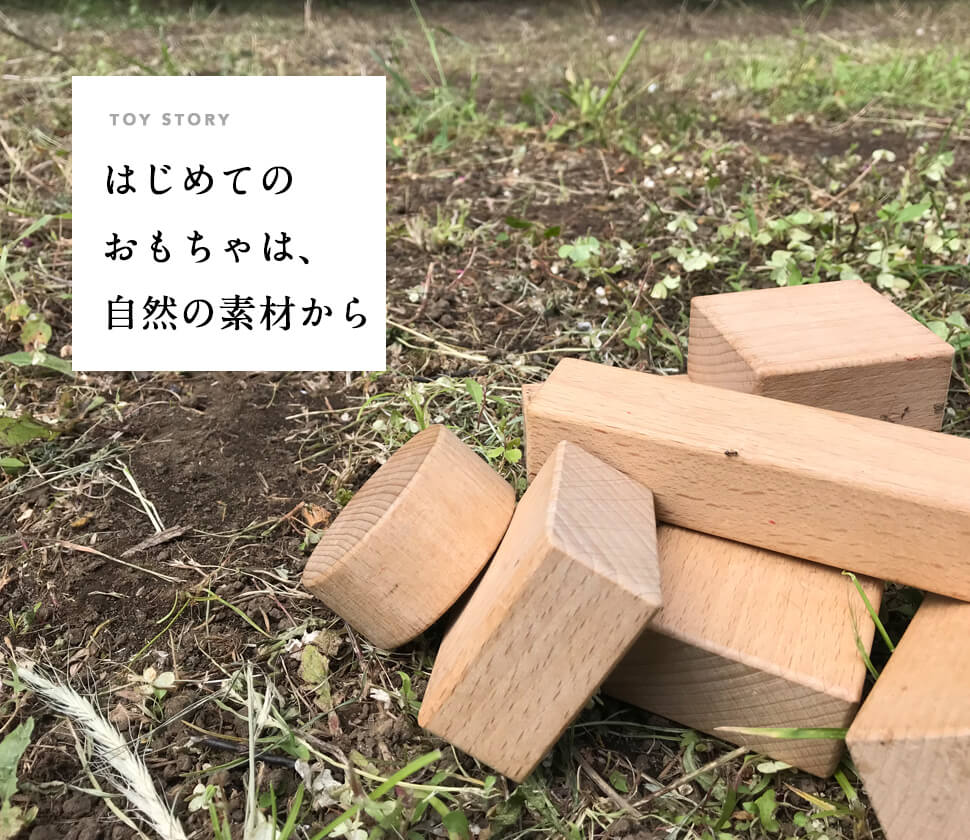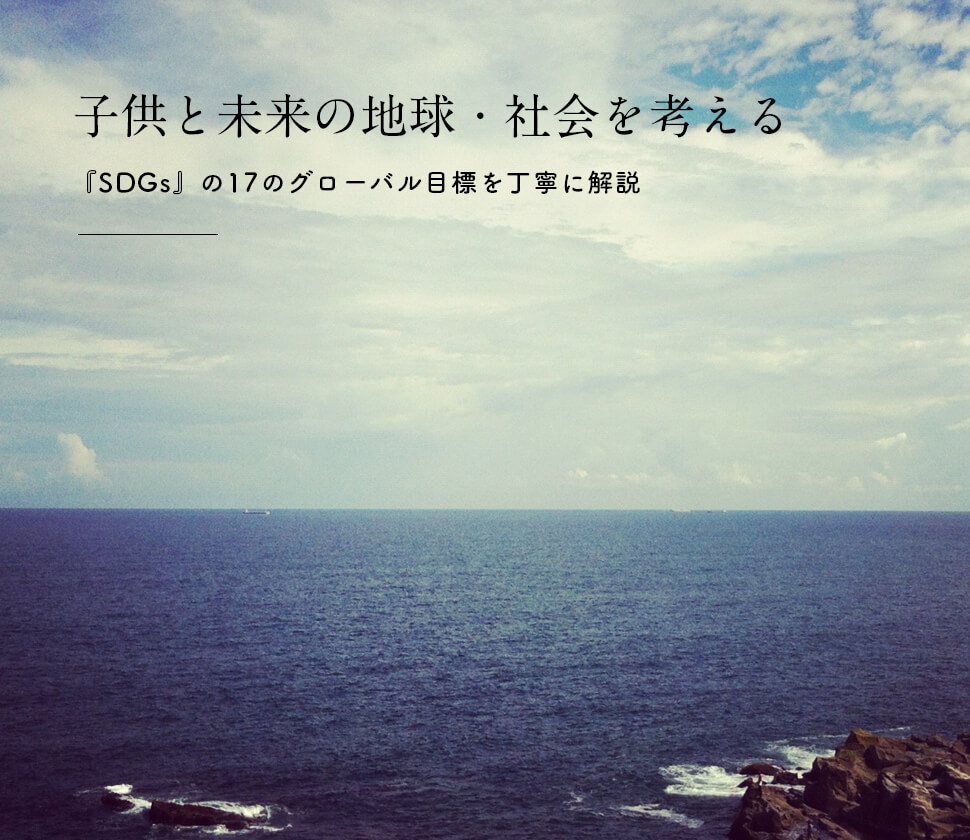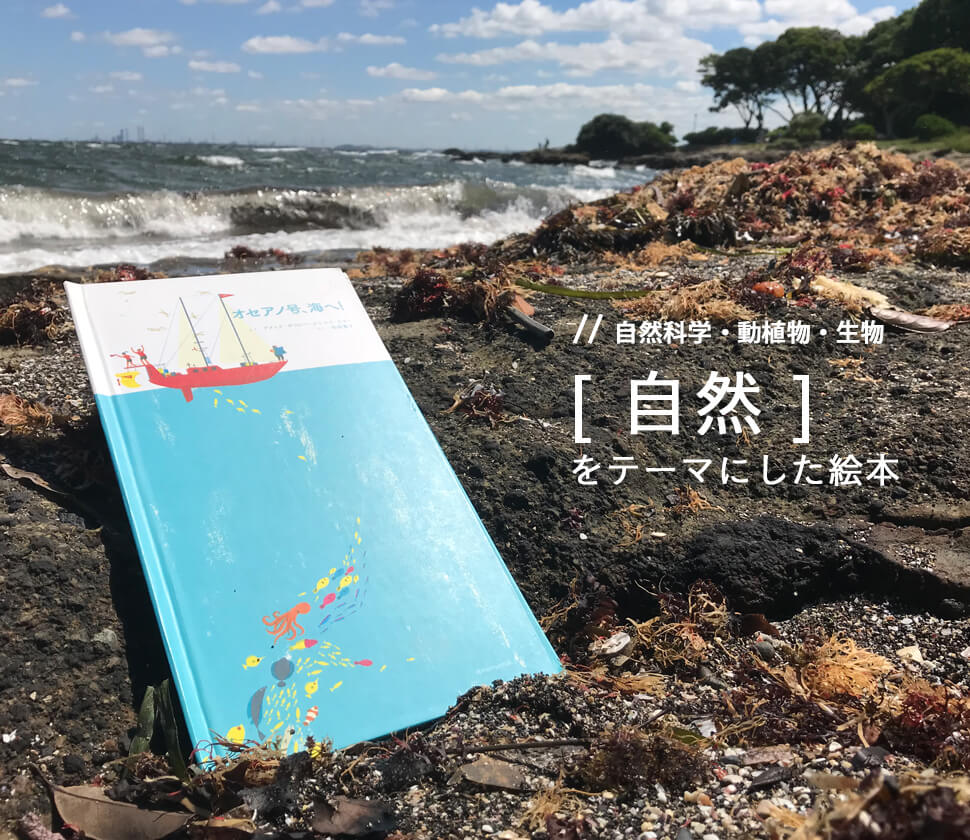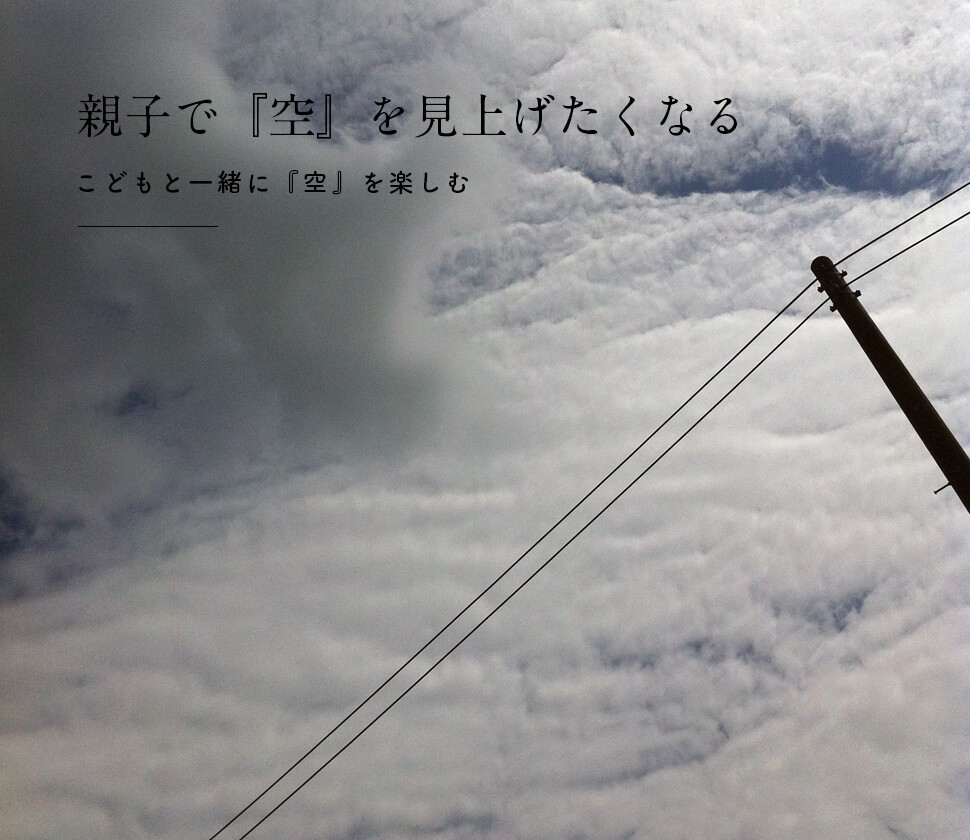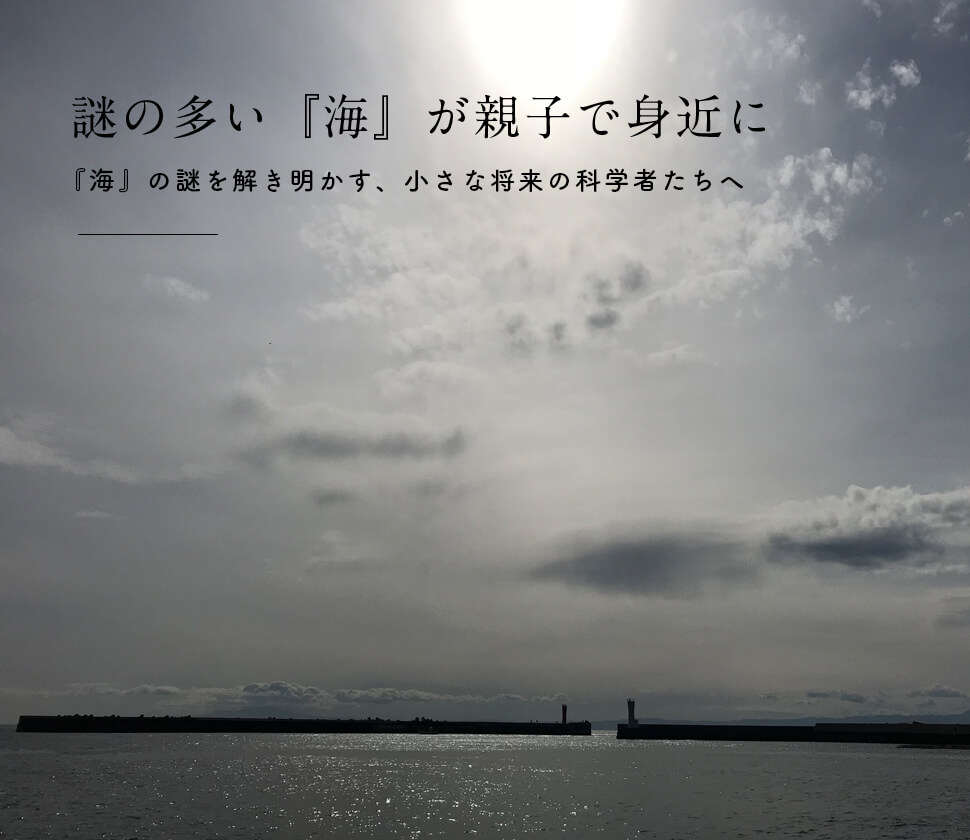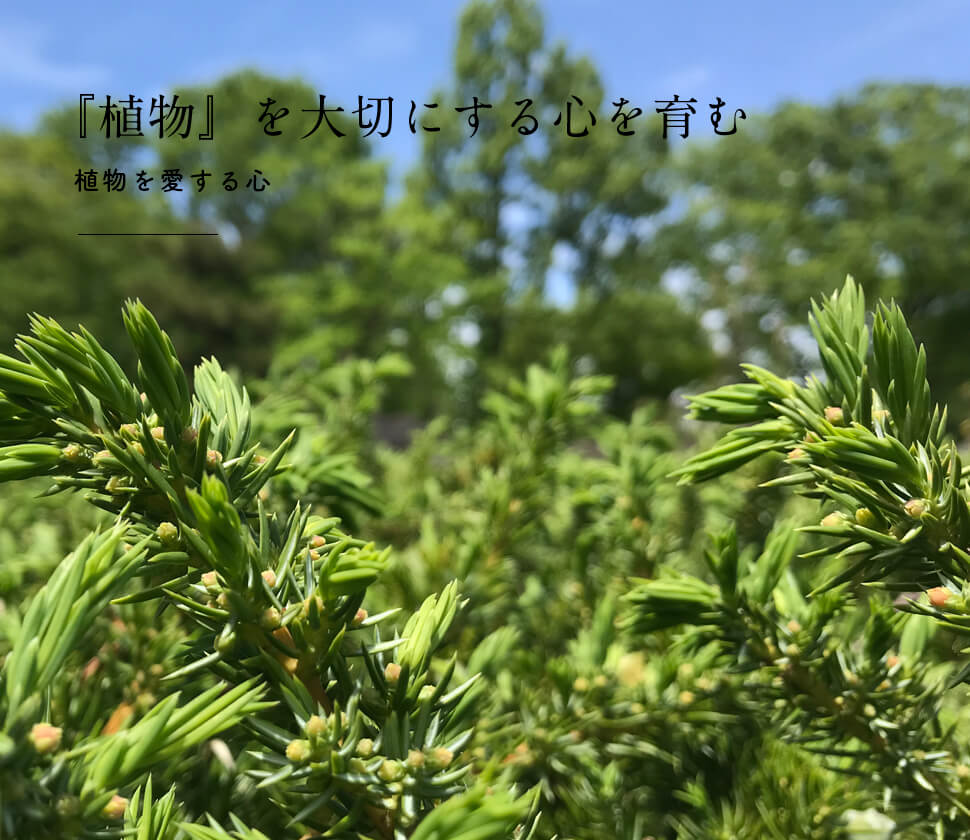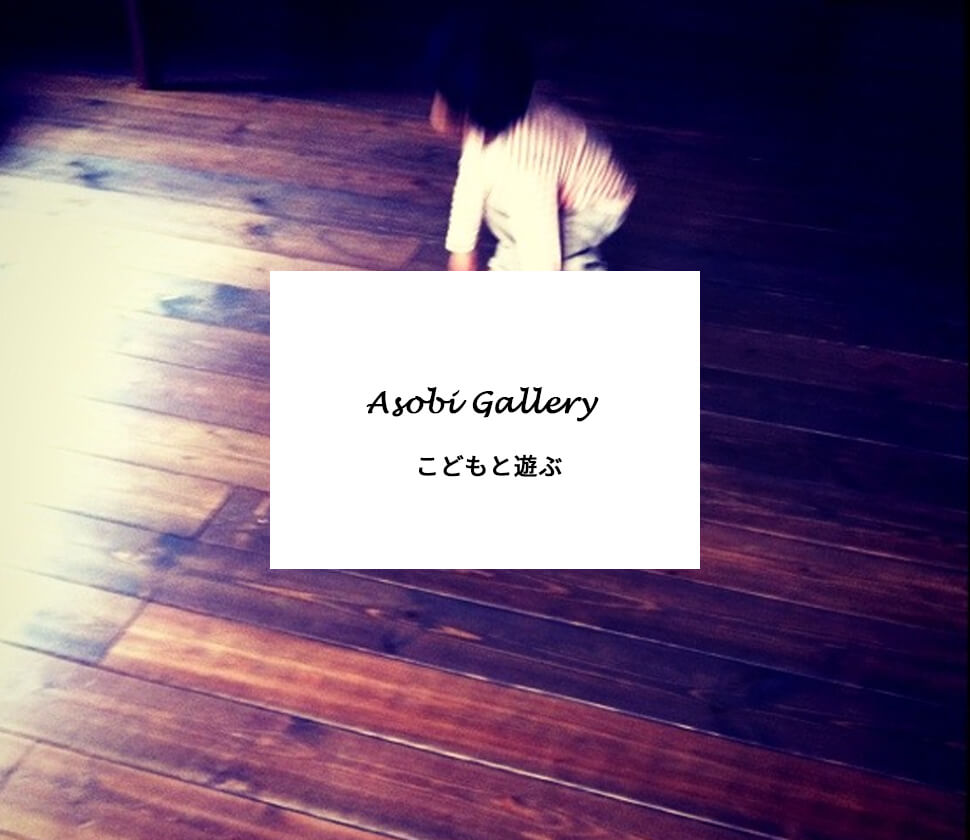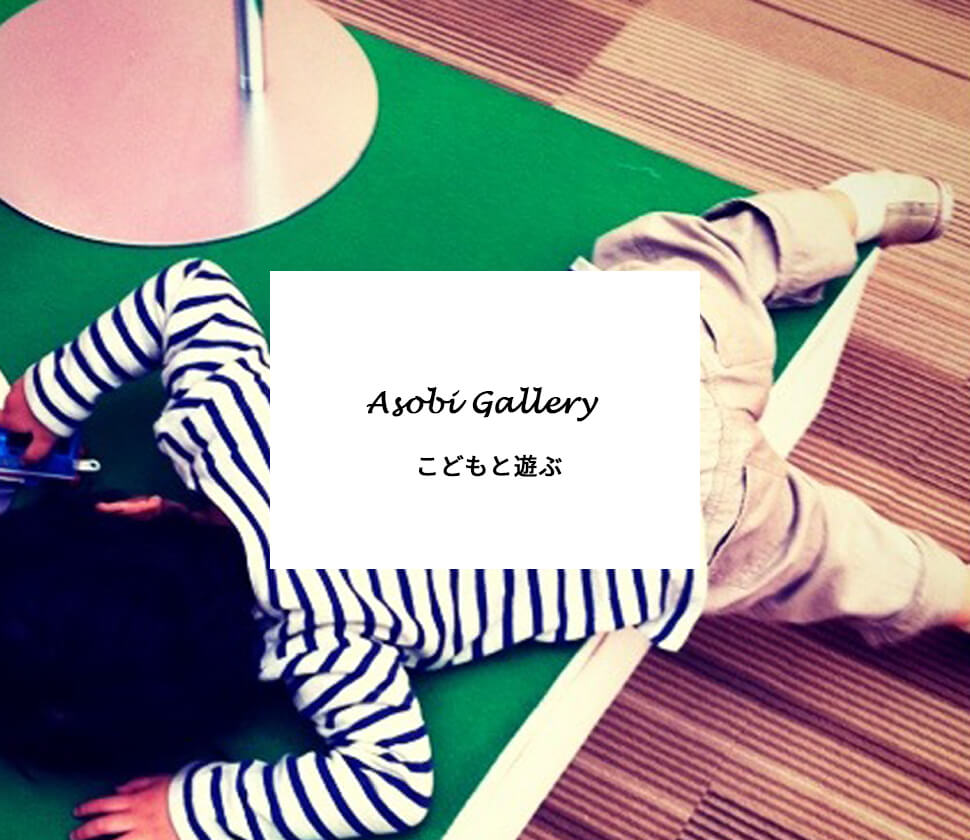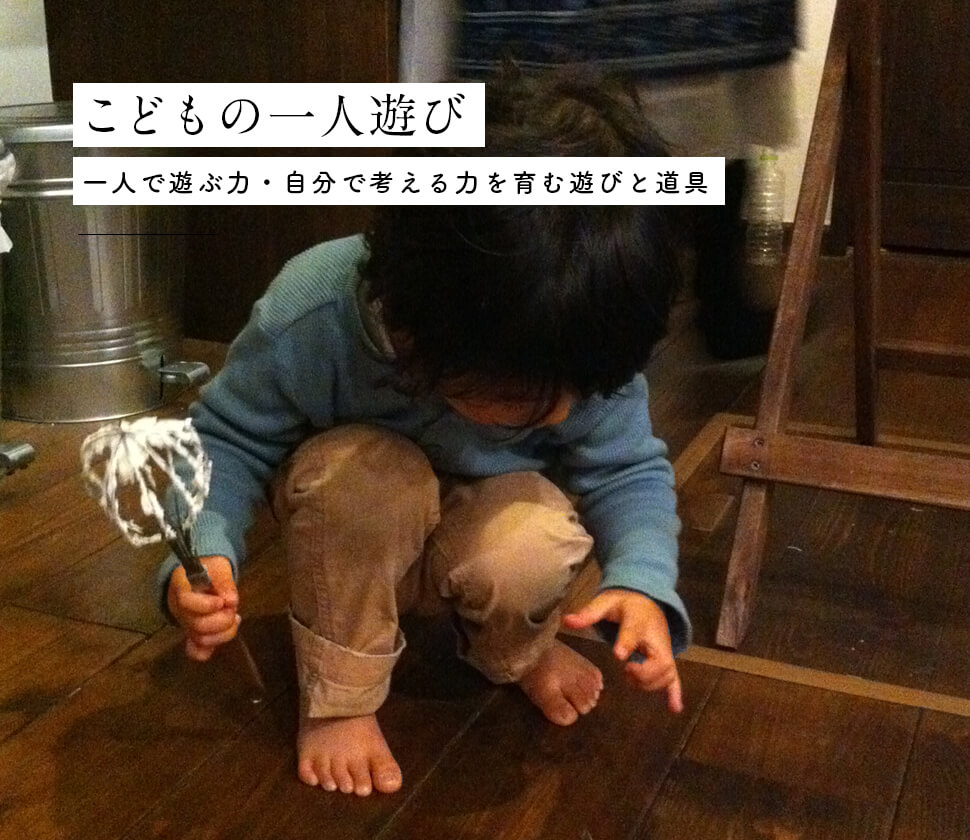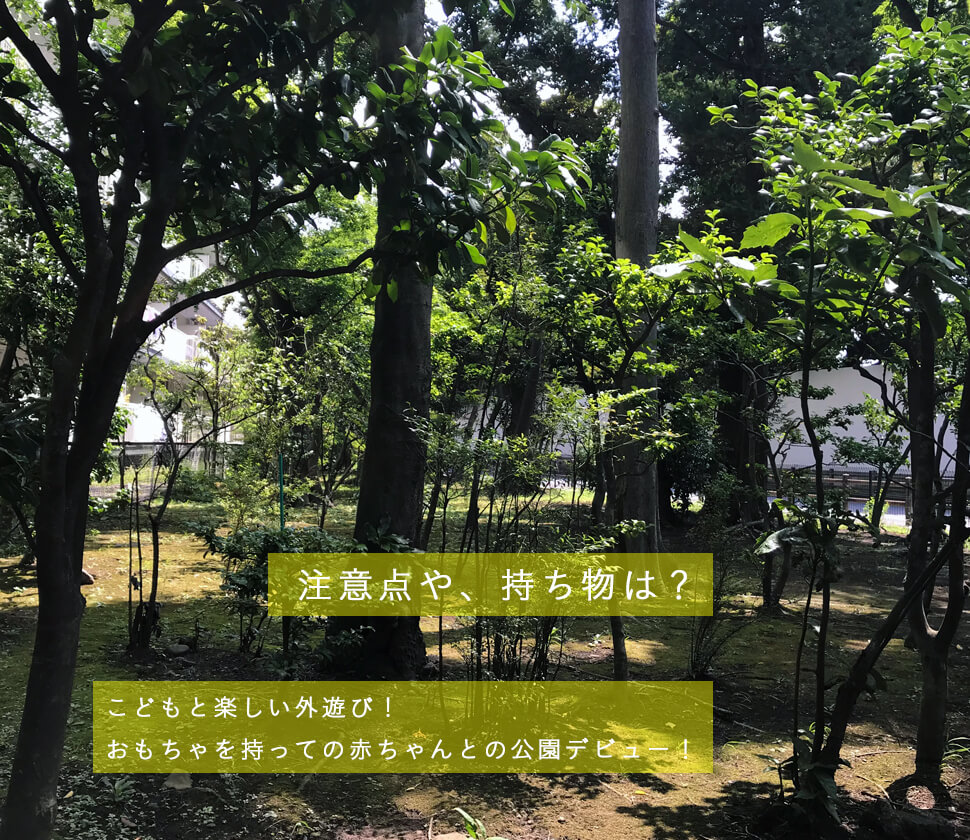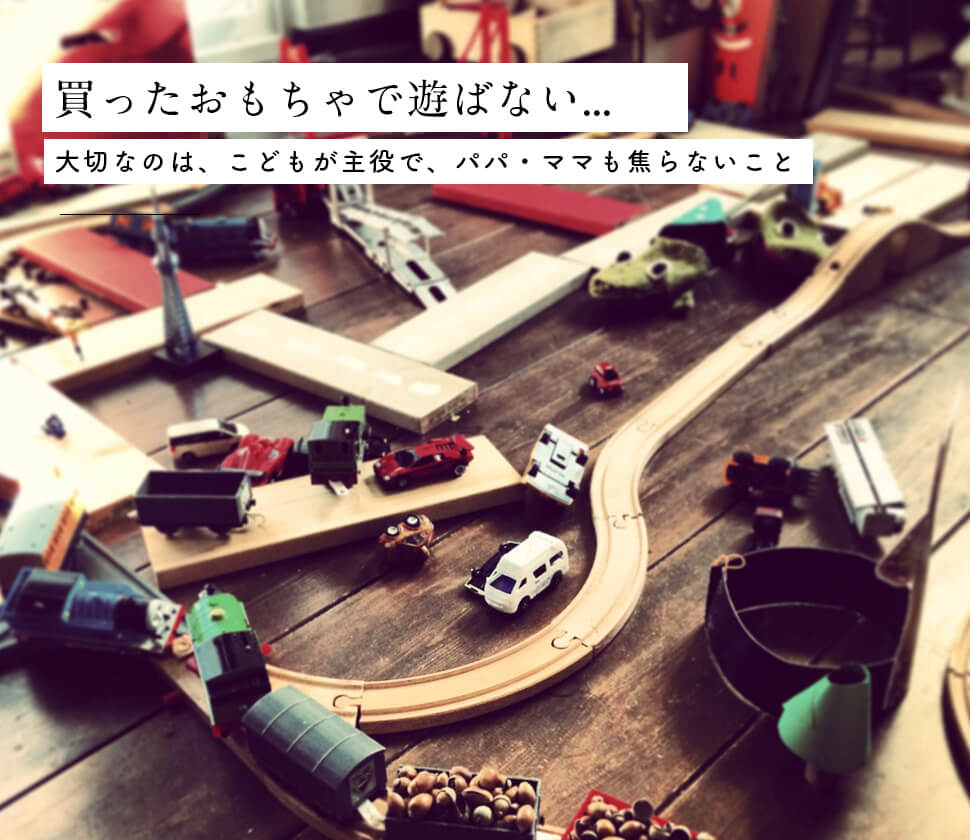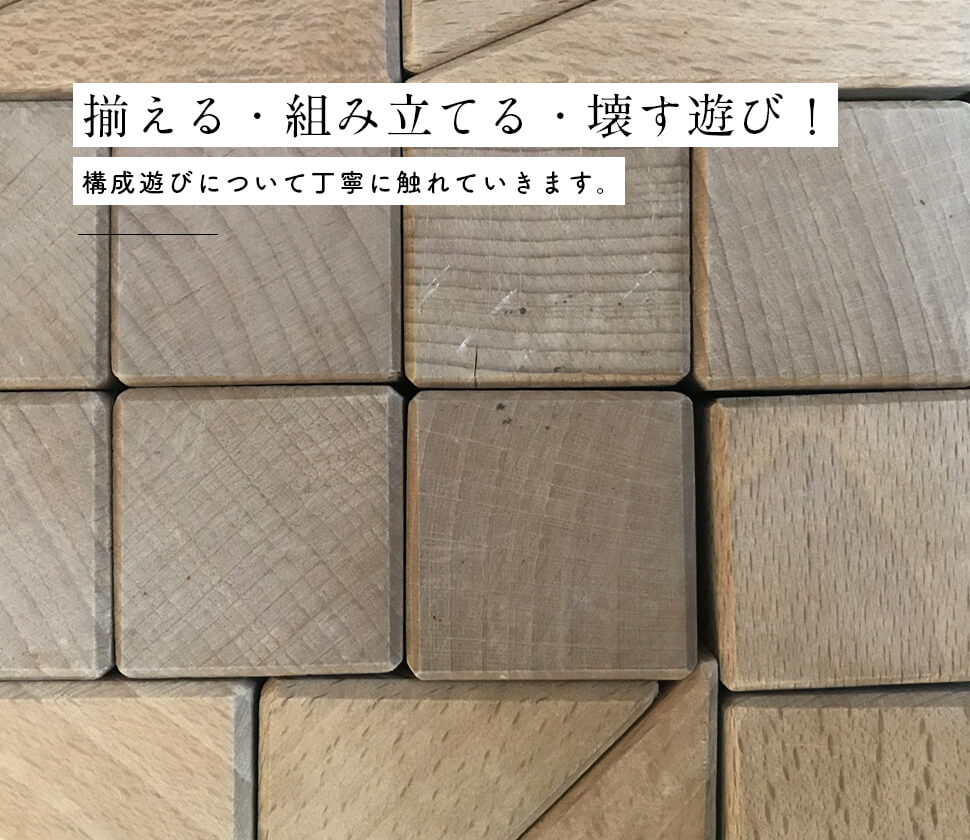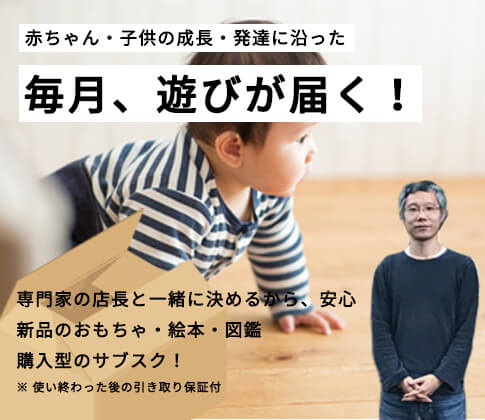読み物
最終更新日:2025年4月7日
絵・写真・文:いろや商店の編集室
れんさいプロジェクト:赤ちゃん・こどもを育む環境づくり
はじめての『粘土遊び』はいつから?注意点や育まれる力
はじめての粘土遊び
遊びのポイントから、興味のない子まで!
指先を使ってこねたり、伸ばしたり、自由な形を作り出す粘土遊びは、子どもたちを夢中にさせる魔法のような魅力を持っています。粘土遊びは単に楽しいだけでなく、子どもの心と体の成長に欠かせない大切な力を育みます。なぜ粘土遊びが子どもの発達に良いと言われるのか? 安全に、そして子どもの「やってみたい!」を引き出すためには、大人はどのように関わればいいのでしょうか?
ここでは、粘土を扱っている店長として、そんな疑問や不安に一つひとつお答えしていきます。粘土遊びを始める目安の年齢から、安全な粘土の選び方、遊びを通して育まれる「創造力」や「集中力」などの力、そしてご家庭でできる環境づくりのポイントまで、当店で扱っている粘土にも触れながら、詳しく解説していきます。この記事を参考に、親子で安心して粘土遊びの世界を楽しみ、子どものより良い成長をサポートしませんか?

いろや商店の店長のおおま(@iroyaonline)です。
ご覧いただきましてありがとうございます。
育児・子育て苦手な店長が、こどもが主役で書いてますのでゆっくりご覧くださいませ〜。

会員登録ですぐに使える!
粘土遊びで大切なこと
粘土遊びはただの遊びではありません。
「粘土遊びをはじめとする造形遊びは、子どもの自由な創造力を育む大切な活動です。粘土遊びでの指先を使ってこねたり、丸めたり、伸ばしたりする活動を通して、子どもの成長に欠かせない集中力や、表現力が育まれます。造形遊びの中で特に大切なのは、上手にできることよりも、創作する楽しさや、表現を形にする楽しさを実感することです。
ちなみに、造形遊びについては「親子でつくる喜び!『造形遊び』は失敗も成功もない自由な発想・表現を楽しむ遊び」でも触れていますので、あわせてご覧ください。
粘土をこねて、形を作ったり、色のついた粘土を混ぜて色の変化を楽しんだりと、一言で『粘土遊び』と言っても遊び方はさまざまです。
いろいろな遊び方を楽しむ中で、子どもは試行錯誤を繰り返します。その過程で生まれる「楽しい!」という気持ちがさらに遊びを発展させ、もっとやってみたいという意欲に繋がります。上手くできるかどうかは問題ではありません。大切なのは、子どもが自らの手を使い、試行錯誤しながら、自分だけの世界を創り出すことです。
子どもが粘土遊びの中で十分に表現するためには、表現を形にする楽しさを味わえる環境を用意したり、適切な大人の関わりが不可欠です。大人は日常生活や遊びの中で、つい「こうしてみたら?」と助言してしまいがちですが、造形遊びのときは特に意識して見守るようにしましょう。子どもは「こうしたらどうなるだろう?」「次はこうしてみよう」と、主体的に考え、行動するようになります。これについては「こどもの『自発的・主体性を育む遊び』のサポートをするおもちゃが人気な理由」でも触れています。
また、自分の思いを形にできた時の達成感は、自己肯定感を高めるので、子どもが達成感を感じたときには十分に共感してください。環境づくりや、大人の関わり方については、後ほど詳しく解説します。

ここでは、『粘土遊び』をはじめる前に、知っておきたいことについて書きました。
『粘土』があれば、自由に楽しめる遊びですが、遊び方について理解することで、もっと深く遊ぶことができるはずです。
- 店長が解説!『粘土』を徹底比較
- いろや商店がはじめての方へ
- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』
- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて
- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。
粘土遊びで育まれる『5つの力』
粘土遊びは、遊びながら子どもの成長に欠かせないさまざまな力が育まれる活動です。
ここでは、粘土遊びを通して育まれる5つの力について解説していきます。
粘土遊びで育まれる『5つの力』は以下のとおりです。
- 手先の器用さ
- 創造力
- 集中力
- 表現力
- 社会性
1つ目は「手先の器用さ」です。
粘土をこねる、丸める、伸ばす、ちぎるなどの動作は、手先の細かな動きを促し、器用さを高めます。手先が器用になることで、日常生活におけるさまざまな動作もスムーズに行えるようになります。指先や手を使った遊びの重要性については「握るからつまむへ!乳幼児期に『指先や手を使った遊び』を育むおもちゃが大切な理由」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
2つ目は「創造力」です。
自分で考えたものを形にしたり、何気なく出来上がった形がいろいろなものに見えたりと、粘土遊びを通して創造する力が豊かになります。「何を作ろうかな?」「どうやって作ろうかな?」と考える中で、頭の中にイメージを思い描いて、形にする経験の積み重ねが大切です。
3つ目は「表現力」です。
創造したものを自分なりの方法で表現する力です。年齢が上がると、複雑な形で表現したり、色のついた粘土を使って色で表現したりとさまざまな表現する力が養われます。嬉しい気持ちや楽しい気持ち、悲しい気持ちなど、言葉では上手く表現できない感情を色や形で表現することで、表現力が豊かになるのです。
色遊びについては「色を覚える・学ぶ!おもちゃ・絵本で遊びながら子供の色彩感覚・色彩認知を育む」や「わー、きれい!こどもと色遊び。自宅で美しい色の変化を親子で楽しむ遊びをしよう」で触れていますので、ぜひご覧ください。
4つ目は「集中力」です。
指先を使った細かな作業に取り組み、試行錯誤を繰り返すことで、自然と集中力が高まります。粘土遊びに没頭すると、大人も子どももあっという間に時間が経っているということは珍しくありません。一般的に、子どもの集中力は「年齢+1分」と言われていますが、粘土遊びに夢中になると、それ以上の時間集中して遊ぶ姿もみられます。
5つ目は「社会性」です。
友達同士や親子で一緒に粘土遊びをする中で、コミュニケーション能力や協調性が育まれ、社会性が身に付きます。冷たい、柔らかいなど感じたことを言葉にする機会が増えるので、言葉の理解にも繋がります。作品を見せ合ったり、意見を交換し合ったりと、粘土遊びは他者との関わりも生み出す遊びなのです。
「『言葉遊び・文字遊び』コミュニケーション能力を遊びから育むおもちゃ・絵本・図鑑」では、コミュニケーション能力を育む遊びやおもちゃを紹介しています。また、社会性を育む遊びについては「こどもの根気や集中力を養い社会性を育む、ルールのある遊び・ゲームが人気の理由」で触れていますので、ぜひ合わせてご覧ください。
粘土遊びという一つの活動の中で、さまざまな力が育まれ、子どもが遊びを楽しめば楽しむほど、いろいろな角度から良い発達が促されます。子どもにとって「遊び」がどれだけ大切なものかということがお分かりいただけたのではないでしょうか。「工夫して遊び学ぶ力を育む!幼児期のおもちゃ選びに大切なこと教えます」も参考にあわせてご覧ください。

ここでは、『粘土遊び』を通して育まれる力について書きました。
創作活動の道具として、粘土はありますが、粘土遊びを通してどのような点が育まれるかを知りながら取り組むことで、大切にするポイントも自ずと見えやすくなるかと思います。
- 店長が解説!『粘土』を徹底比較
- いろや商店がはじめての方へ
- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』
- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて
- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。
粘土遊びはいつから?
結論から言うと、粘土遊びは0歳児からでも始められます。
ただし、年齢や発達段階によって、適切な粘土の種類や遊び方、大人の関わり方が異なります。
0歳児はまだ自分で形を作ることは難しいですが、粘土の感触を確かめるだけでも、十分に楽しめます。柔らかい粘土を触ったり、握ったりすることで、触覚が刺激され、これは感触遊びの一環として、五感の発達を促します。この時期は、誤飲の危険性があるので、必ず口に入れても安全な素材の粘土(小麦粉粘土、寒天粘土など)を選び、大人が必ずそばで見守ることが大切です。
なお、粘土の種類や特徴については「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『粘土(ねんど)』を徹底比較」で解説していますので、粘土選びの参考にしてみてください。0歳児については「【0歳・赤ちゃん】成長・発達に沿ったおもちゃ・絵本と遊び」で丁寧に解説しています。また、0歳児に人気のおもちゃ・知育玩具については「【0歳・赤ちゃん】人気の知育玩具・おもちゃ選び専門家がおすすめを徹底比較解説!」でも書いていますので参考にご覧ください。
1歳頃になると、指先の発達が進み、粘土をちぎったり、丸めたりする動きが少しずつできるようになります。大きなかたまりを手でつかんで引きちぎる、丸くこねて手のひらで転がすといった、シンプルな動作そのものが遊びになります。この時期は、まだ道具を上手に使うのは難しいですが、親が簡単な型抜き(例えば丸や星など)を使って見せてあげると、興味を示し、同じようにやってみようとする姿が見られるようになります。型に粘土を詰めて押し出すなどの遊びも、少しずつ真似するようになります。なお、1歳頃については「【1歳】成長・発達に沿ったおもちゃ・絵本・図鑑と遊び」で月齢に応じて解説しています。また、1歳児に人気のおもちゃ・知育玩具については「【1歳】人気の知育玩具・おもちゃ選び専門家がおすすめを徹底比較解説!」でも書いていますので、それぞれを参考にご覧くださいませ。
2歳頃になると、少しずつ言葉や思考の発達が進み、想像力が豊かになってきます。この時期の子どもは、頭の中にある「〇〇みたいなもの」を粘土で表現しようとするようになり、形にするために試行錯誤する姿が見られるようになります。たとえば「ごはん」「バス」「ネコ」など、身近なものや身の回りのものをテーマにしながら、自分なりのイメージを粘土で再現しようとしたり、「これ○○だよ!」と大人に説明してくれたりする場面も増えていきます。まだ完成度は高くありませんが、自分でつくったものに意味づけをしたり、役割を与えたりするようになります。また、例えば粘土ベラや型抜き、ローラーなどを使ってみることにも興味を示しはじめ、自分の手だけでは難しい形や模様をつけることを面白がるようになります。さらに、色の違う粘土を組み合わせてみたり、ちぎって貼りつけてみたりする中で、表現の幅が少しずつ広がっていきます。遊びの中では「〇〇に見立てる遊び」や「ごっこ遊び」といった要素が少しずつ入り始めることもあり、粘土遊びが単なる造形の活動にとどまらず、ストーリー性や役割をもつ遊びへと発展していきます。2歳児については「【2歳】成長・発達に沿ったおもちゃ・絵本・図鑑と遊び」で書いています。そして、2歳児に人気のおもちゃ・知育玩具については「【2歳】人気の知育玩具・おもちゃ選び専門家がおすすめを徹底比較解説!」で丁寧に解説しています。
3歳以上になると、指先の巧緻性や集中力、そして言葉や社会性の発達が進み、粘土遊びの内容もさらに豊かになっていきます。この時期は、より複雑な形を作ることができるようになり、「丸める」「伸ばす」「ちぎる」といった基本的な動作を組み合わせて、動物や食べ物、乗り物などイメージに沿った具体的な作品を作る姿が見られるようになります。道具の使い方も上達し、細かな形を整えたり、模様をつけたりすることも楽しむようになります。色の組み合わせや配置にも意識が向くようになり、「赤はイチゴ、緑は葉っぱ」など、現実の世界と遊びを結びつけた表現が増えていきます。
また友達と一緒に遊ぶことも増え、協力して一つの作品を作ったり、役割分担をして「ケーキ屋さん」「お弁当づくり」などのごっこ遊びに発展することもあります。自分と他者の意見やアイデアを取り入れる中で、社会性やコミュニケーション能力も自然と育まれていきますし、完成した作品を「見て見て!」と大人に見せることも増え、作品に対する自信や達成感が育つ時期でもあります。3歳児については「【3歳】成長・発達に沿ったおもちゃ・絵本・図鑑と遊び」で書いています。そして3歳児に人気のおもちゃ・知育玩具については「【3歳】人気の知育玩具・おもちゃ選び専門家がおすすめを徹底比較解説!」で丁寧に解説しています。
このように、粘土遊びは0歳から楽しめますが、年齢が上がるにつれて、遊びの内容も、大人の関わり方も変化していきます。
大切なのは、子どもの発達段階に合わせて、無理なく、安全に、そして何よりも「楽しい!」と感じられるようにサポートすることです。

よく質問されることに、粘土遊びは「いつから?」というのがあります。
ここでは月齢ごとの遊び方についても触れていますので、参考にしながら取り組んでみてください。
- 店長が解説!『粘土』を徹底比較
- いろや商店がはじめての方へ
- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』
- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて
- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。
大人の関わり方のポイント
粘土遊びは、子どもの自由な発想や表現力を育む上で、非常に効果的な遊びですが、その効果を最大限に引き出すためには、大人の適切な関わり方が不可欠です。
文部科学省が定める保育所保育指針の中では「表現」の分野における保育者の関わりとして、以下のように示しています。
② 子どもが試行錯誤しながら様々な表現を楽しむことや、自分の力でやり遂げる充実感などに気付くよう、温かく見守るとともに、適切に援助を行うようにすること。
③ 様々な感情の表現等を通じて、子どもが自分の感情や気持ちに気付くようになる時期であることに鑑み、受容的な関わりの中で自信をもって表現をすることや、諦めずに続けた後の達成感等を感じられるような経験が蓄積されるようにすること。– 1歳以上3歳未満児の保育に関わるねらい及び内容 オ 表現
まずは、子どもと一緒に粘土遊びを思いきり楽しんでみてください。
その中で、発見や喜びに一緒に驚いたり、共感したりすることで、子どもの「楽しい」という気持ちに寄り添うことができます。そして、安心できる大人に見守られながら、気持ちを受け止めてもらうことで、子どもはより遊びに集中できます。大人が「こうしなさい」と指示したり、手伝いすぎたりするのではなく、子どものやりたいことを尊重しましょう。その結果出来上がった作品を、上手下手で評価するのではなく「ここを頑張ったんだね」など、子どもの表現に寄り添う言葉がけを意識してみてください。
また、年齢に応じて大人の関わり方も異なります。
0~2歳なら、大人も一緒に粘土の感触を楽しみましょう。また、誤飲防止のため、常に見守りが必要です。
3~4歳なら、子どもの姿を見守りながら、必要に応じて声掛けや手助けをします。
5歳以上になると自分でできることが増え、誤飲の可能性も低くなるので、最小限の見守りで自主性を尊重し、集中を妨げないように配慮しましょう。
大人の関わり方次第で、粘土遊びは、より楽しく学びの多い時間になります。
子どもの成長をサポートするために、適切な関わり方を心がけると、粘土遊びを通して、子供がチャレンジをして成長していく様子が見られるはずです。

子供を見るというよりも、一緒になって楽しむのが月齢の小さい頃では大切です。
その後、自分でイメージを形にできるようになってきたら、そっと見守り、子どもの完成したものを評価するのではなく、子供の意思を聞いてより良いモノづくりができるように導くのも大人の役目ですね。
- 店長が解説!『粘土』を徹底比較
- いろや商店がはじめての方へ
- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』
- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて
- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。
粘土遊びをしたがらない子・苦手な子の原因と対応
ここまで、粘土遊びの素晴らしさを解説してきましたが、中には粘土遊びをしたがらない子どももいます。
考えられる原因を挙げてみましょう。店長もよく耳にするのは以下のような点です。
- 感覚が過敏で、粘土の感触が苦手
- 親や周囲の大人が「汚れること」に過敏になっている
- 楽しく汚れながら遊ぶという経験が少ない
- 何をしたら良いのかわからない
- 集中して取り組む遊びにまだ慣れていない
1つ目の原因として、感覚が過敏で、粘土の感触や冷たさを嫌がっていることが考えられます。
嫌がっているのに無理に触らせようとすると、粘土遊びに対してさらに嫌なイメージを持ってしまうので、無理強いは禁物です。まずは大人が楽しく遊ぶ様子を見せて、粘土遊びに興味を持ってもらうように働きかけましょう。また、粘土用の道具やスプーン、カップなどを用意して、直接粘土を触らずに楽しめる工夫をしてみてもいいでしょう。例えば、当店で扱っている蜜蝋粘土は温かくなると柔らかくなり形状を整えやすいタイプのものです。先にご家族が柔らかくほぐすことで、少し温かさが残った状態で楽しむことができますので、そういった粘土素材から考えるのもおすすめです。
2つ目の原因として、普段の生活で、親が周囲の大人が「汚れること」に過敏になっている可能性が考えられます。
食事中や外遊びの場面などに「汚れるからやめて」と言ったり、汚したときに過剰に叱ったりしていると、子どもの中で「汚れること=いけないこと」というイメージができ、粘土遊びも汚れる遊びだと思ってしまいます。洋服などが汚れてしまうと、つい叱ったり嫌な顔をしたくなりますが「汚れること=子どもがよく遊んだ証」という考えを持って対応してみてください。外遊びでは泥だらけになるくらい遊べるのは勲章ですし、本もボロボロになるまで使うことができるのも才能です。綺麗であることが良いことではないことが子育ての場面では多いですので、その辺り頭に入れておくと良いかもしれませんね。
3つ目の原因は、2つ目の原因と共通しますが、楽しく汚れながら遊ぶ経験が少ないということが考えられます。
汚れを気にしながら遊ぶと、遊びになかなか集中できません。粘土遊びだけでなく、実際の絵の具遊びや泥遊びの場面では、手や衣服が汚れると気になって、その都度洗いたがる子どももいます。こういった原因が考えられる場合は、まずは大人が遊びを楽しみ、汚れることは嫌なことでもダメなことでもないことを伝えてあげてください。その上で「一緒にやってみよう」「汚れても大丈夫だよ」と声掛けすると、子どもは安心して「ちょっとやってみようかな」という気持ちになったりするものです。また、大人が率先して汚れることで安心感を与えることもできます。
また、ザラザラやふわふわ、冷たいなどいろいろな感触に触れることに慣れるよう、粘土以外の感触遊びにも挑戦してみましょう。ラップやビニール袋に入れた素材を触ってみるなど、段階を踏んで少しずつ慣れるような工夫も効果的です。
粘土以外の感触遊びや感覚遊びについては「こどもの『感触遊び・感覚遊び』はインクルーシブに楽しめる五感を使った遊び」で紹介しています。
「夏も冬も楽しい!『氷遊び』感覚・感触を育み、状態の変化を学ぶ」では、生活の中で身近な「氷」を使った感触遊びを紹介しているので、ぜひご覧ください。
また、「何をしたら良いのかわからない」や「集中して取り組む遊びにまだ慣れていない」といったこともよく聞きます。
粘土は自由に楽しめる反面、何をしたら良いかと目的が見えなくなりがちです。なので、いきなり手渡しても何をしたら良いのかわからない。ということは多いです。こういう時は、ご家族が先にお手本を見せて、一緒に同じ形のものを作るところから始めてみてください。例えば、家にあるリンゴ・バナナなど、目の前に置いて同じものを作るというのでも良いです。参考になるものと同じものを作る。もちろん、同じ形に見えなくても、それに向かって取り組むというのが何よりも大切です。
そして、粘土遊びは比較的落ち着いた環境でじっくり取り組む活動です。活発な遊びや短時間で達成感が得られる遊びを好むタイプの子は、粘土に興味が向きにくいこともあります。そういう場合は、少し時間を決めて、好きなものと同じものを作ったり、作った遊びに出よう!のように取り組むのがおすすめです。そうすることで次第に創作する時間の楽しさを理解できるようになっていきます。いきなり満点を目指すのではなく、少しずつ取り組む時間を増やしていく感じで取り組んでみてください。
このように、粘土遊びをしたがらない子には、さまざまな原因が考えられます。
子どもの様子をよく観察し、原因に合わせた対応をすることで、少しずつ粘土遊びの楽しさを伝えてみてください。

粘土遊びはとても楽しいことなのですが、したがらない子・苦手な子もいます。
それには原因となることや、過去に叱られたなど何か起因することがあったりもしますので、他の遊びなども含めて一度考えてみると、解決のきっかけが見つけられるはずです。
- 店長が解説!『粘土』を徹底比較
- いろや商店がはじめての方へ
- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』
- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて
- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。
粘土遊びの環境づくり
粘土遊びを存分に楽しむためには、適切な環境づくりが大切です。
まずは安全な環境を整えましょう。粘土遊びで最も注意すべきなのは「誤飲」です。特に0~2歳の子どもが遊ぶ場合は、万が一口に入れてしまっても安全な素材の粘土を選んでください。代表的なのは、小麦粉粘土ですが、アレルギーの危険性があるため、米粉粘土や片栗粉粘土もおすすめです。もちろん、安全な粘土を使用していても、大人の見守りは必須です。
安全な粘土の他にも、年齢や発達に合った道具を用意しましょう。
0歳の赤ちゃんが遊ぶなら、ちぎりやすい柔らかい粘土を用意した方が遊びやすいです。また、粘土用の道具だけでなく、上でも少し触れていますが、カップやスプーンがあるだけでも、子どもの創造力が広がり、遊びがどんどん発展していきます。誤飲の心配がなくなってくる3歳ころからは、ビーズや木の枝などを用意すると、作品を飾ってさらに表現を楽しめるのでおすすめです。いろいろな道具や素材を組み合わせることで、粘土遊びで育まれる力が更に高まります。
例えば「落ち葉・木の実で遊ぶ!子供と簡単な作品づくりで新しい発見に出会う」では、落ち葉や木の実など、自然物を使った遊びを紹介していますので、あわせてご覧ください。
また、子どもが思いきり遊べるように、汚れ防止の対策をしましょう。
汚れても良い洋服を用意したり、テーブルにシートを敷いたりと、親が安心して思いきり遊ばせてあげられる環境を整えられるといいですね。それにより、子どもがのびのびと表現できるようになります。
このように、子供は「遊び」の中からさまざまなことを学び、身に付けて成長していきます。
子供が健やかに、よりよく成長するためには大人のサポートが欠かせません。年齢に合った適切な環境をつくり、大人も一緒に遊びに参加することで、子供はより多くの学びや気付きを得て成長していくのです。こうやって、一つ一つ子供の遊びの環境を作ることは、家庭でできる「幼児教育」の一つだと当店では考えています。幼児教育については「家庭で『幼児教育』5育を意識しておもちゃ・絵本・図鑑で遊び学ぶ」をご覧くださいませ。
なお、当店では一人一人にあった『遊び道具・遊び方』をお届けする定期便を提供しています。何を購入したら良いか?と悩んで結論の出なかった方は「絵本選書とおもちゃ・知育玩具の定期便・定期購読『いろや商店くらぶ』」のご利用も検討くださいませ。目標を決めて取り組むなど、通信教育のようなイメージで楽しんでいただくことも可能です。

この下には、店長による「まとめ(あとがき)」を簡単に書いてます。
『粘土遊び』は、長時間室内遊びに時間がある時におすすめの遊びです。このページを参考に、粘土遊びを楽しんでみてください!
もし、何か聞きたいことがあったら、当店の『いろや商店くらぶ』も検討してみてください。お子様の成長・発達に沿った遊びをサポートする身近な存在として、いつでもドシドシ!ご相談をお受けしております。📨
- 店長が解説!『粘土』を徹底比較
- いろや商店がはじめての方へ
- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』
- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて
- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。
会員登録ですぐに使える!
あとがき
ここでは「粘土遊び」を通して子どもたちの成長を育むために、大切なことについて解説しました。
ここまでお読みいただくと、粘土遊びが子どもの成長に大切な力を育み、その効果を最大限に引き出すためには、大人の適切な関わり方や環境づくりが重要であることがご理解いただけたと思います。
粘土遊びは、子どもたちにとってただの遊びではありません。手先の器用さ、創造力、表現力、集中力、そして社会性を育むかけがえのない学びの場です。
子どもたちは、粘土をこね、形を作り、色を混ぜる中で、いろいろな表現をしたり、喜びや達成感を感じます。
大切なのは、上手な作品を作ることではなく、創作の過程で生まれる「楽しい!」という気持ちです。
大人は、子どもの作品を評価するのではなく、その表現に込められた思いや工夫に寄り添い、共感することが大切です。
もし、子どもが粘土遊びを嫌がったとしても、原因を探りながら少しずつ慣れていけるように対応しましょう。
この記事を参考に、子どもと一緒に粘土遊びを楽しみ、その成長を温かく見守ってください。子どもたちの健やかな成長を心から願っています。