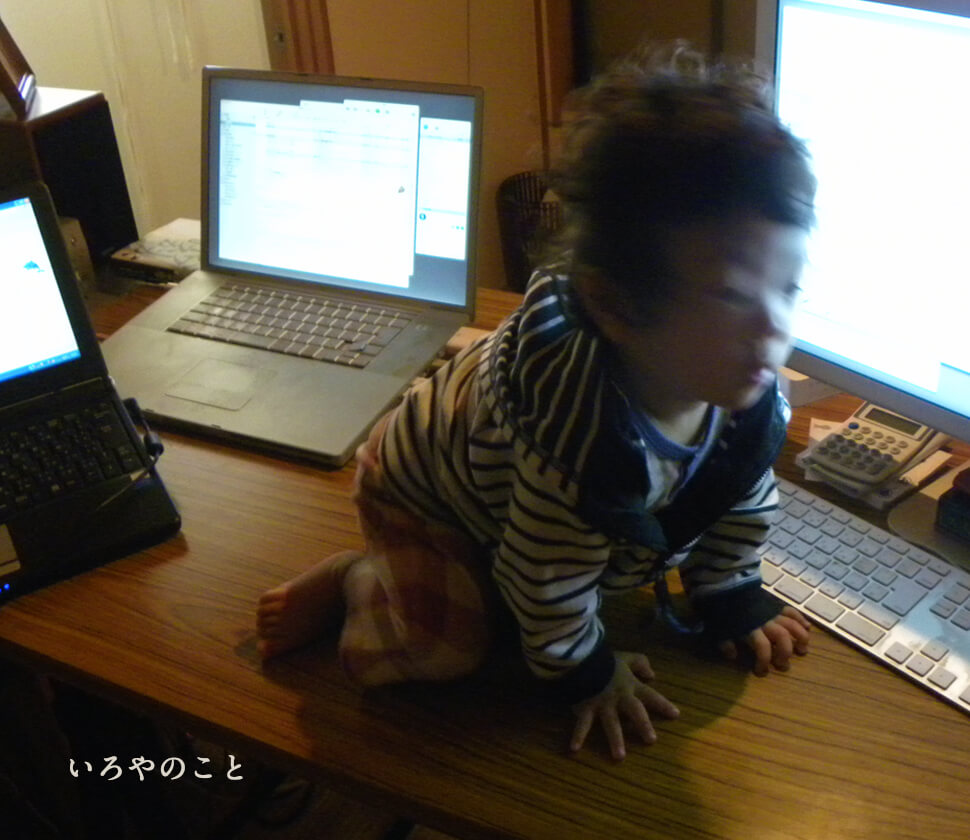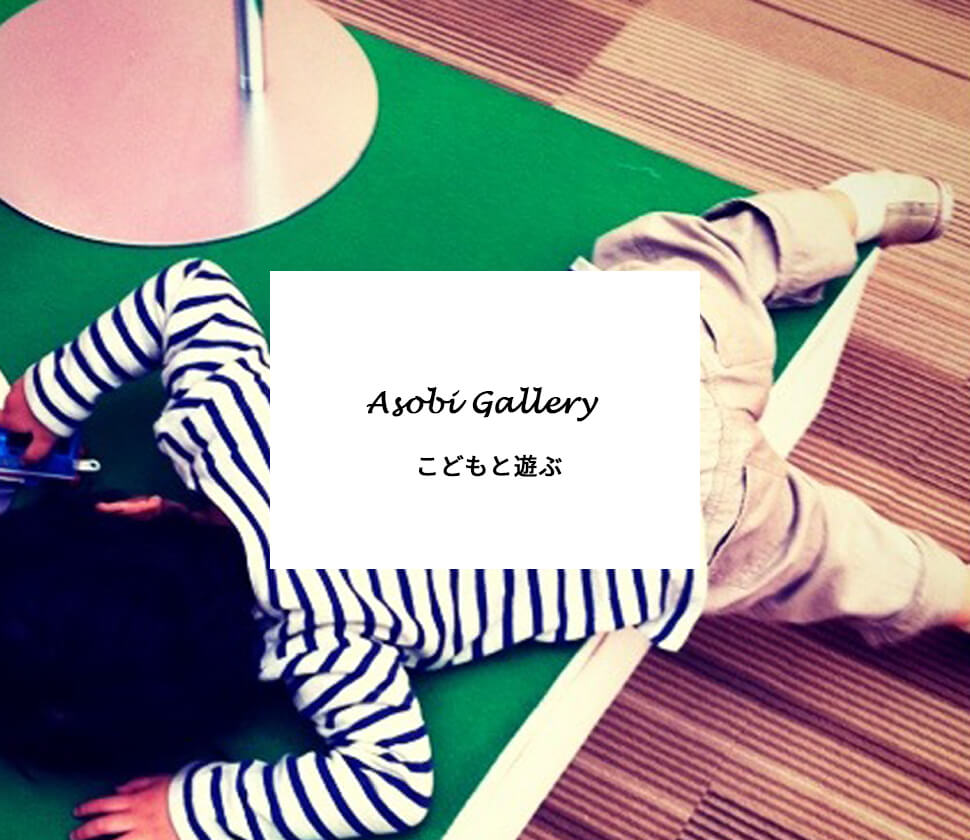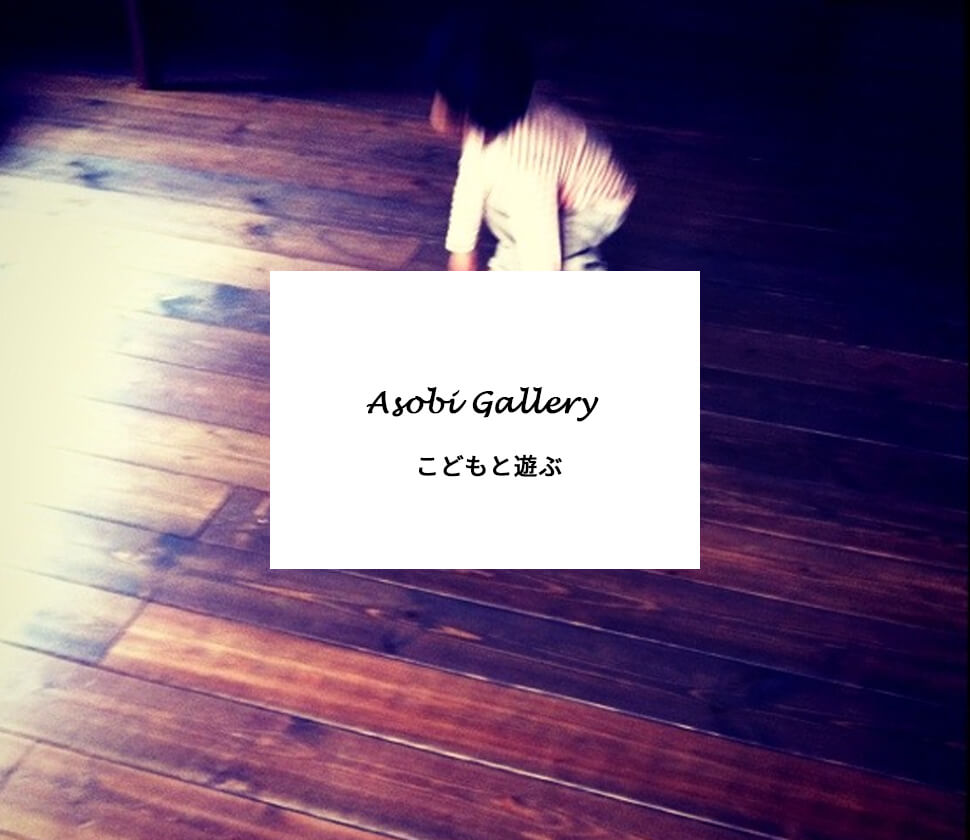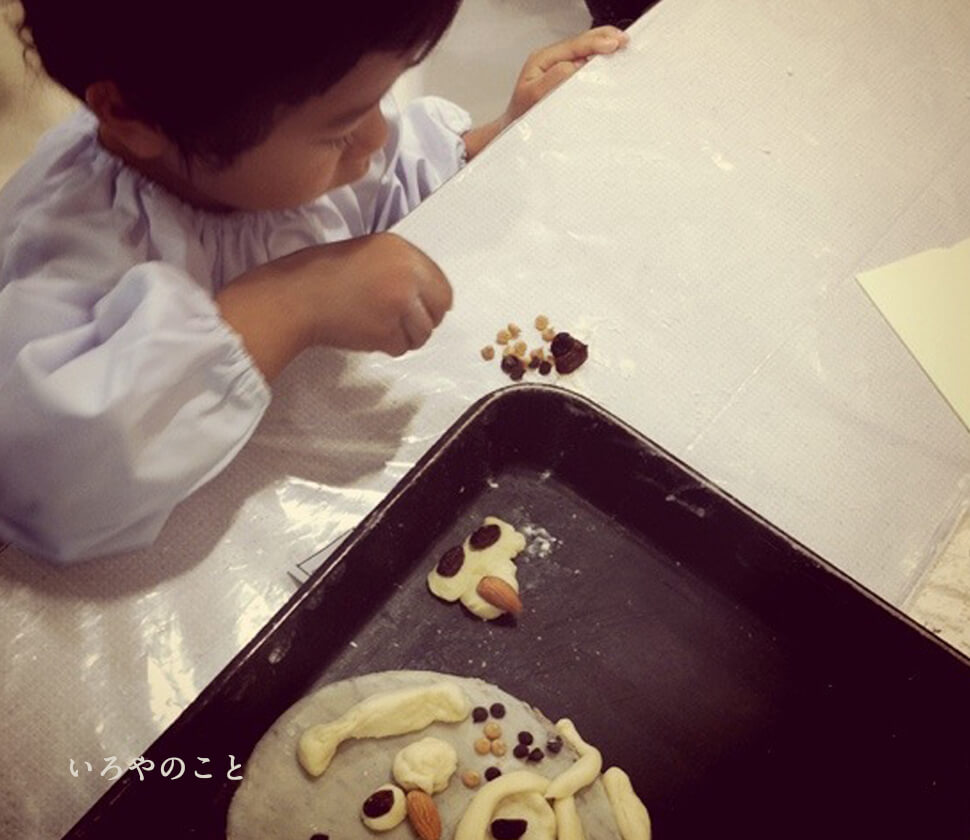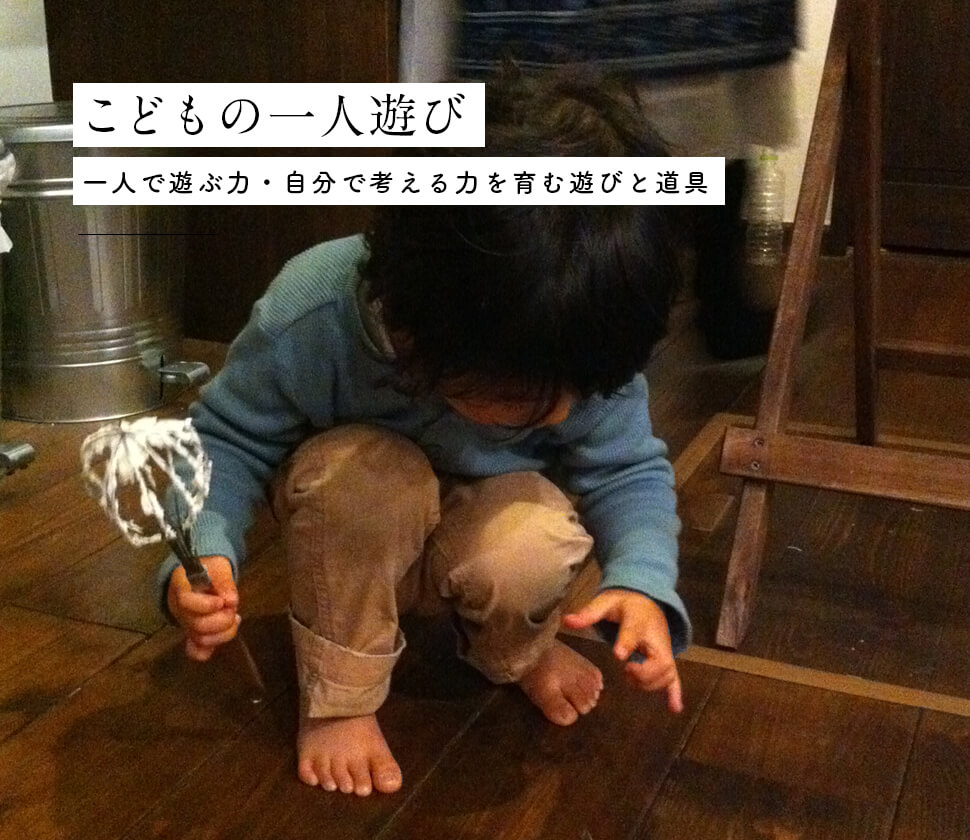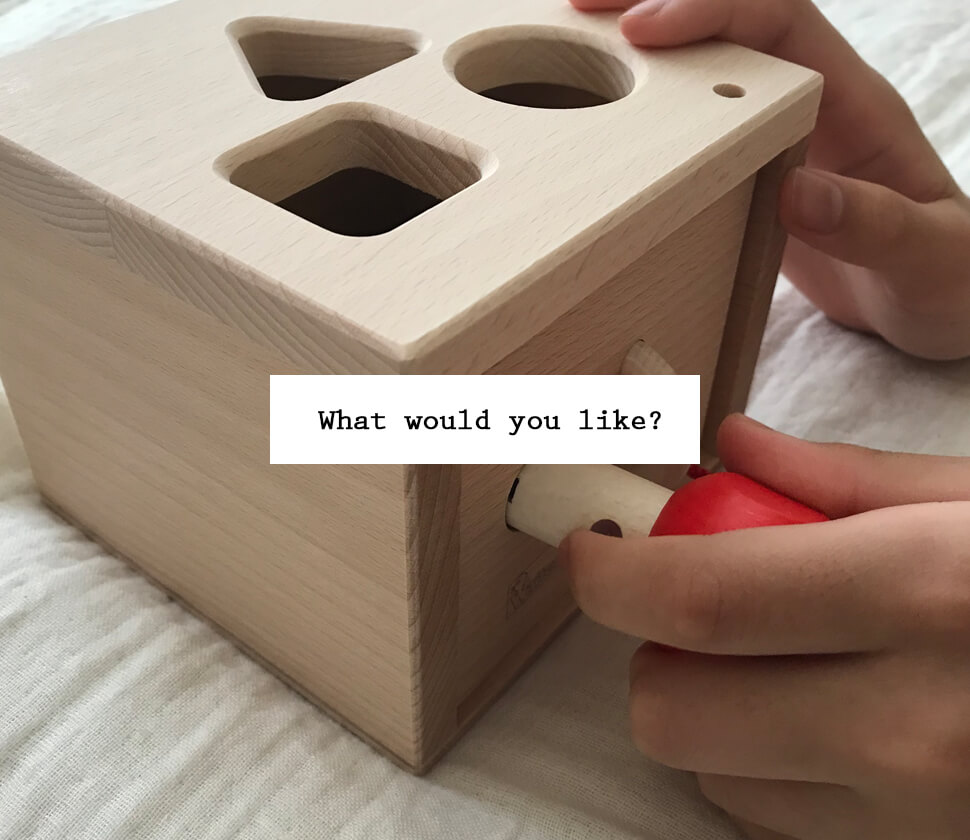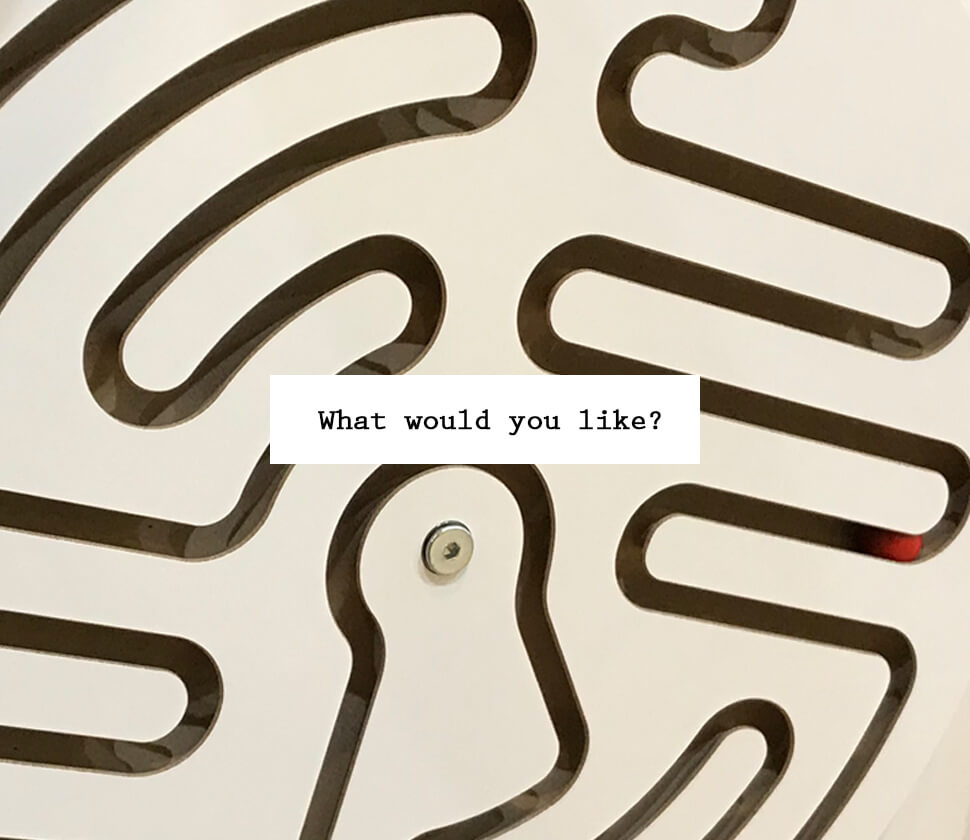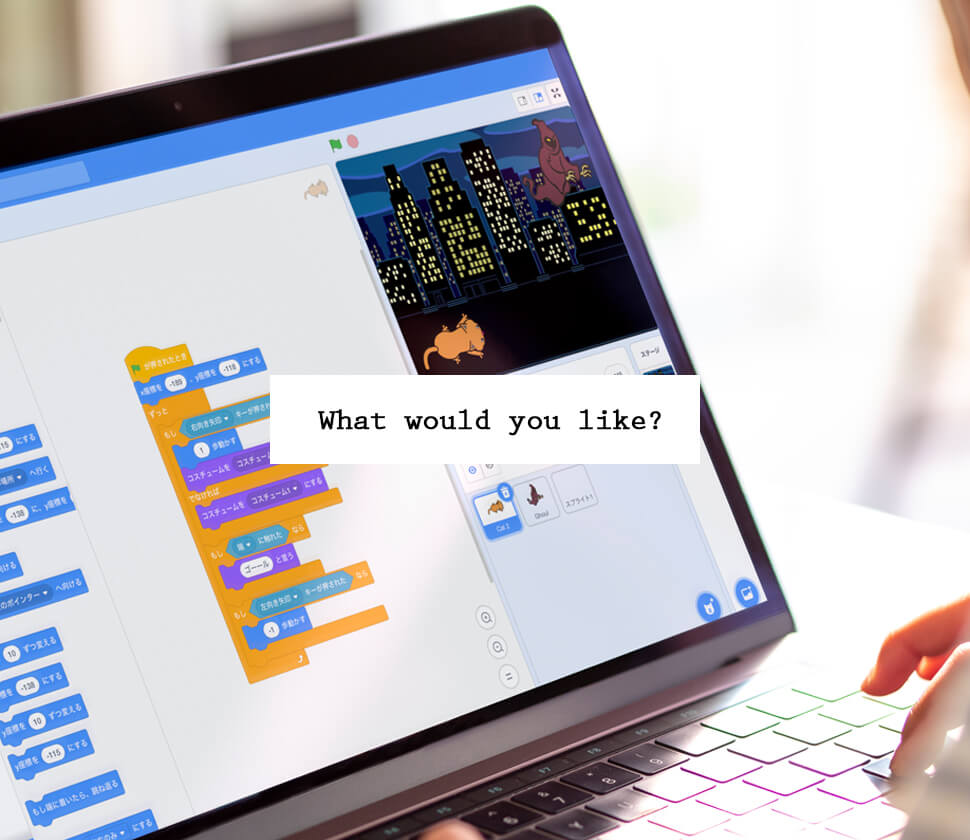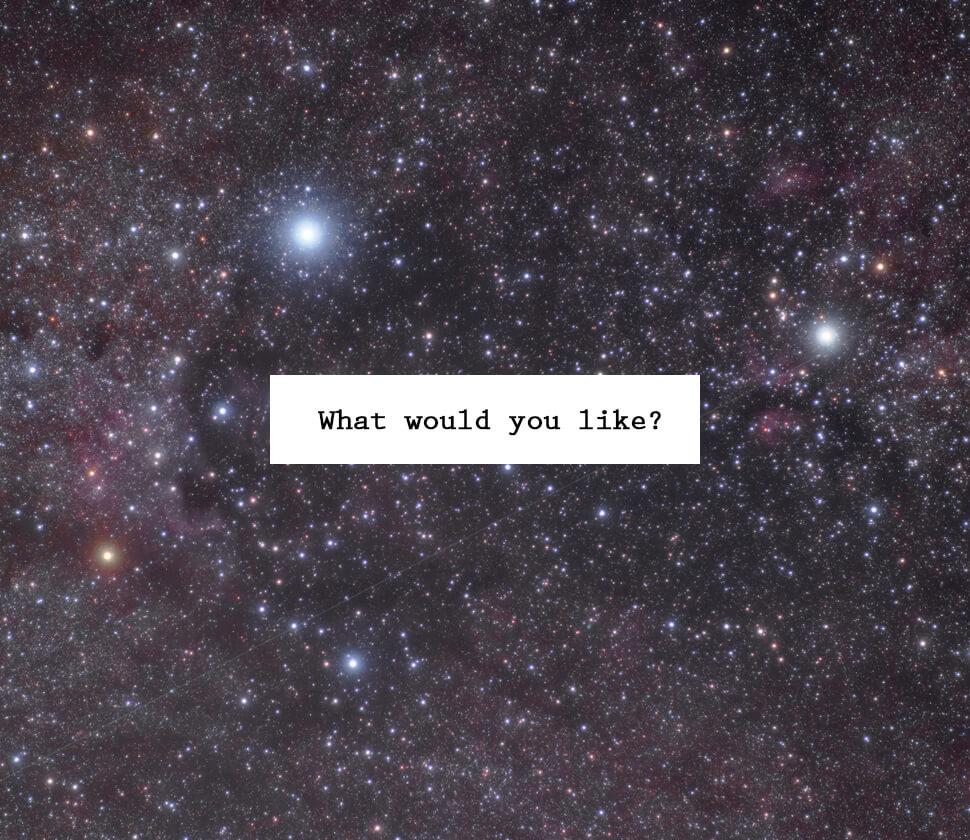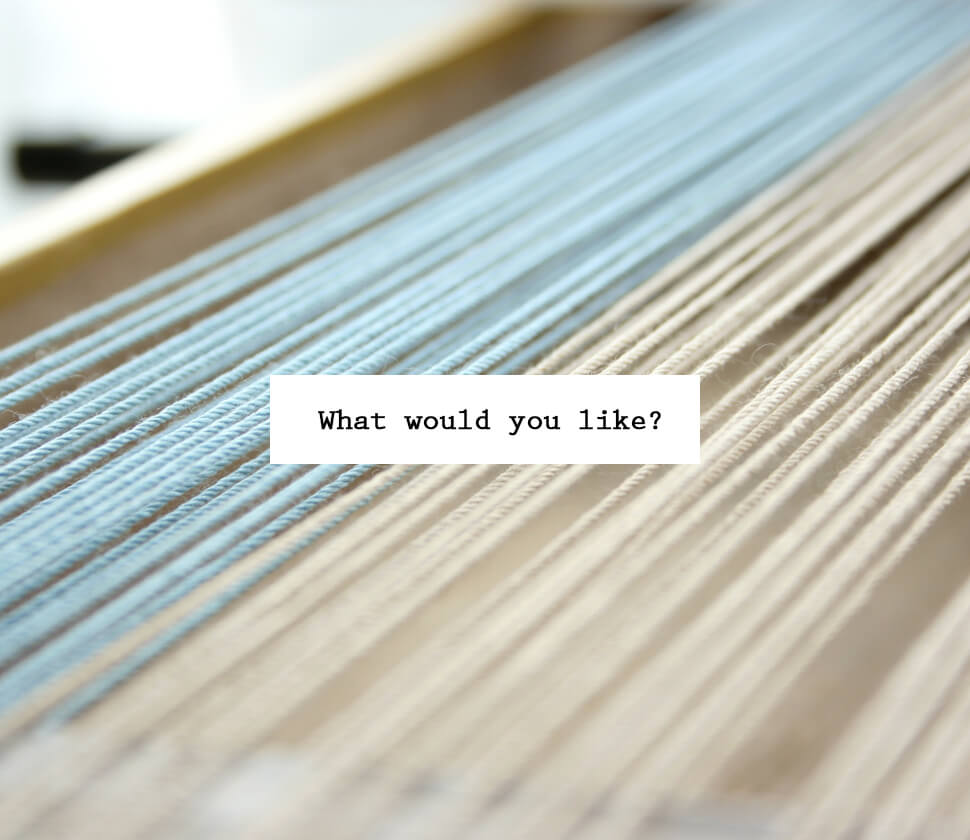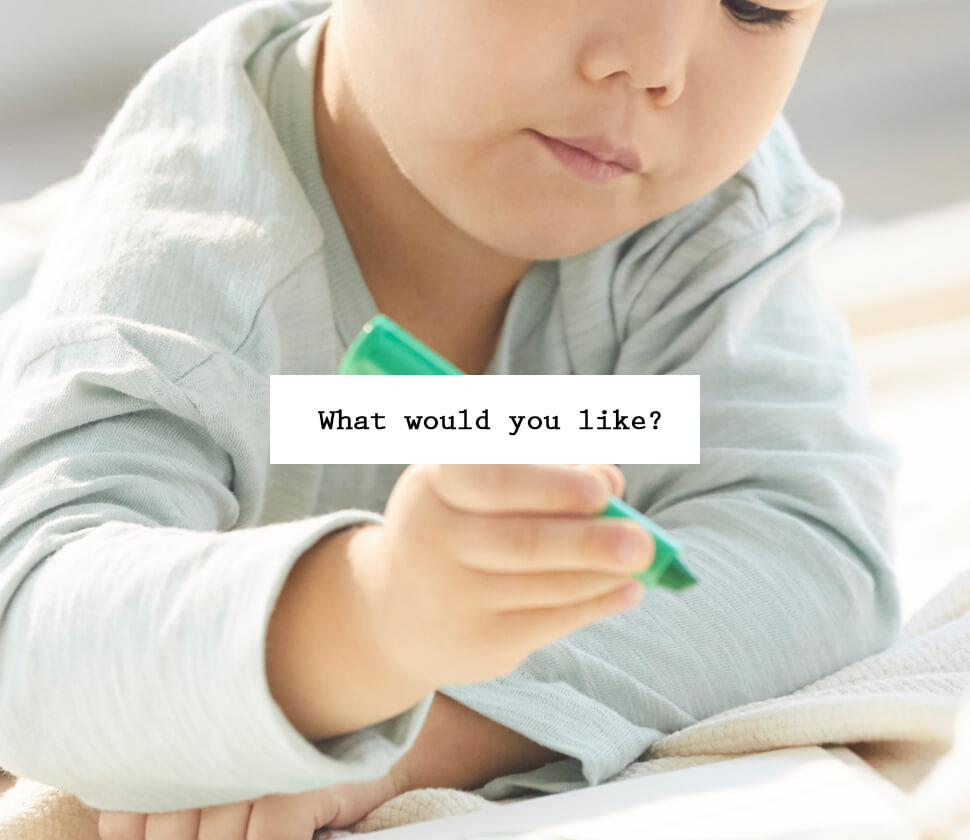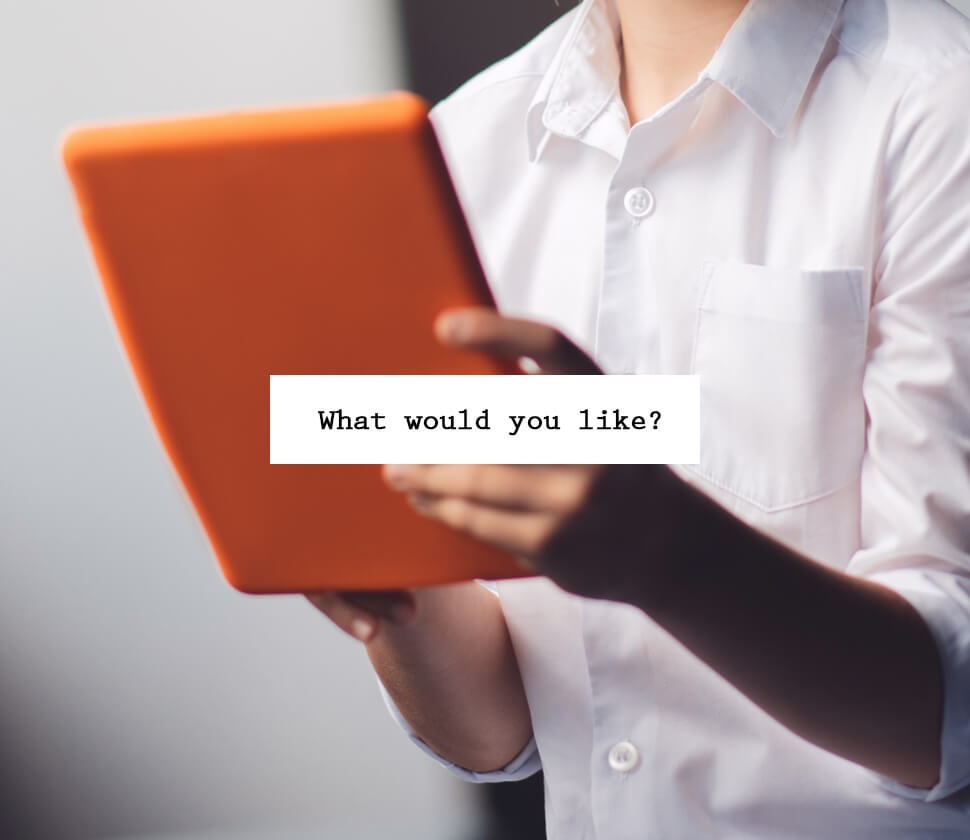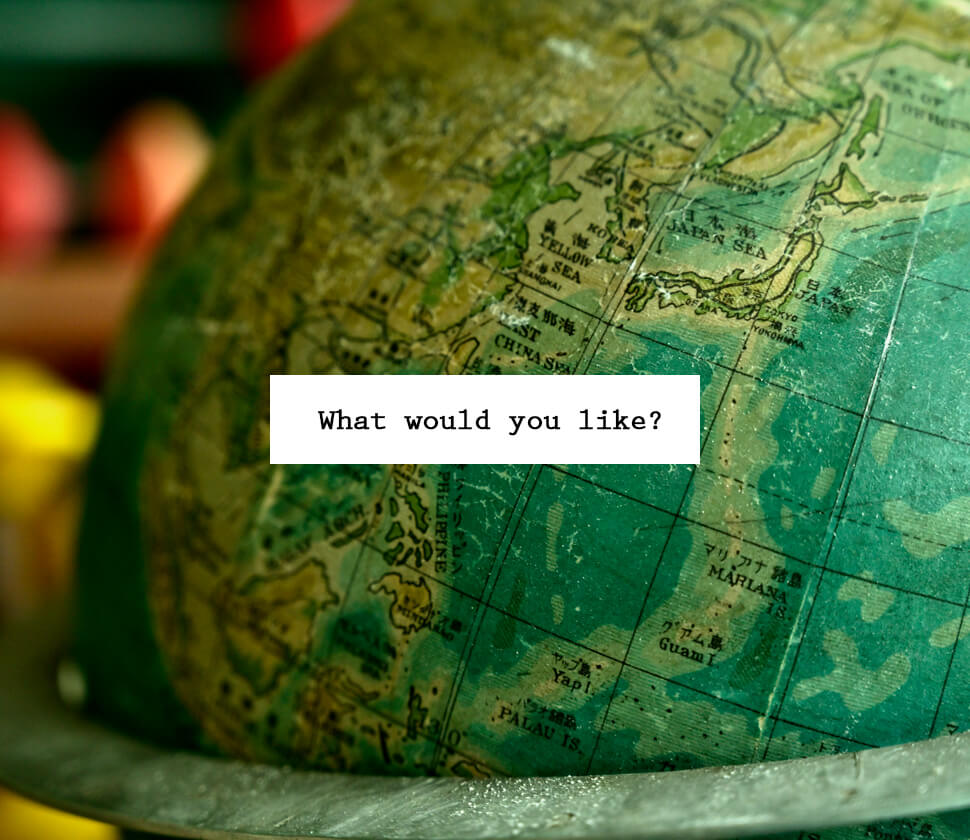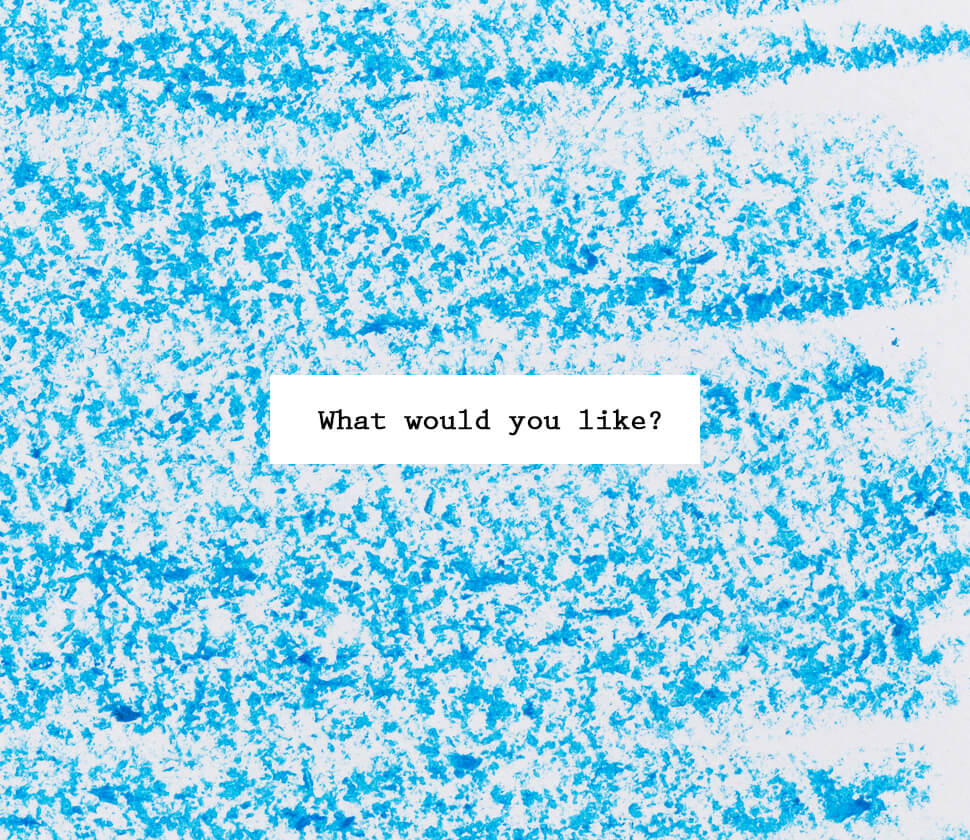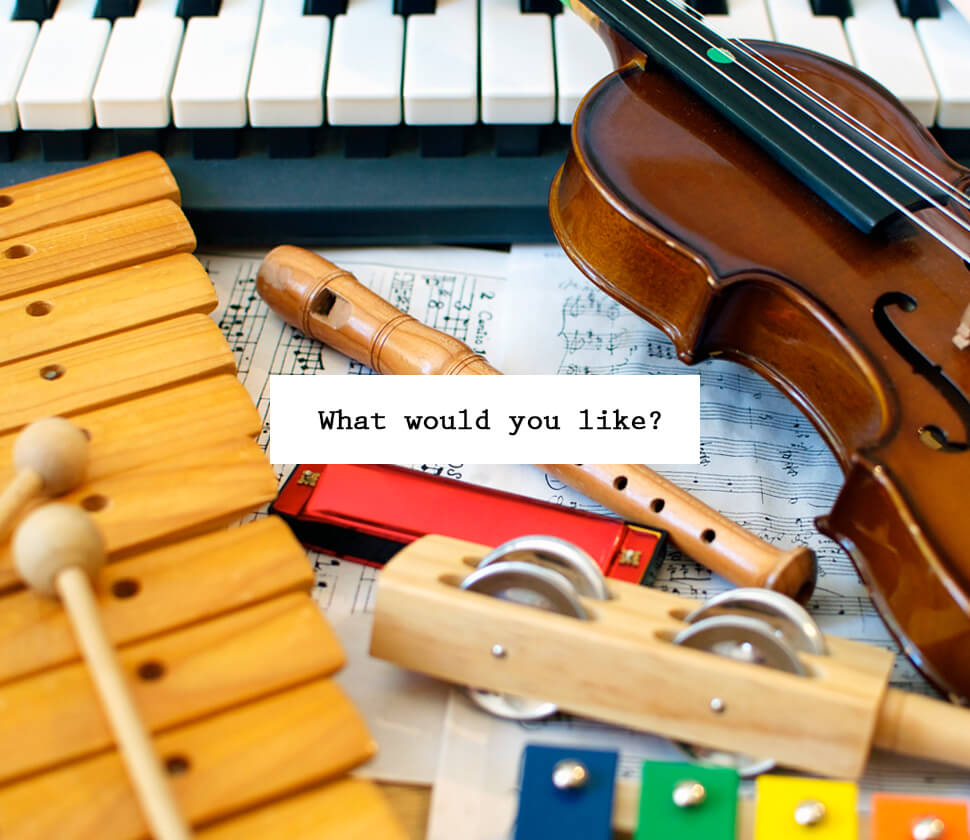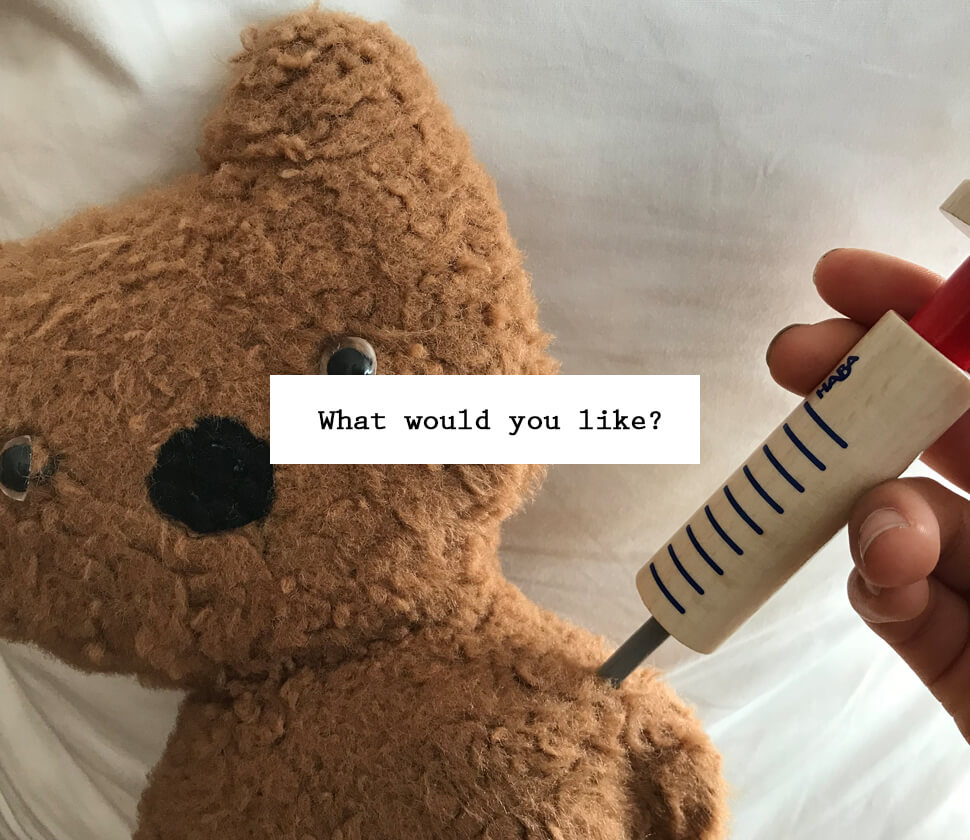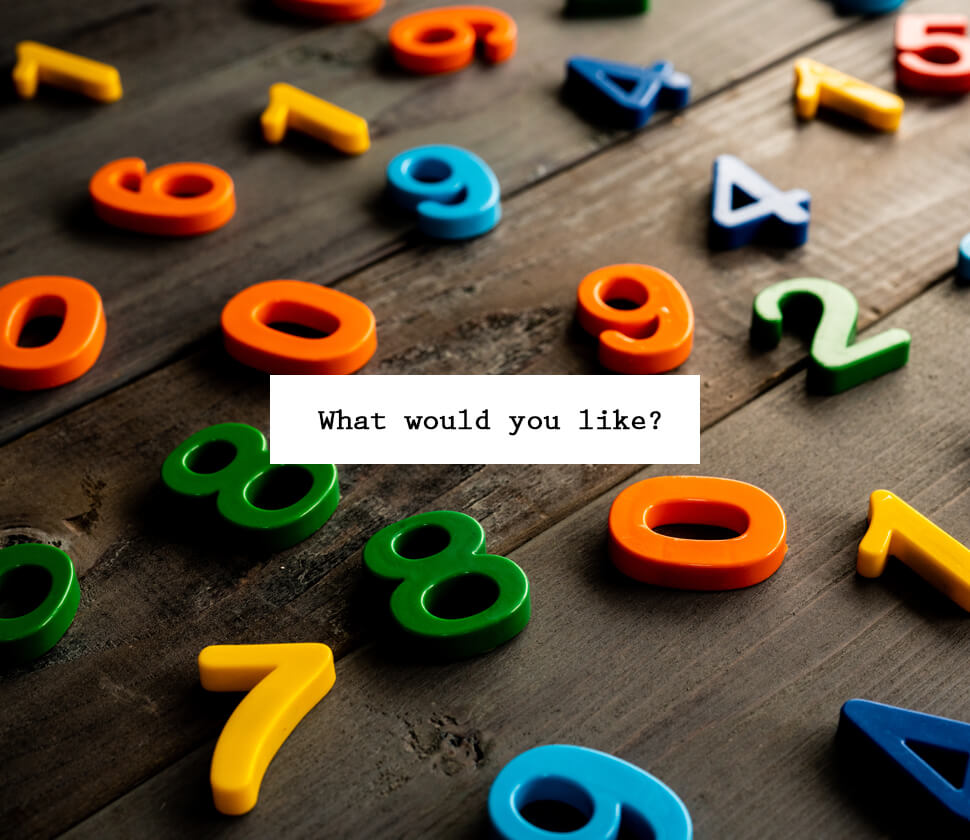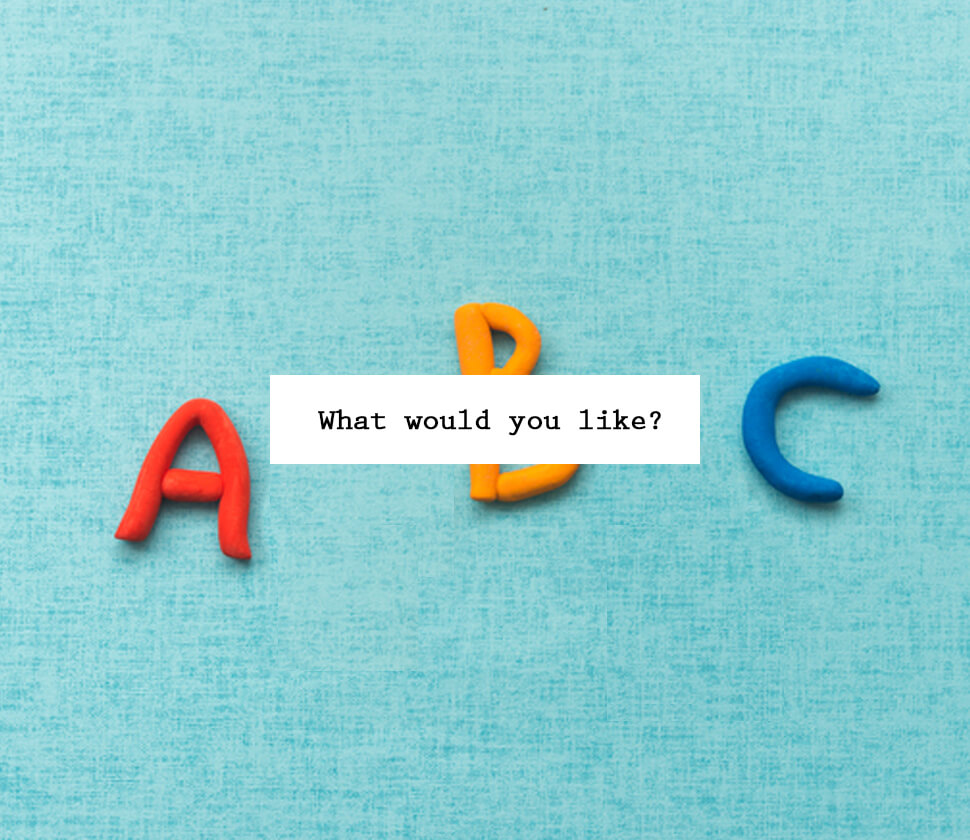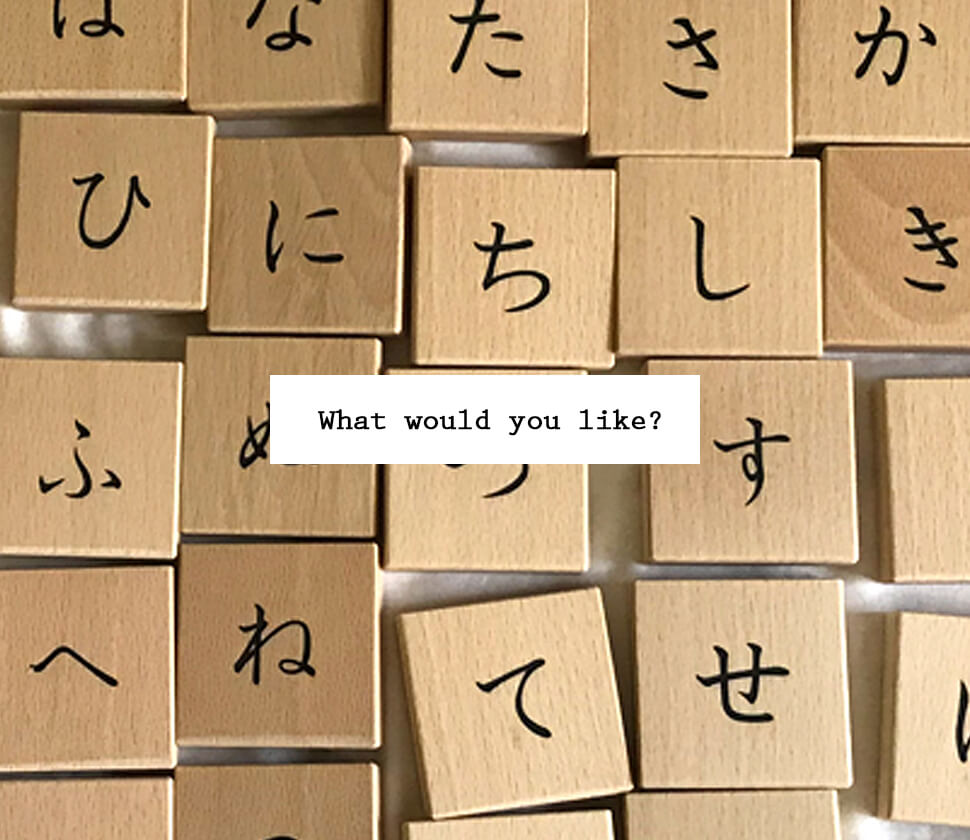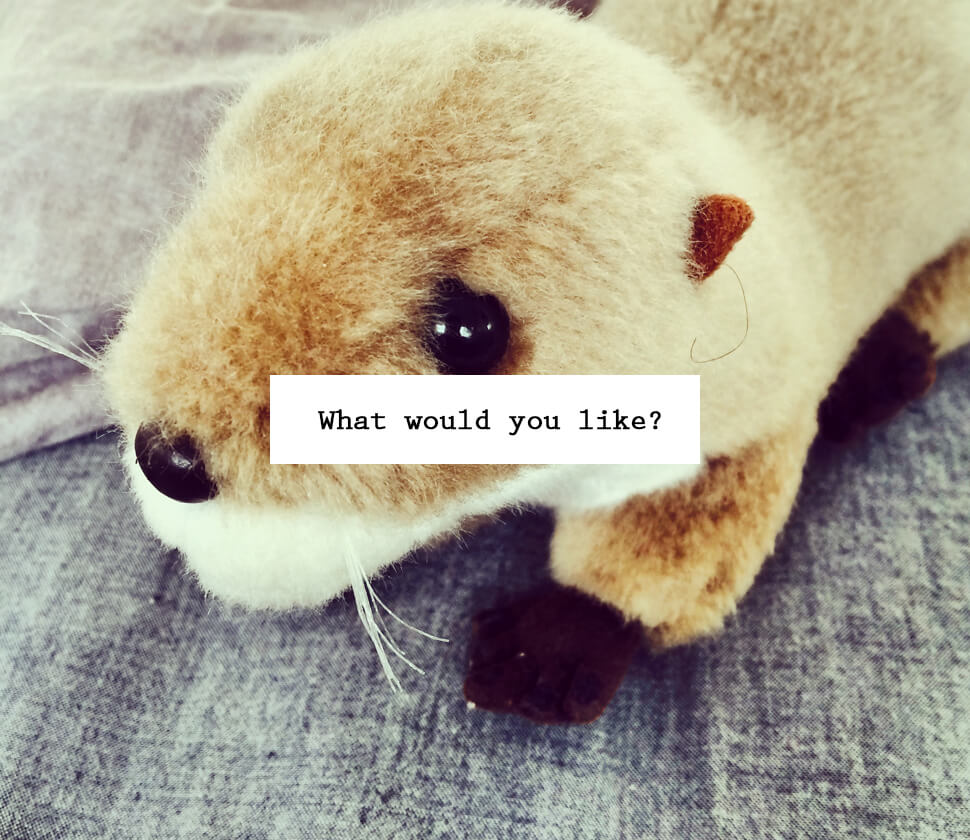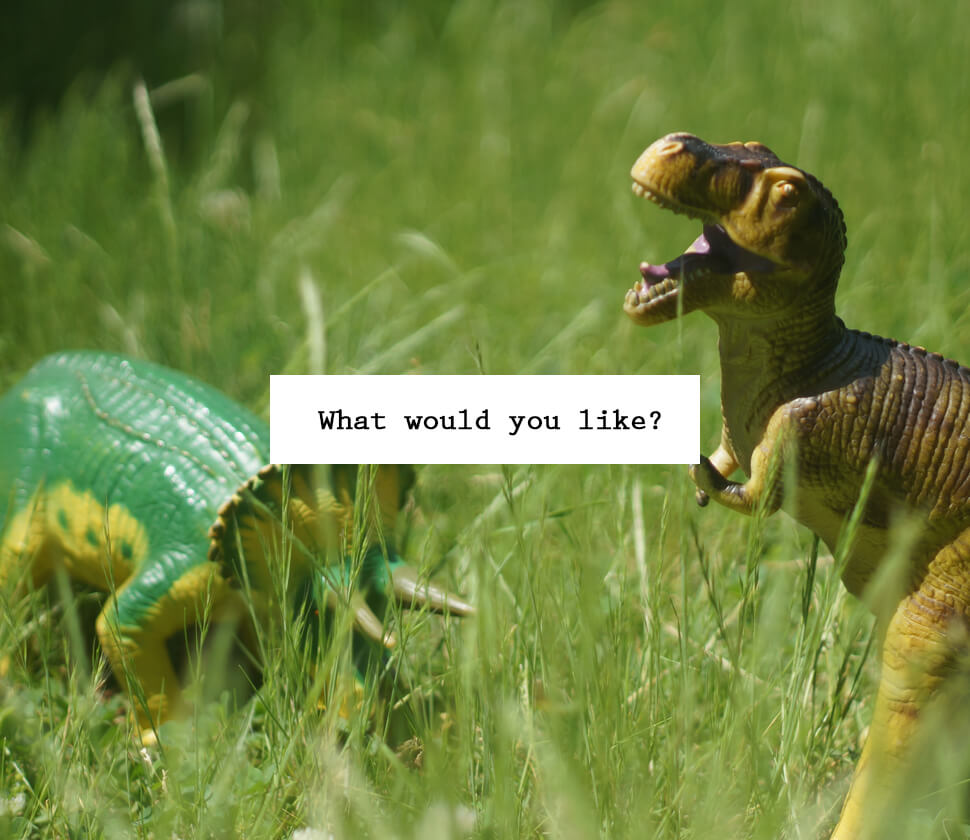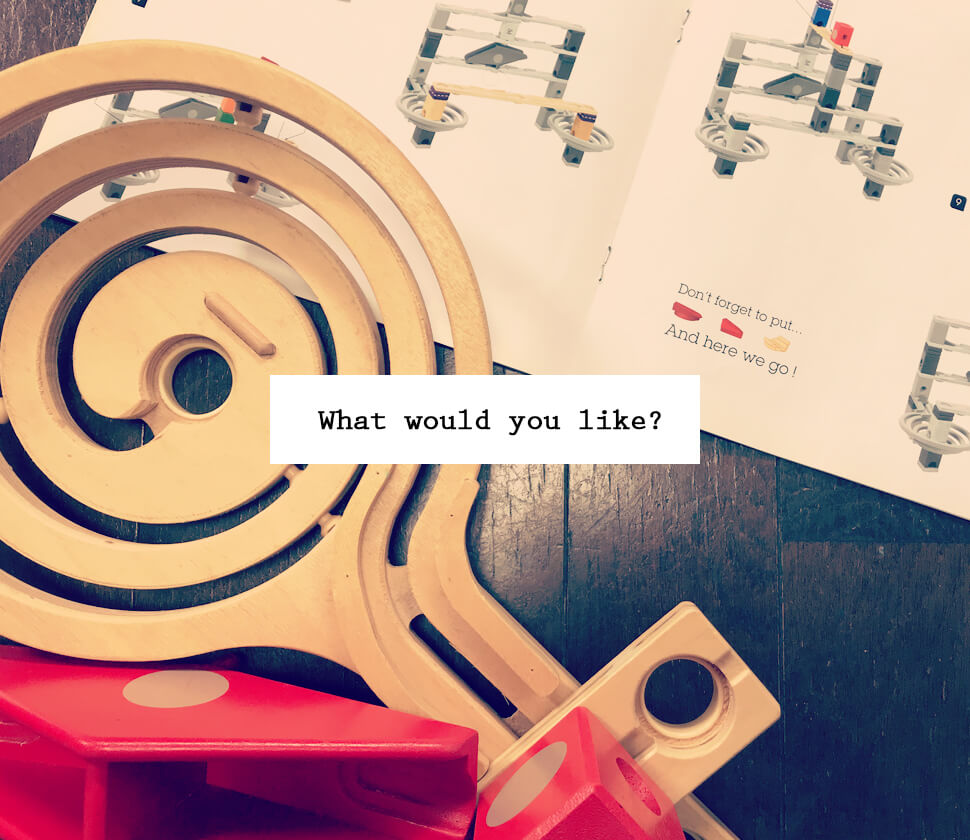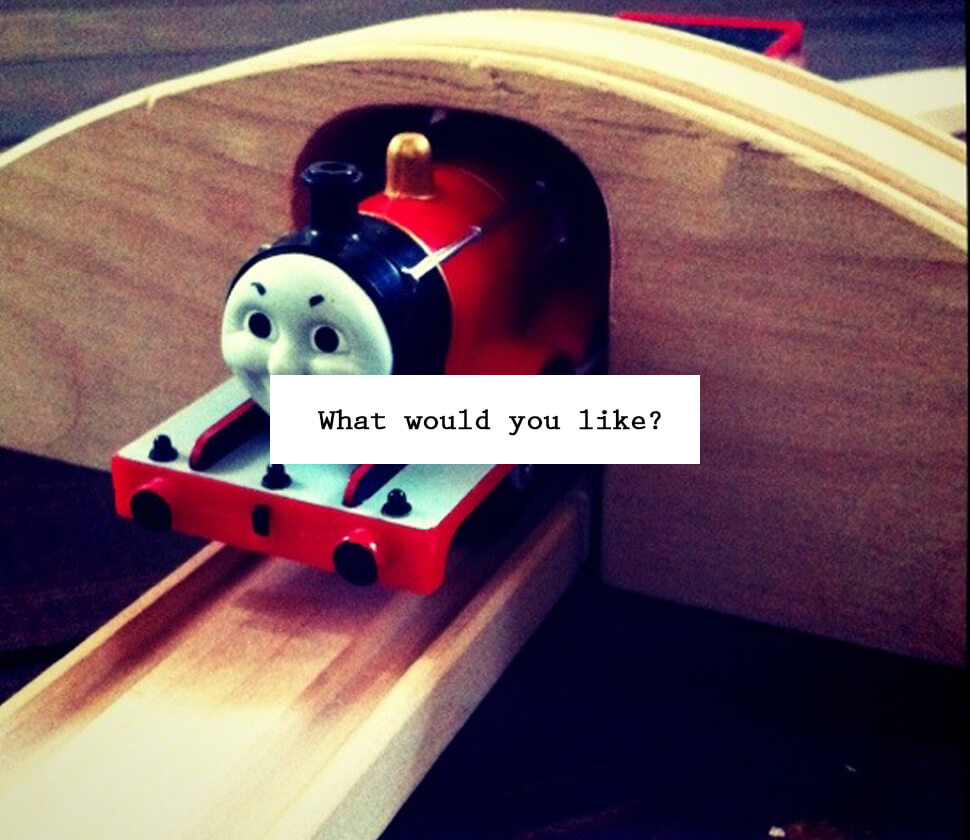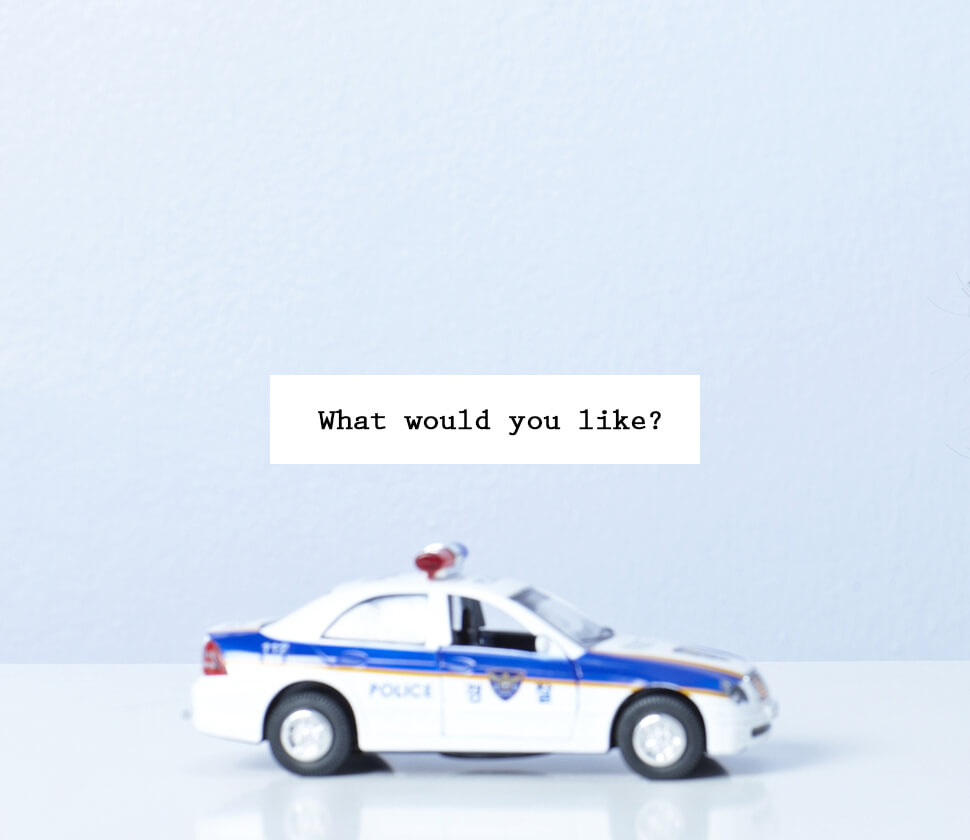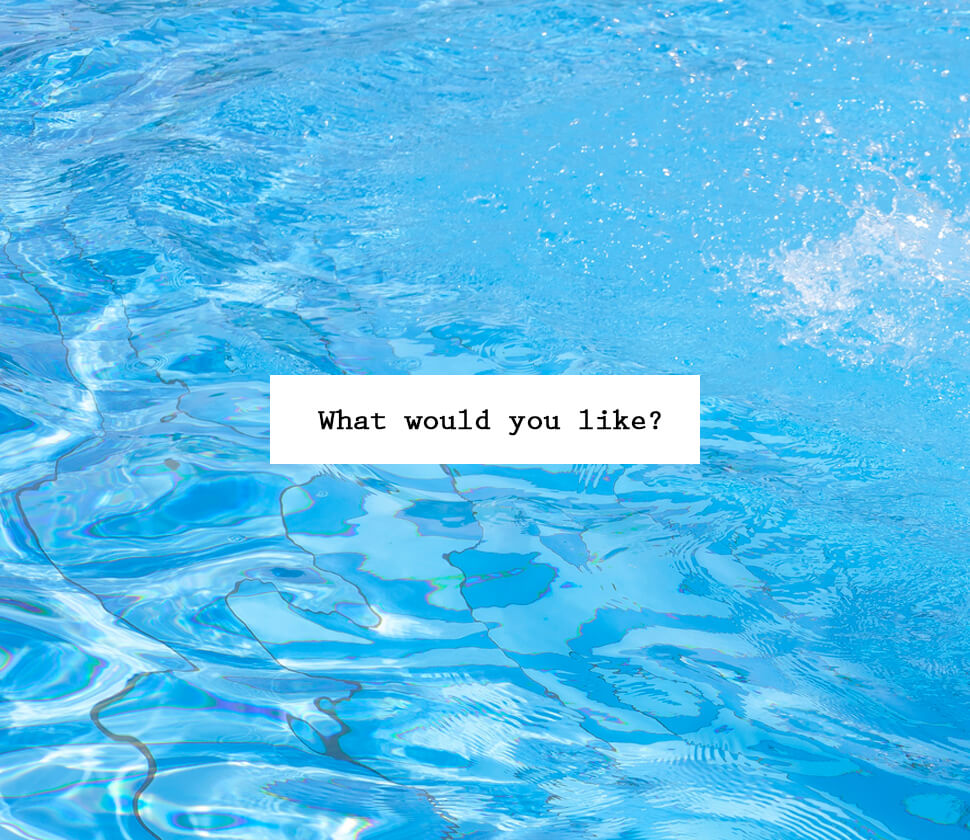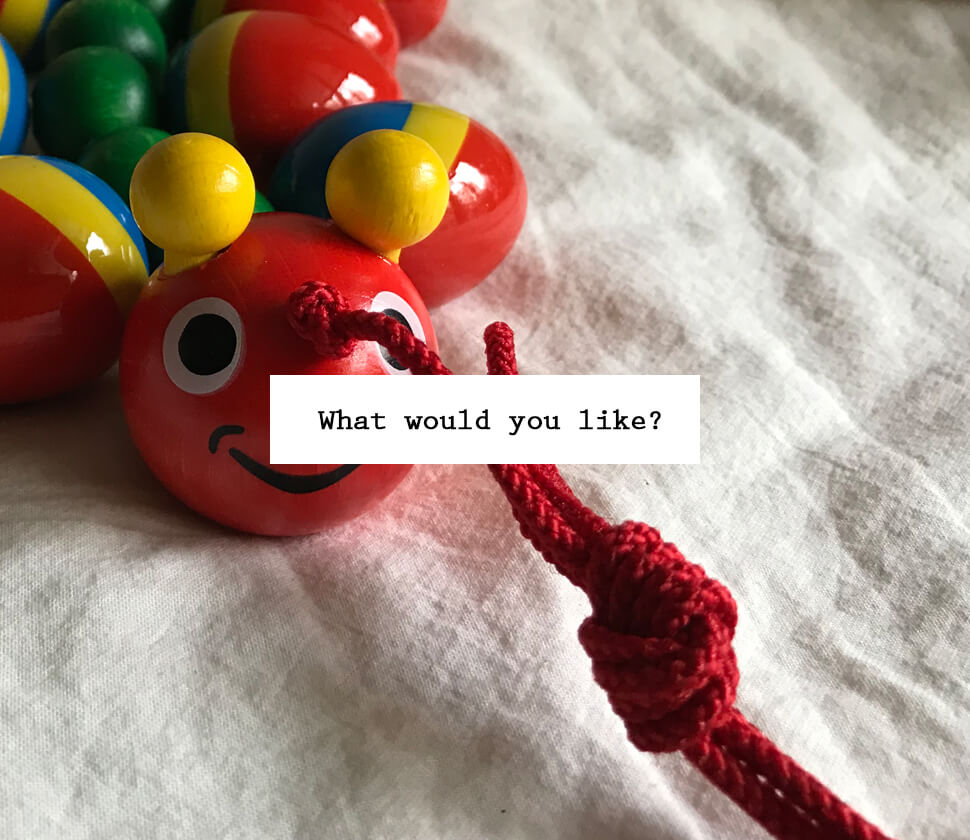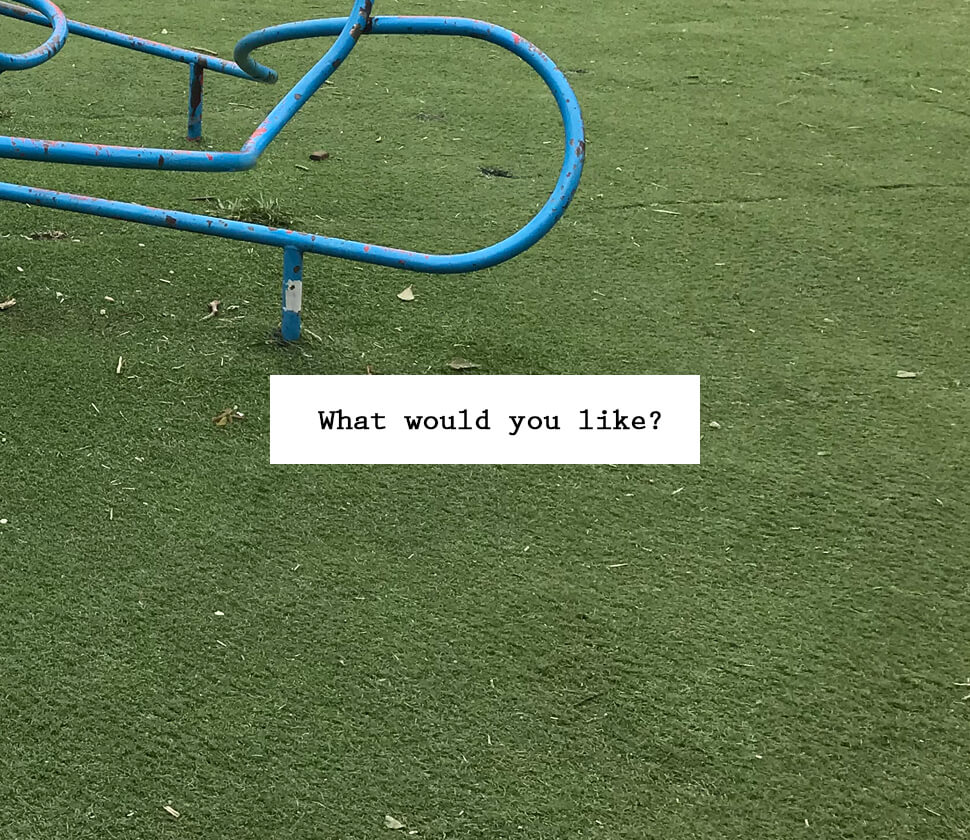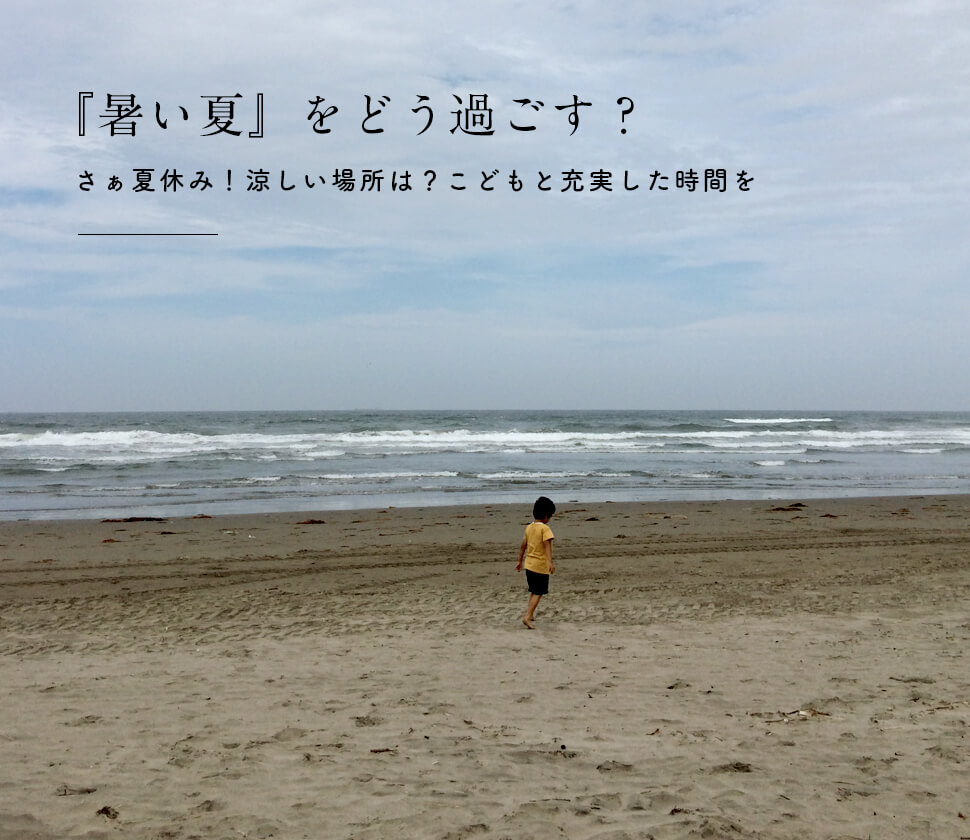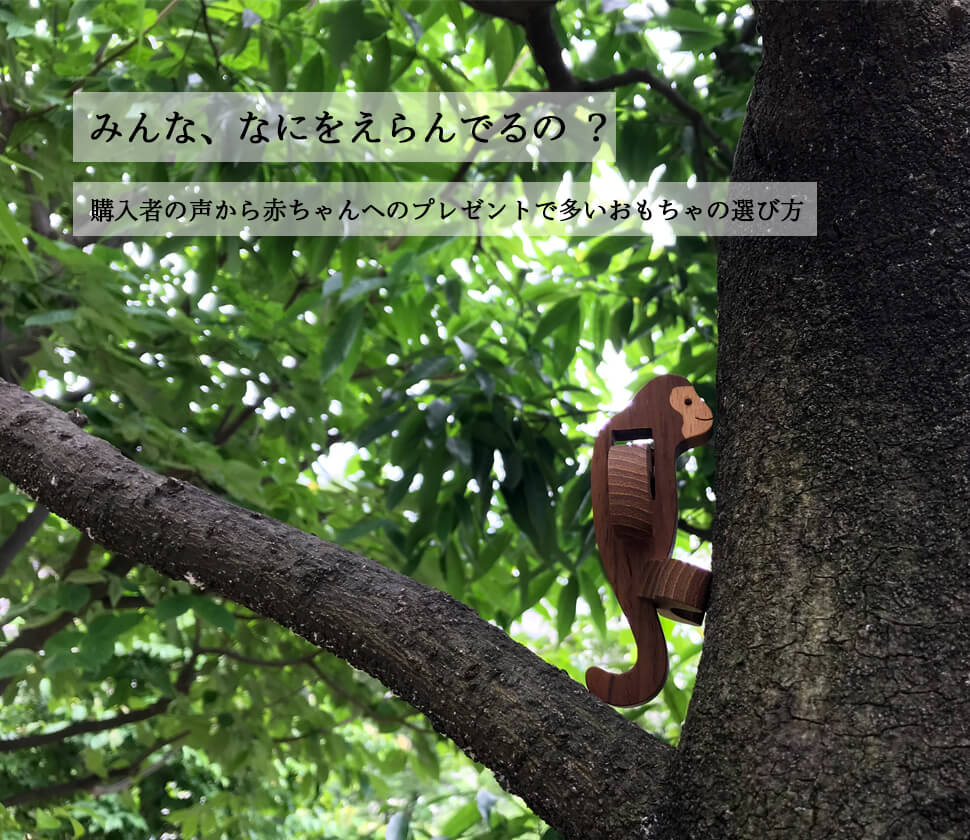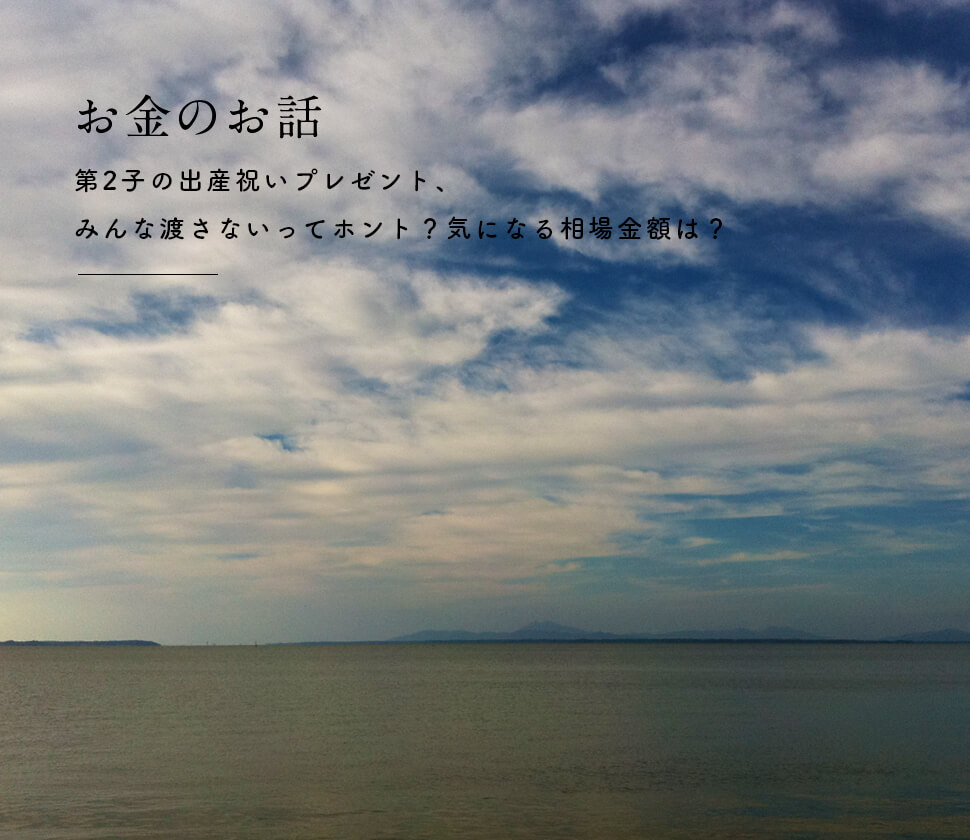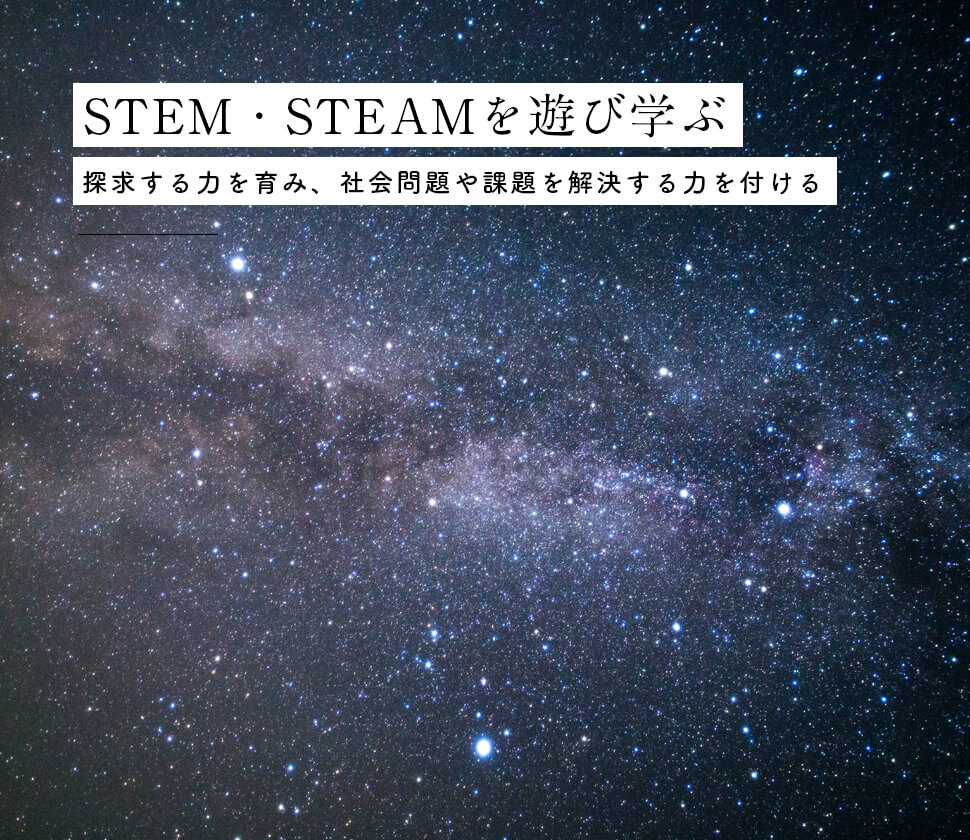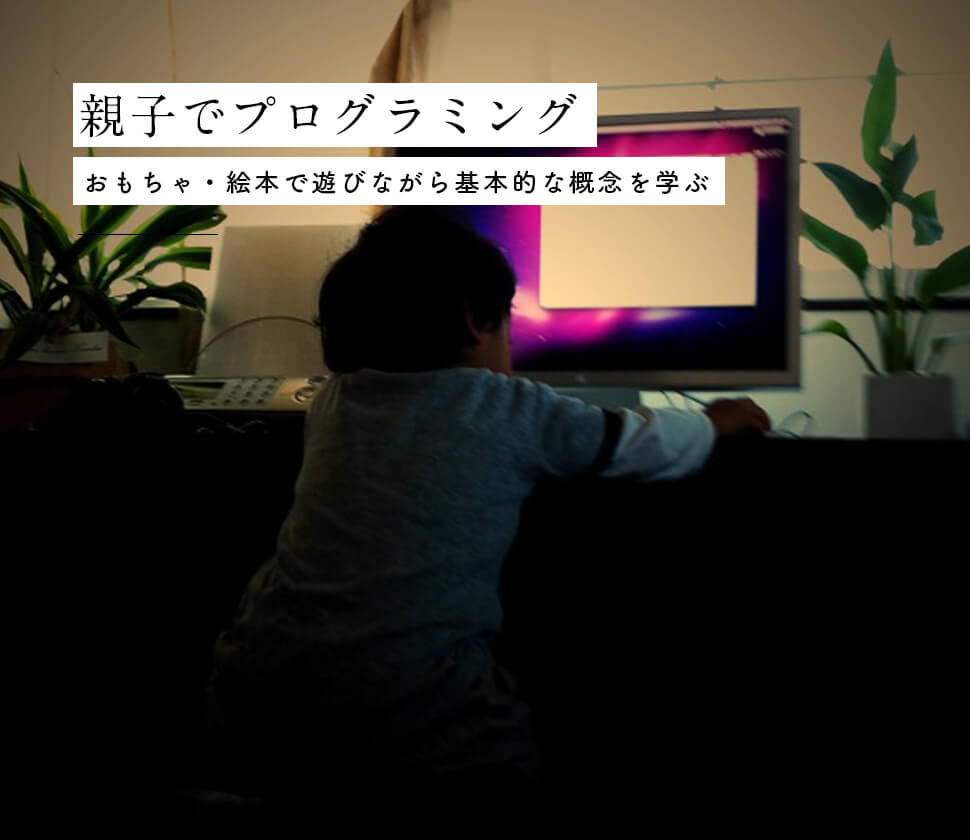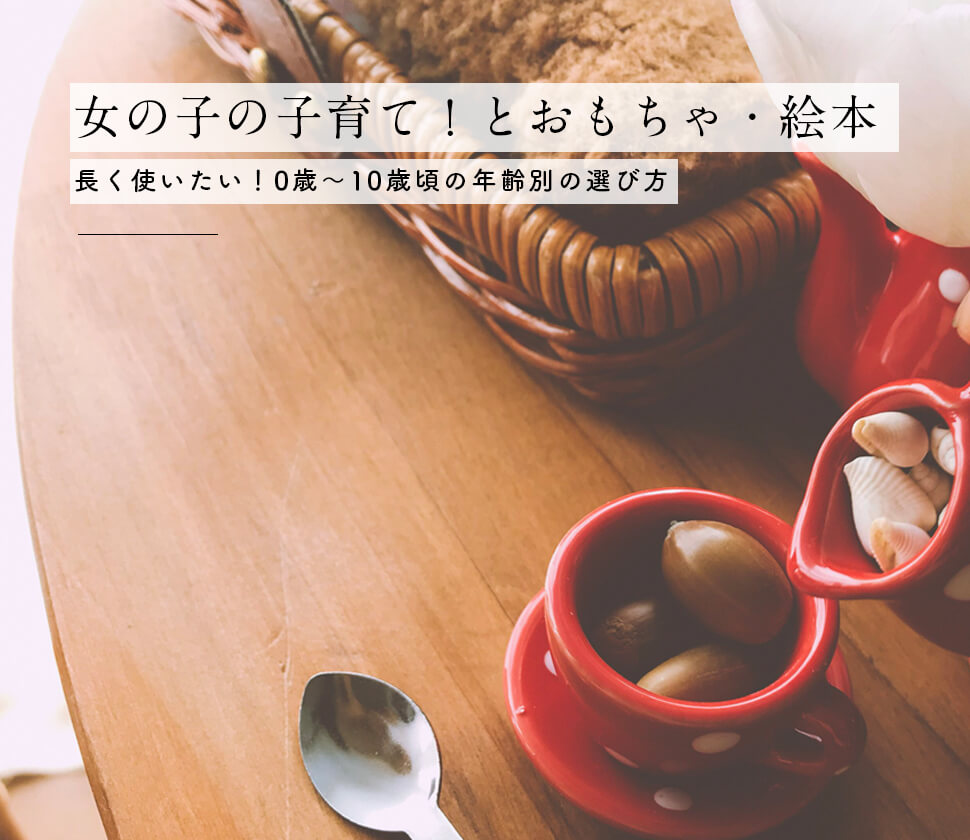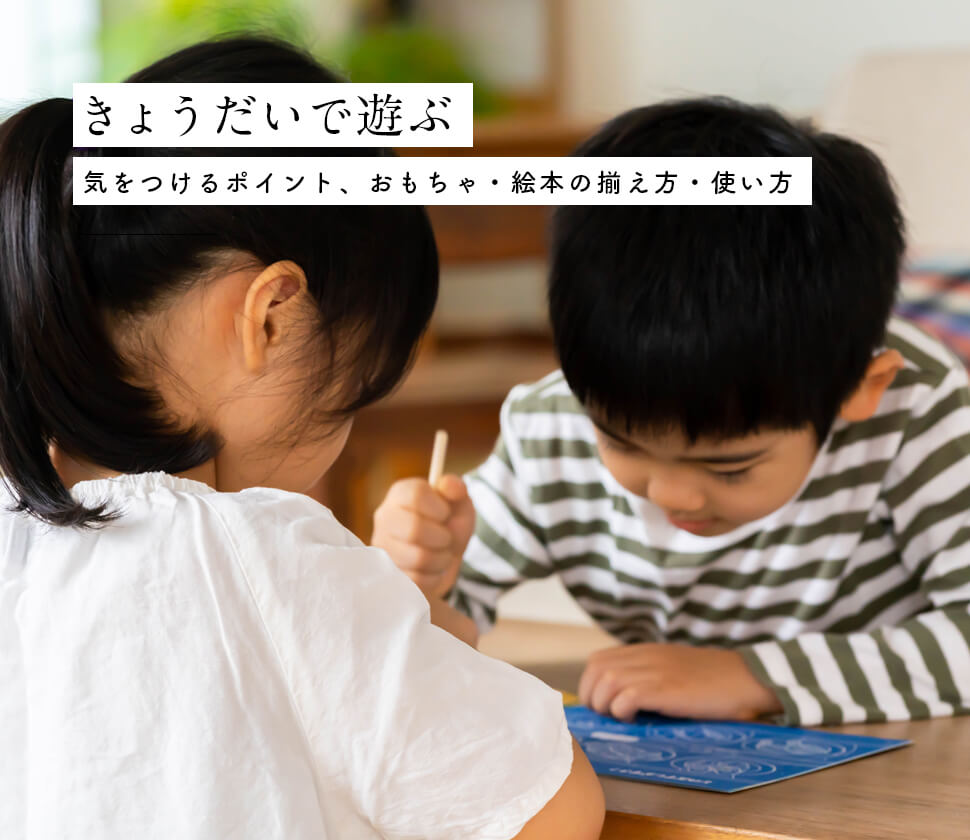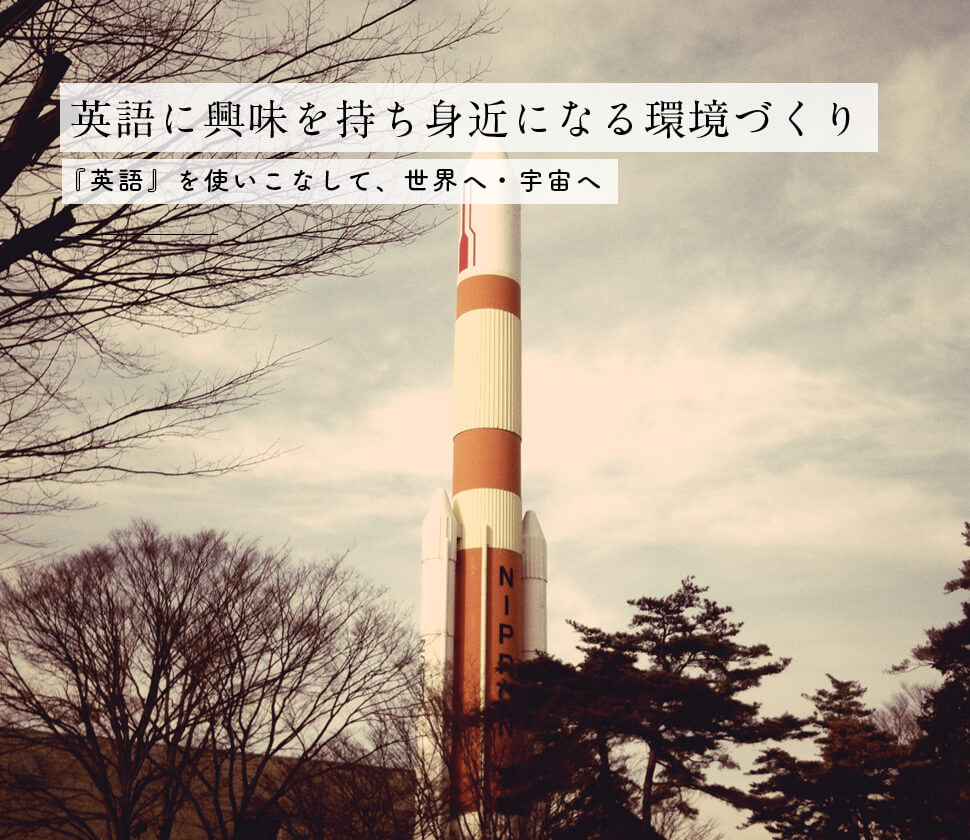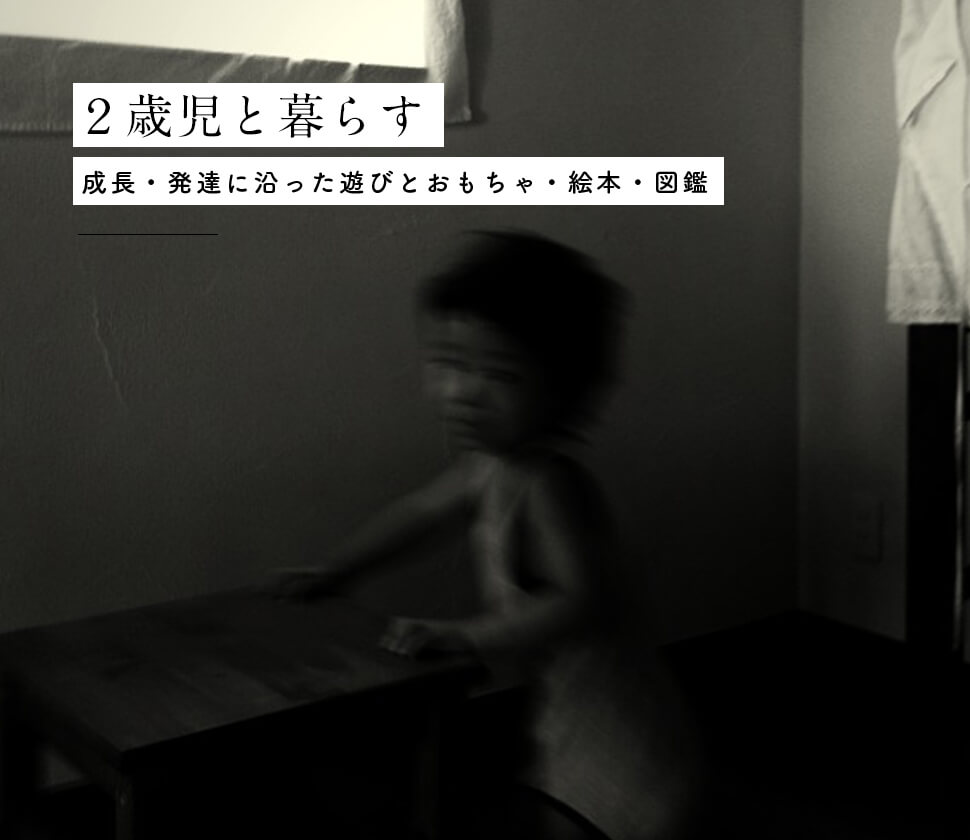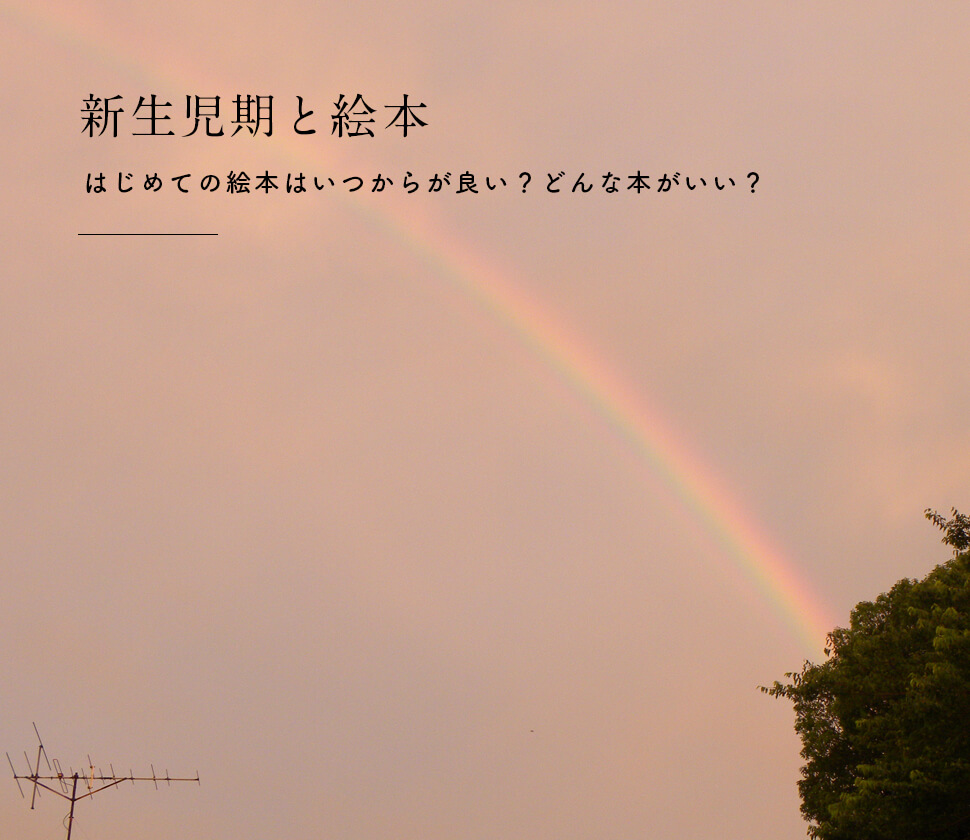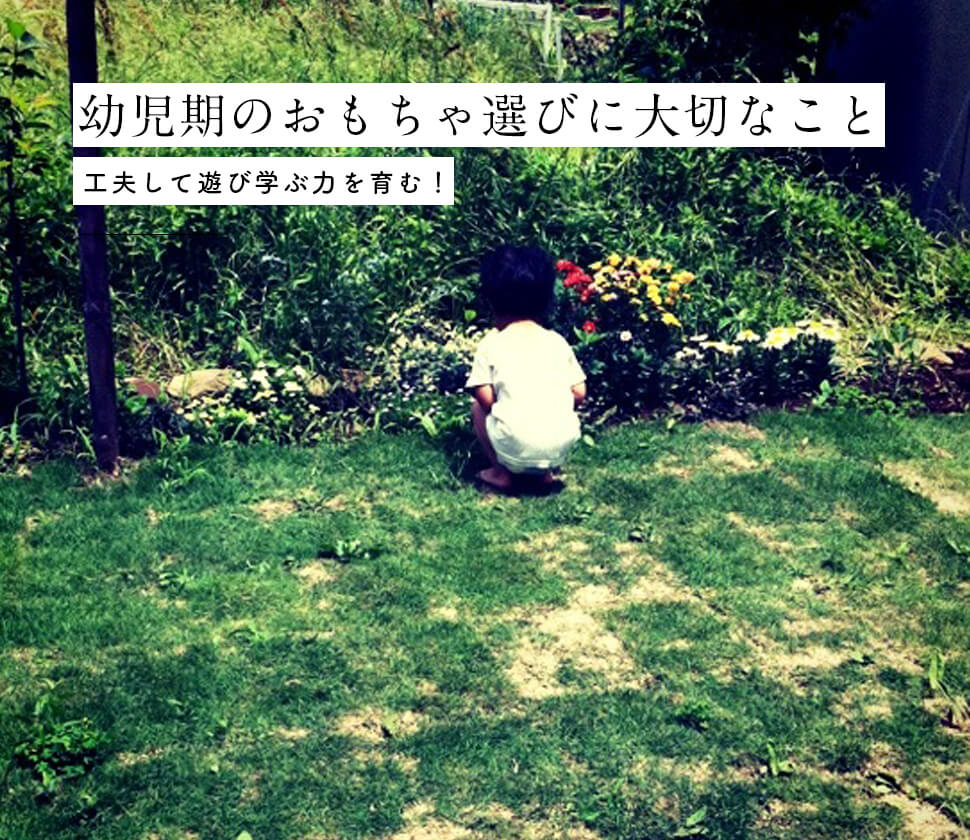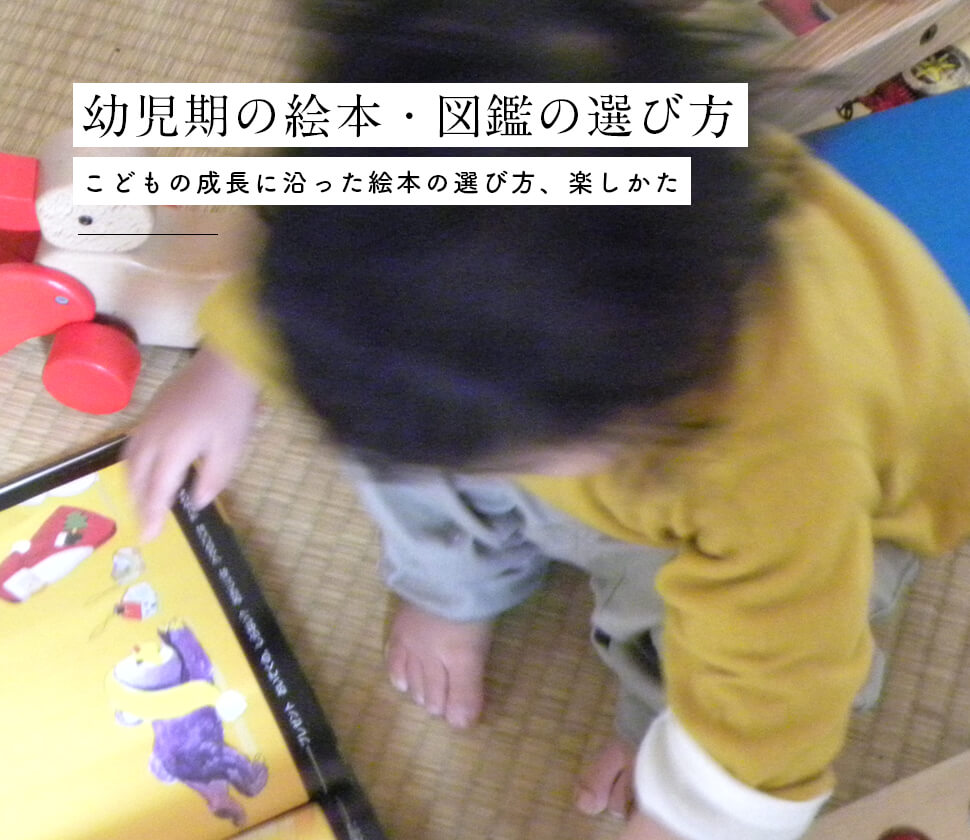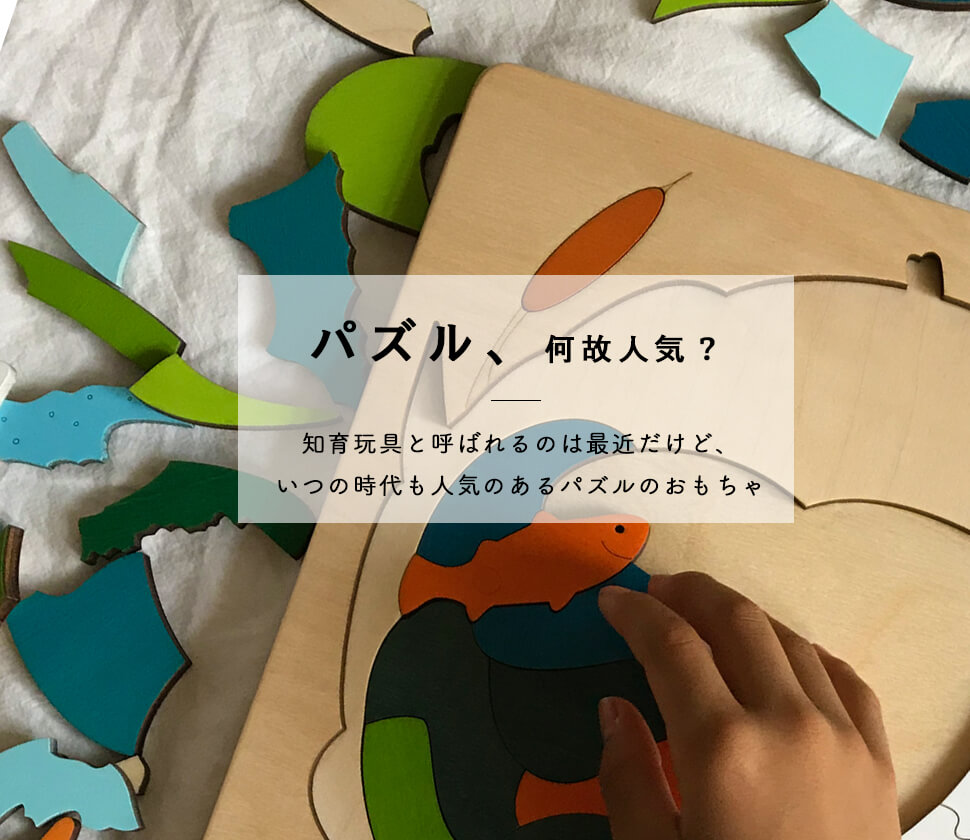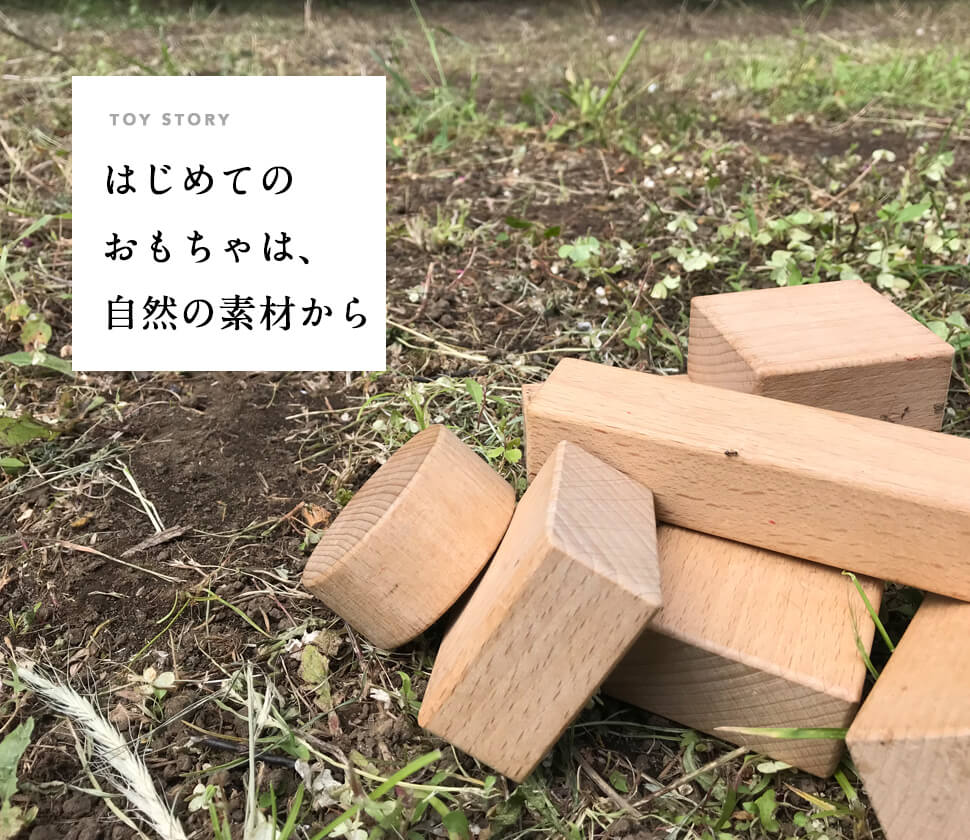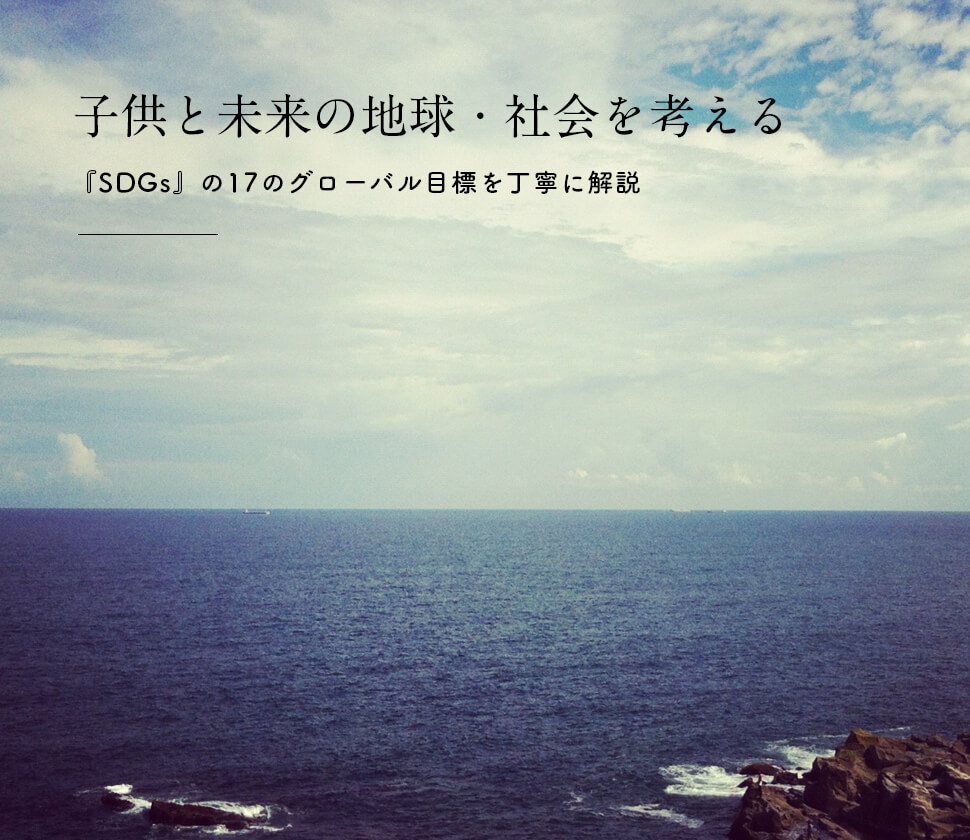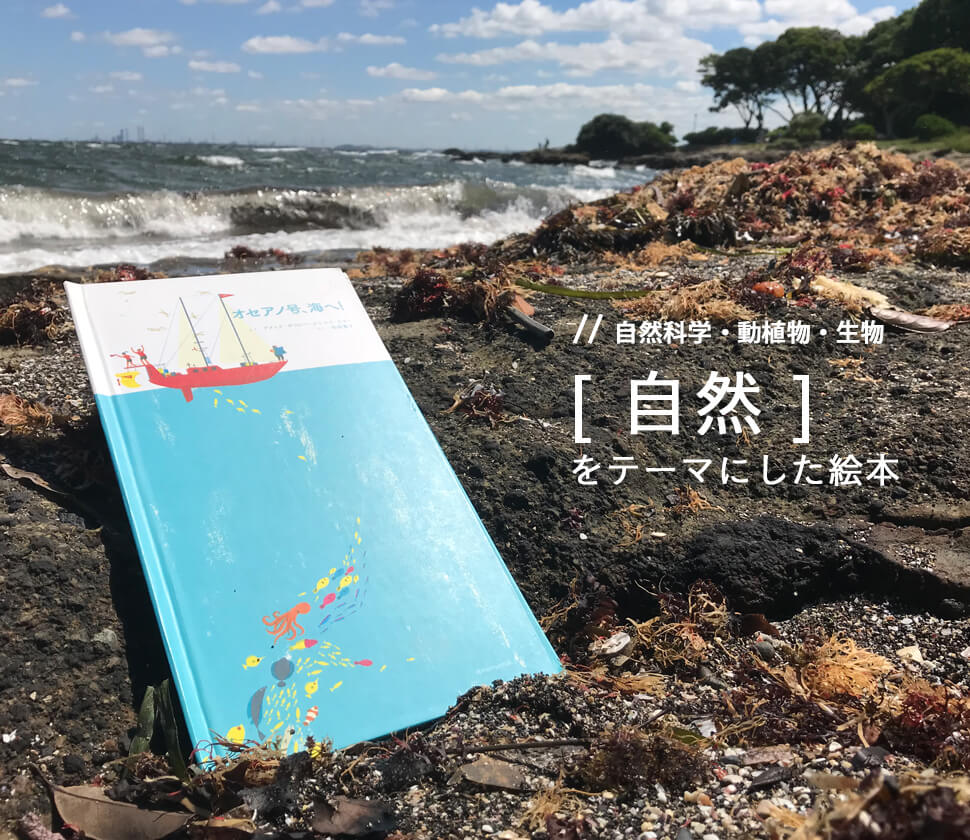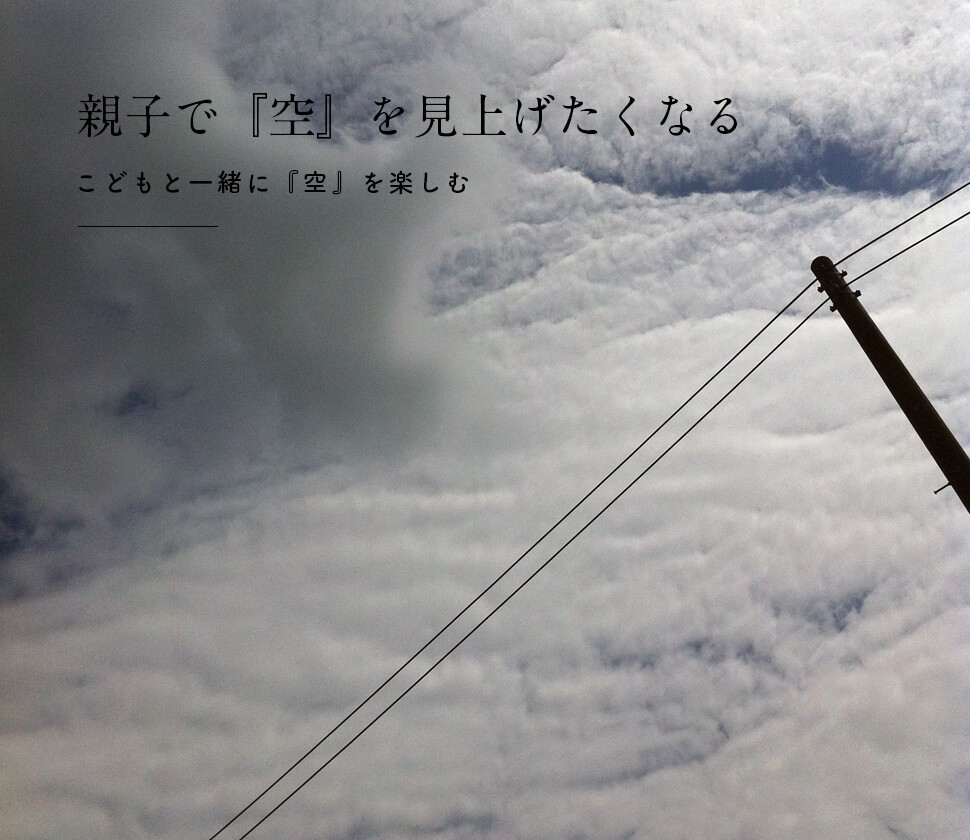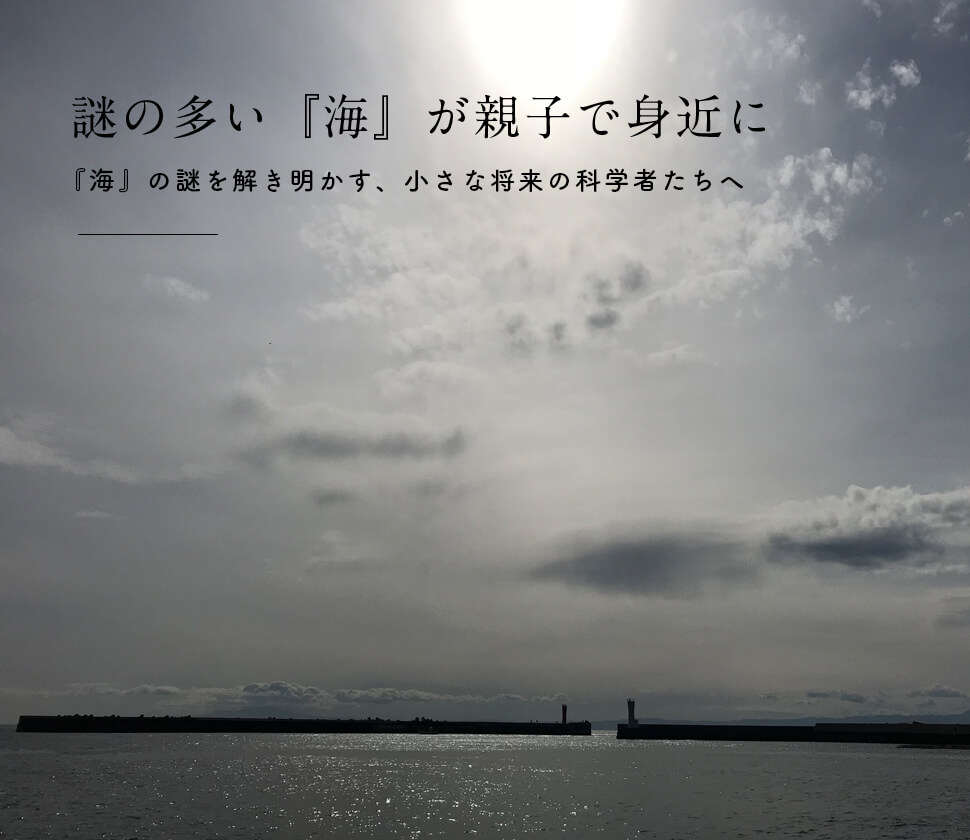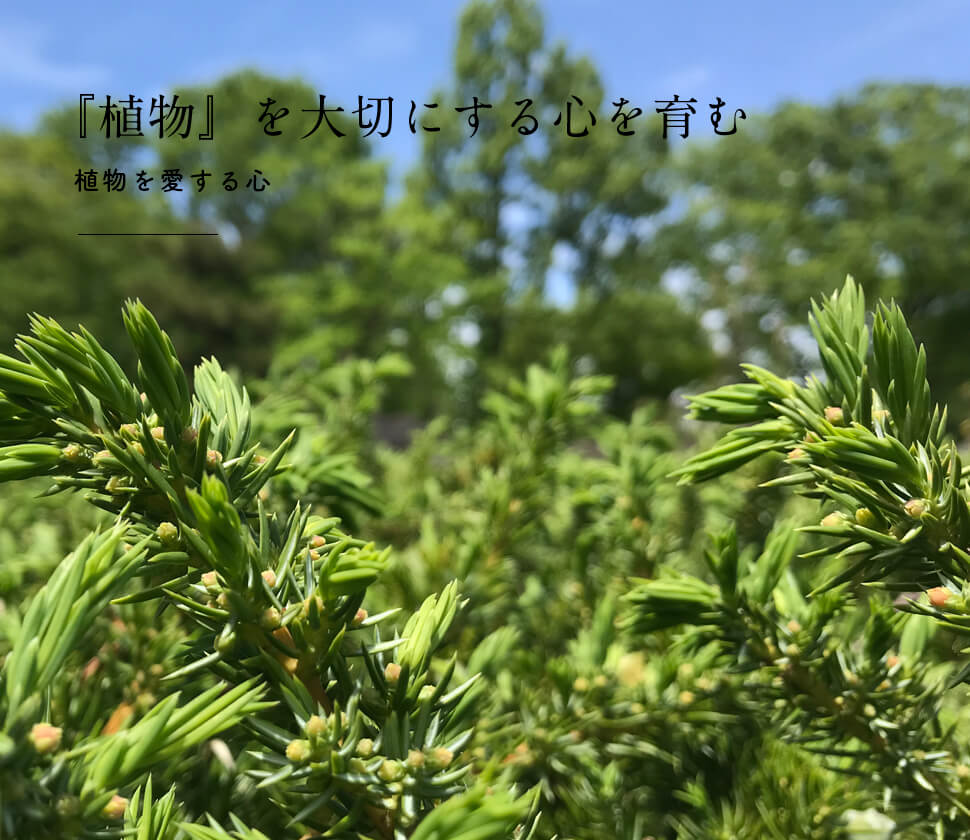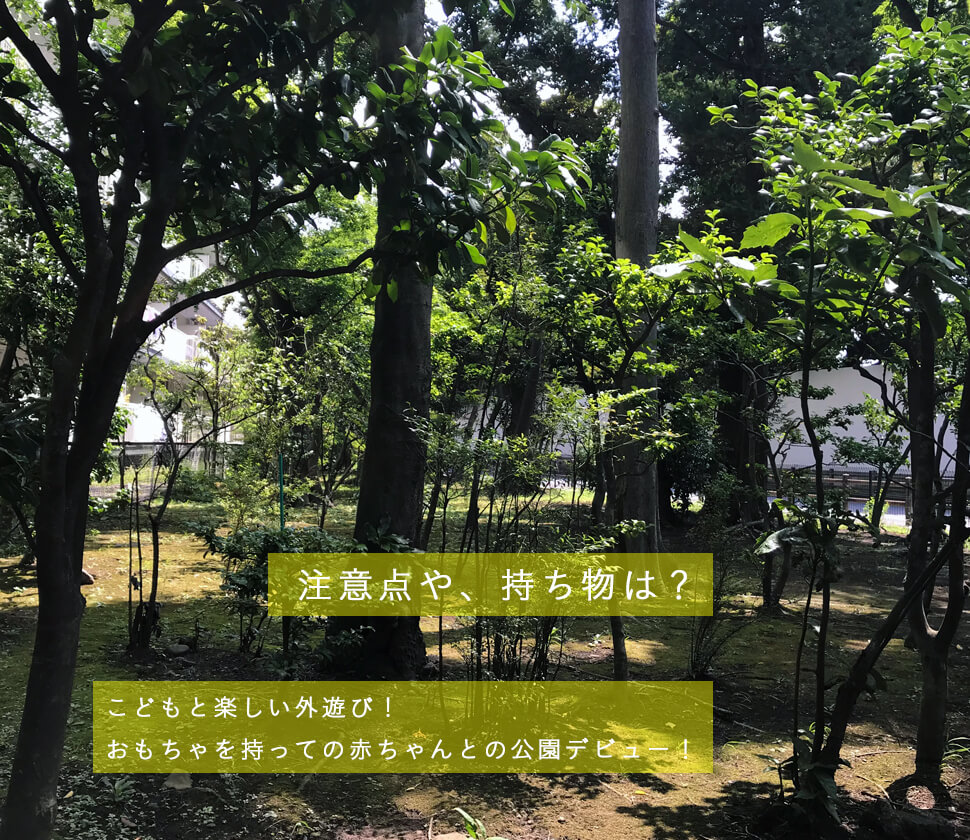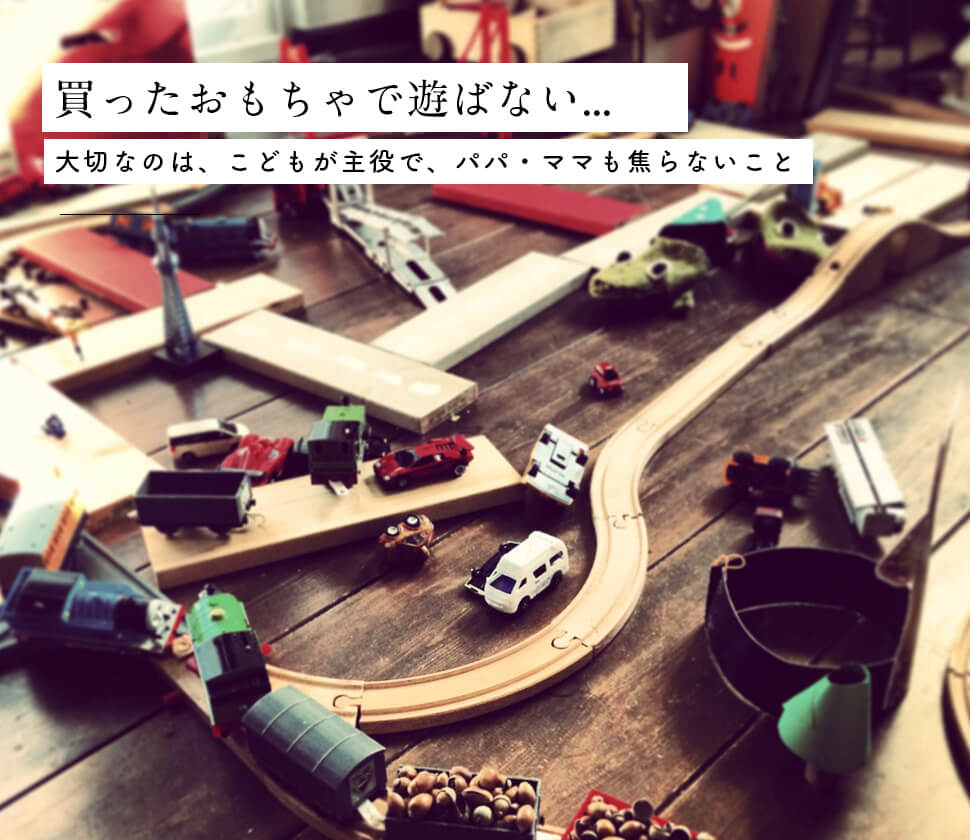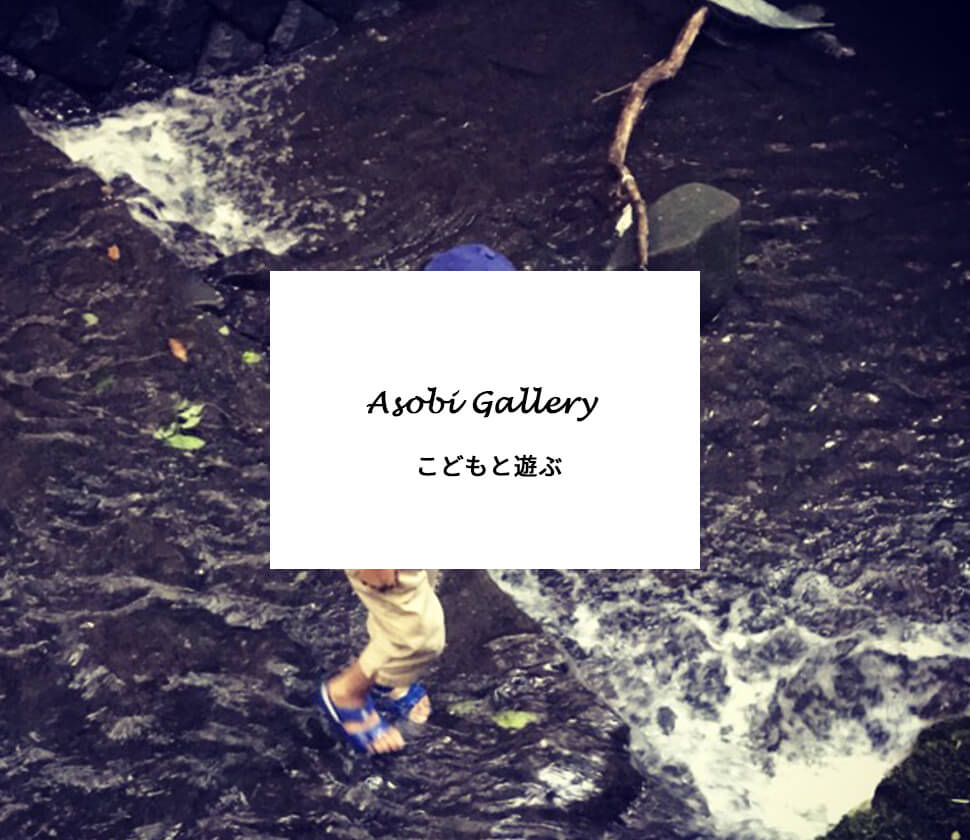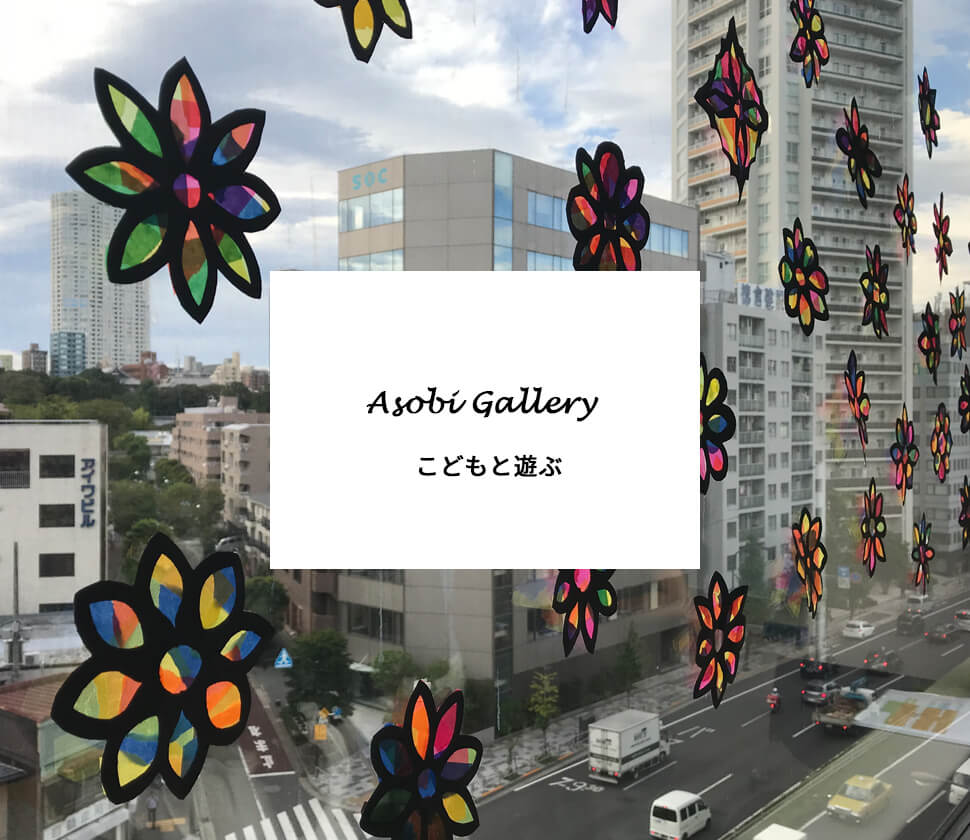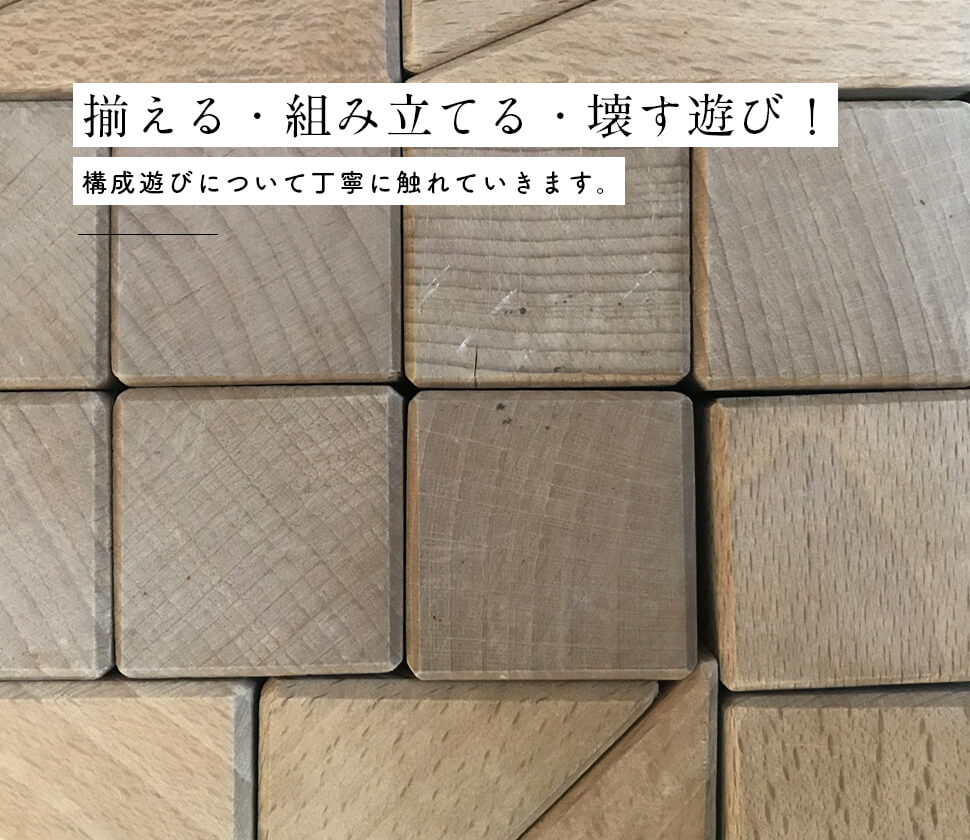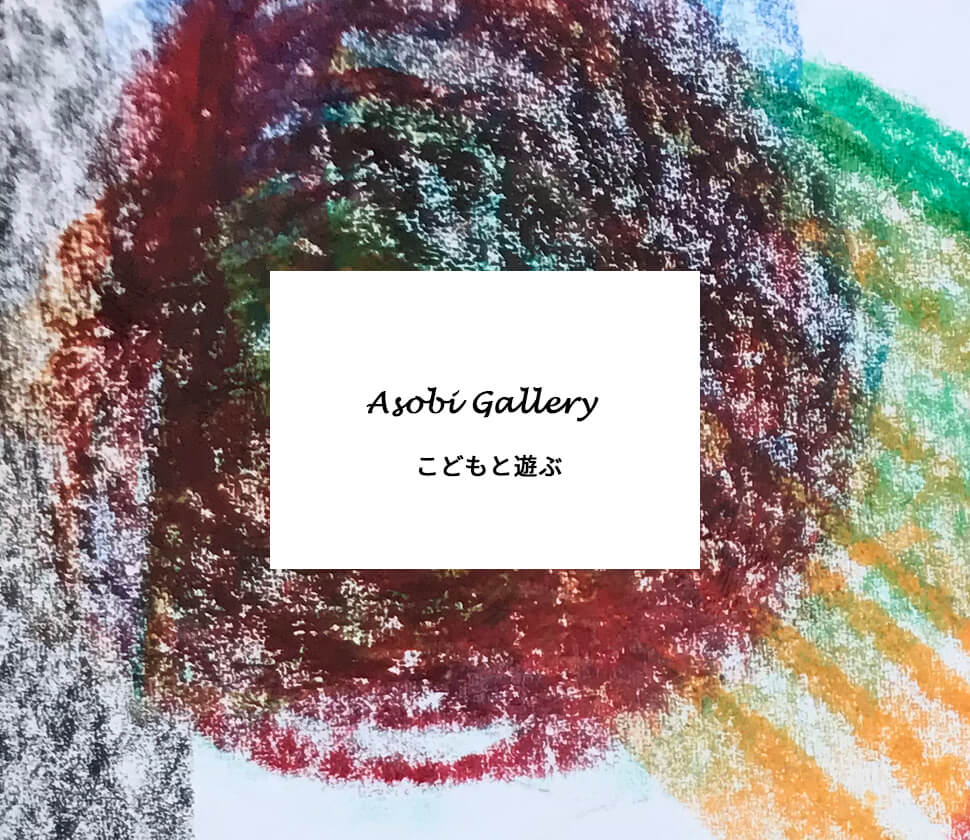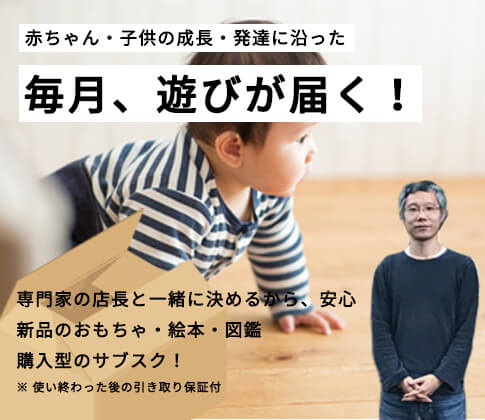読み物
最終更新日:2020年6月2日
絵・写真・文:いろや商店の編集室
れんさいプロジェクト:いろやのこと
【ワンオペ育児】夫の『育児参加』じゃ解決しない!父親は育児から逃げちゃダメ
こんにちは。いろや商店の店長のおおま(@iroyaonline)です。
ここ「いろやのこと」では、まったりマイペースにいろやのあらゆる側面のおはなしをお伝えしています。
今回は『ワンオペ育児』についてです。
店長の育児の経験から、父親としてどう向き合ったら良いの?ということを書くことにしました。店長が育児をしていた頃は『ワンオペ育児』という言葉はありませんでした。それ以前に他人の子育てを知る機会は少なく、インターネット上に今のように子育て情報が溢れている時代でもありませんでした。そのようなわけで、手探りの子育てだったのですが、意識的に『ワンオペ育児』にはならないようにしていました。どんなに優しい母親でも、家事が大好きな母親でも、小さなこどもの命を一日中・長い期間1人でみることでのしかかる責任・ストレスの重さは比べ物になりません。
「人の生」をその手に抱えながら、毎日寝る時間もままならず生活をしていれば、苦しくなるのは当たり前です。でも、多くの父親は働き盛り・稼ぎ盛りという時期で、外でのストレスや仕事での責任にこれまた「家族の生」を背負って働いていると考える人も多いと思います。この埋まらない溝。さて、これは多くの家庭で起こっているどこにでもあることです。
実際問題、家で働ける店長ですら毎日ずっと家にいることは困難だったので、『孤育て』である以上は、どこかでは『ワンオペ育児』をお願いしなくてはならない日はありました。その時にどのようにしたら良いのか?店長なりの経験を少し書くことで、誰かの役に立つのではないかと思って書いてみることにしました。

いろや商店の店長のおおま(@iroyaonline)です。
ご覧いただきましてありがとうございます。
育児・子育て苦手な店長が、こどもが主役で書いてますのでゆっくりご覧くださいませ〜。

会員登録ですぐに使える!
ワンオペ育児と父親
店長自身が育児をしていた頃を思い出して、店長なりにまずは『ワンオペ育児』がどのようにして出来上がるのか?を思い出しながら整理してみることにしました。
『ワンオペ育児』になってしまう理由は様々ですが、基本的にワンオペ育児をする側は、妻(奥さん)になるケースがほとんどです。夫側の育児参加が強く叫ばれてはいますが、まだまだ育児・子育て現場の中心はお母さんです。そして夫側は育児・子育て・家事については仕事をしている時間以外の空いた時間に手伝い程度でという家庭がまだまだ多い状況です。(実際に店長もそうでした。)そして残念ながら夫婦で一緒に子育てをするというよりも、妻の子育てに協力するという立場で育児・子育ての状況にいる夫はとても多いです。実際に、店長も育児・子育てをしていた頃は、妻の手伝いという意識からスタートしました。
でも、それだとうまくいかない。それから変わりました。
さて、店長の周りを見てもこどもが産まれる頃の夫婦は、共に仕事で一番働き盛り・稼ぎ時であることが多いです。
会社における責任も大きくなり、仕事で得られる成果や楽しさもとても大きなものとなっているタイミングです。こどもの出産のタイミングでこれらを失う怖さ。は、『こどもは要らない』と考える人が増えていく理由の一つだとも感じてます。
女性の社会進出や、働き方改革など、働き方の多様性が広がる中で、店長のようにフリーランスで働いていた人もいれば、夫婦で会社勤めの人、2世帯住宅などで一緒に親族と暮らしている人など、暮らし方も多様になりました。その中でも『ワンオペ育児』になりやすいのは、夫婦共に仕事を一生懸命して、お互いの親族から離れて独立して暮らし、その後結婚し、こどもが生まれた場合です。親族から離れ、しっかりキャリアを重ねて結婚。こどもが生まれたごくごく身近にある家庭に起こる問題の一つです。
店長家族も親族から離れ、遠い地(出身はお互い青森県)から関東へ引越しをして来ました。
仕事で築いて来た人間関係と、生活環境。
こどもが生まれるとこれらは大きく変化します。
こどもと一緒にいて家事に育児と大変な時間帯、今まで一緒に過ごしていたお友達などは働いていることが多いので、会社や外出先などで人の輪の中で暮らしていた日々から、家の中にいることが多くなり急に孤立することになります。『ワンオペ育児』は、このようにしてちょっとした何気ない生活環境と暮らし方の変化から始まります。
店長が感じたことでもありますが、『ワンオペ育児』は、夫婦どちらも頑張っているからこそ起こることです。
そして、これを乗り越えるためには、今までの生活の中でできていたことなど何かを妥協しながら、協力し合うこと、話し合うことが不可欠だと感じました。
ワンオペ育児、その時『夫(父)』は?
妻側にとっては『出産』という絶対に休まないと乗り越えられないことがあるため、今まで築いて来た仕事・キャリアから一旦退いたり、今後の仕事・キャリアを諦めるといった選択に迫られる場合も多いですが、夫側は、こどもが産まれるからといって自身のキャリアを諦めたり、方向性を考え直したりとはなかなかなりません。最近は育休制度も少しずつ浸透してきたので、妻側(女性)がキャリアを諦めなければいけないということは少なくなってはきましたが、それはある程度の規模がある会社の場合です。
数十人規模の小さな中小企業の場合、一人抜けると他にしわ寄せが行くため周りに気を遣いますし、会社に出ていない育休中スタッフへの給与を保証する余裕がない会社もあります。
そして夫側に求められるのは、社会全体でも「こどもが生まれたらもっと稼がなきゃね!」と、仕事へ打ち込もうね的な空気が漂うので、育休をとったり、育児や子育てのために家での時間を増やそうという気持ちが折られます。女性の社会進出の変化にあわせて、男性側の社会でのあり方も変化が求められています。
これが『ワンオペ育児』に拍車をかけていきます。実は、こどもが生まれた時の夫側はさらに仕事での役割が増える場合があります。
出張が増えたり、激務が増えたり、責任が増えたり。
会社としてはこどもが生まれると、より責任の重い仕事を任せていきます。
会社員としては、ついに手に入れた会社からの『信頼の証』でもあるのですが、その反面、会社側としては仕事へさらに打ち込ませるチャンスとも捉えています。こどもができた後は、なかなか転職はしにくいものなので、有能な社員ならできる限り会社にそのまま長く骨を埋めて欲しいと考えることが多いですから、夫側は仕事で与えられる責任が重くなるケースもあります。
実際のところ、店長自身もこどもが生まれるタイミングは夫婦にとって、仕事への向き合い方のターニングポイントにもなる時期と実感しました。
妻にとっては、一時的にせよ長期にせよ必ず仕事・家事などから離れなければいけません。
お互いの仕事への向き合い方を変えずいくか・家庭の時間を増やすかという、ふたつの分かれ道を、夫婦間でハッキリ共有することが大切になります。まわりをみても、こどもが産まれるタイミングでの仕事に対しての温度差が、その先の『ワンオペ育児』に繋がる一つの原因だと感じました。このタイミングで、夫婦でどちらが良いかよく話し合い、場合によっては共に仕事の仕方を変えるということも必要になります。
様々な社会制度も充実してはきていますが、最終的に自分たちの生活を守るのは、自分たちになります。悔いのないように、はっきりと決めるのが良いです。ただ今後は「こどもが主役」な社会へと変わっていくといいなぁと思っています。
ちなみに店長の場合は、両方(仕事も家庭も)を求めてしまいました。
育児・子育てを大車輪で頑張ろうとした結果うまくいきませんでした。自由時使える時間が減る中で、仕事で稼ぎを増やしつつ、家庭の時間を増やすなんてそんなに都合よくいくはずはないのです。冷静に考えたら火を見るよりも明らかなのですが、若気の至りですかね。当時は体力もありましたし、その時は頑張れる!と思いました。
店長の場合、結果的に家庭の時間を増やす方を選択し、仕事時間を大きく削ることにしました。その影響もあって、稼ぎは大きく減ることとなります…。
ワンオペ育児は、夫側の『育児参加』が大切なの?
育児・子育て、そして家事などについて、世の中の風当たりは年々強くなっていますね。(苦笑)
世のお父さんの中には、『ワンオペ育児』を解決したい!と意気込んで、仕事が休みの日や、自分に余裕がある時に家事手伝いをしている人は多いと思います。夫側としては育児に参加している!手伝っている!俺はこれでイクメン!と思ってしまいそうですが、実はそこに大きな落とし穴があります。(しないよりはマシですけども。)
実はこのような状況では、夫側の都合で手伝っているだけで、育児に参加しているとは言えないのです。
『育児に参加する』というのは、夫側もいろいろなことを削ってまさに『身を以て参加する』ことなので、手伝うではないのです。
一緒になって、子育てに揉まれることが大切!そのためにはそれなりの覚悟が必要です。
店長もとても苦しいことばかりでした。『育児』は、綺麗ごとだけじゃないのです。(苦笑)
そして、父親にとって『育児・子育て』のイメージを掴むのがまだまだ難しい時代です。
店長の場合は、父親とあまり過ごす時間がなかったため、父親像!という固定観念がありませんでしたので、自分自身で学びながら父親像というのを作ってきました。でも周りの知り合いの父親を見ると、24時間働けますか!という仕事人間の世代の方が圧倒的に多く、幼少時期から男性に求められることも家事などよりも仕事での活躍を強く願われて、育てられた方も多いでしょう。そのため、これからの時代はお父さんも育児に参加だ!と言われても、ロールモデルになるような存在が自分自身の周りにない場合がほとんどです。
でも、周りや妻からは育児参加を求められることは多く、手探りの状態。これは母親もですが、父親もそうなのです。
時代の変化を受け入れられる人もいますが、変化をおそれ変化しないことを選択する気持ちも理解できます。
そして、この『育児参加』という表現がまた誤解を生みます。
はっきりしていることは、父親にとって育児は、そもそも『参加』するものではなく、しなければいけないことです。
『育児参加』という言葉は、どこから妻に協力する立場で自分ごとではないといったイメージでも捉えられるようです。でも、多くのお父さんは育児への参加は大切だと感じています。育児・子育てにしっかりと向き合いたい!でも、育児・子育てへのの向き合い方がわからなかったり、想像力が少なかったり、イメージができないという場合もたくさんあります。もちろん、父親の中には育児・子育てににそもそも無関心な人もいます。
でも、こどもを育てるのは夫婦お互いに責任があるので、お母さんだけ、お父さんだけということはないのです。
夫側にとっても育児への参加は必要というよりも、育児・子育てはしなければいけないことです。
ワンオペ育児の解決策は?父親は育児から逃げても良い?
夫婦間で育児の際に協力して欲しいこと・求められることは10人10色です。
家事の場合もあれば、こどもと遊ぶこと、精神的なサポートなど、それらを夫婦間で共有し、お互い支え合うことが何よりも大切です。100点パパ・100点ママは居ないので、お互い支え合わないとなかなか育児はうまくいきません。
ママだから育児・子育てが得意ということはないですし、パパだから仕事が得意ということもないのです。
日々過ごしやすく、そして何よりも『こどもが主役』で考えながら家族での暮らしを作っていくことが求められます。
そして、父親が育児から逃げると、母親一人で育児に向き合うことになります。これは辛いです。
いろいろなことから逃げてきた男性も、育児・子育てからは逃げてはダメです。
当店では、子育ては『子を育む』ことだと考えています。
『こどもを見ている』ことではないのです。
なので、夫婦それぞれが協力しあって支え合い、こどもを一緒に育んでいくことが育児では求められます。
その時に最も必要になるのは『夫婦間でのコミュニーケーション』です。お互いに、今何を求めているのか、何が足りないと感じているのかを常に話し合いながら一歩ずつ物事をクリアーしていくことが育児では求められます。
初めてのこどもの場合はお互いは子育て若葉マークです。夫婦で一緒に考えながら進んでいかないとなかなかうまくいきません。
もしかすると、妻が必要として居たのは食事の手伝いではないかもしれない。
夫が必要として居たのは、掃除ではないかもしれない。
という風に、実は育児・子育ての一部と考えて手伝っていたことが、双方の意図していたことではないという場合も多々あります。
店長も、息子が小さい頃は一生懸命、育児・子育てと思ってありとあらゆることを手伝いました。
できることは片っ端からしたような気がしますが、逆にやり過ぎてしまって、一時期は主夫のようになり、かえってお互い苦しくなってしまったのを覚えています。イクメン!の大きな波も訪れ、大きく取り上げられていた時期でもあり、それに反応してできることを探し、なんでも実践してみましたが、動くことばかりに気を取られて、奥さんの話をよく聞いたり、サポートしたりというところには頭が回りませんでした。
ワンオペ育児になる原因の一つに、夫婦でのコミュニケーション不足があると感じています。
正直なところ、店長自身の育児・子育ては課題ばかりでした。でも、そのおかげで経験できたこともあったので、少しでもこういう形で世に出せればと思って書いてます。
夫に育児・子育てへ向かってほしいと感じた奥さんがこのページを開いたら、このページを夫にシェアして読んでもらってください。(笑)
ワンオペ育児!解決の道は?
『ワンオペ育児』の解決の道は、上にも述べた通りで『こどもが主役』で考えながらの夫婦間のコミュニケーションだと店長は考えています。
お互いの状況を客観的に見て考え方をよく話し合い、解決の道を模索していくことが大切です。『ワンオペ育児』に陥る原因はそもそもが親族から離れていたりと、すでに『孤育て化』していて育児・子育てに一人で向き合わなければいけない状態であることが多いです。夫婦で助け合わないと、妻もしくは夫による『日常的なワンオペ育児』が完成されてしまう一歩手前にいるという状況を、客観的に認識するのはとても大事です。
そうならないように、よく話し合い、暮らし方を工夫していくことが夫婦の前に立ちはだかる大きな山となります。
店長も、奥さんの入院により息子が2歳の頃2・3ヶ月くらい『ワンオペ育児』になりました。
1人で仕事をして、1人で朝・昼・晩の食事・家事、そして入院のお見舞いへ毎日行っていたのを覚えています。
今となってみればどのように過ごしていたのか全然記憶になくて、ただただ毎日一生懸命必死に暮らしていたことくらいしか覚えていません。もっと多様な選択肢があったはずなのに、その頃の自分自身には見つけることができませんでした。そういう意味でも、周りに協力してもらえる人を増やしたり、サービスを利用したりなど、育児・子育ての選択肢があるのは、『ワンオペ育児』の解決策の一つになります。
そして『ワンオペ育児』は、夫婦の絆をさらに強くするチャンスだと店長は感じています。
こどもという大切な命を中心に夫婦二人で協力することなので、家族はもちろんのこと夫婦の絆を強くするチャンスでもあるのです。一つの大きな山を乗り越えられれば、次の険しい山も乗り越えられるたくましさを身につけられるのではないでしょうか?
ということで、『ワンオペ育児』になりかけているご夫婦・すでになっているご夫婦。いずれにおいてもこの記事がきっかけで、より良い方向に進めば店長何よりもよかったな…と思うのでした。でも、夫婦のコミュニケーションをどうやって増やして行くのか。これもまた難しいことです。それについてはまた改めて書いていきたいと思います。
そんなわけで店長は、『こどもが主役』でみんなで考え過ごす中で、こどもと穏やかに過ごす時間が増やせる暮らしを見つけられればと思います。